親の介護が必要になったとき、多くの人が直面する問題が「費用」のこと。「施設に入れたいけどお金が足りない」「そもそも介護費用はどのくらいかかるの?」と不安を感じる方も多いでしょう。
そこで本記事では、介護費用の平均額や支払い方法、補助制度、足りない場合の対処法を詳しく解説します。さらに、家族での話し合いのポイントも紹介します。事前に情報を知っておくことで、スムーズな対応が可能になります。
関連記事はこちら→親の介護をしたくない…しないとどうなる?負担を減らす方法と現実的な対処策

介護福祉士・ケアマネジャー・社会福祉士
中谷ミホさん
介護福祉士、社会福祉士、ケアマネジャー、保育士。福祉系短大を卒業後、介護職員・相談員・ケアマネジャーとして介護現場で20年活躍。現在は介護業界での経験を生かし、介護に関わる記事を多く執筆。介護・福祉関連書籍の監修も手掛けている。 X(旧Twitter)
親の介護費用の平均額と詳細(在宅・施設別)

親の介護にかかる費用は在宅か施設かによって大きく変わります。加えて、要介護度や個人の状況、利用するサービス内容によっても異なるため、まずは平均的な金額と内訳を知ることがポイントです。ここでは在宅介護と施設介護の費用を解説し、それぞれの費用目安や注意点をご紹介します。
在宅介護と施設介護の平均額
生命保険文化センターの調査によると、介護費用の平均は月に8万3000円とされています。在宅介護と施設介護でかかる費用の平均額は以下の通りです。
・在宅介護:平均約4.8万円/月
・施設介護:平均約12.2万円/月
このように、施設介護の月額費用は、在宅介護の2~3倍になる傾向があります。また、一般的に介護期間の平均は5年程度であり、介護にかかる総費用は500万円程度になるとされています。
※参照元:公益財団法人生命保険文化センター「介護にはどれくらいの費用・期間がかかる?」
在宅介護の費用詳細

在宅介護では、自宅に住み続けながら必要な介護サービスを利用します。費用の内訳を以下で見ていきましょう。
介護サービス利用料
在宅介護での介護サービス利用料は、介護保険を利用する場合、自己負担は1~3割です。主なサービスの料金目安は下記の通りです。
| 訪問介護(ホームヘルパー) | 1回あたり数百円程度の自己負担。利用するサービス内容(身体介護・生活援助)や利用回数で変動します。 |
| デイサービス(通所介護) | 1日利用で1,000~2,000円前後が目安。利用時間や要介護度、施設の規模により変動します。 |
| ショートステイ(短期入所) | 1泊2日で3,000~8,000円程度。宿泊する施設の種類や要介護度により変動します。 |
介護サービスは、要介護度ごとに決められた月額利用限度額(介護保険の支給限度額)以内であれば1~3割の自己負担で利用できますが、限度額を超えてしまうと超過分を全額自己負担することになるため注意が必要です。ケアマネジャーと相談し、無駄のないサービス利用計画(ケアプラン)を立てる必要があります。
※参照元:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」 「訪問介護(ホームヘルプ)」 「通所介護(デイサービス)」「ショートステイ」「サービス利用者の費用負担等」<居宅サービスの1ヶ月あたりの利用限度額>
生活費(食費・光熱費・医療費など)
在宅介護の場合、日常の家計に加え、介護に伴う出費が増えます。
・食費:自炊や配食サービスによって異なりますが、月3~5万円が目安です。
・光熱費:エアコンの稼働時間の増加などでややアップします。
・医療費やおむつ代:要介護者の体調によって大きく変動します。
施設入居と比べると住宅費や管理費が不要というメリットがありますが、その分、家族の協力やそのほかの費用(送迎・見守りサービスなど)が発生する場合もあります。
住宅改修や介護用品の費用
安全に自宅で生活を送るための住宅リフォームや、介護用品が必要になることがあります。
・住宅改修費(手すり設置・段差解消など):介護保険を利用すれば、生涯20万円まで、1~3割負担で改修工事が可能です。
・福祉用具レンタル(介護ベッドや車いすなど):保険適用であれば月700~1,200円程度の自己負担で利用可能です。
・入浴・排泄用具の購入費:年間10万円まで支給を受けられる制度があります。
なお、在宅介護を始める際のバリアフリー工事や介護用ベッドの購入費用として、平均74万円が必要です。
要介護度別の月額費用の目安(在宅介護の場合)
要介護度別の月額費用の目安は以下の通りです。
| 要介護度 | 月額費用の目安 |
|---|---|
| 要介護1 | 5万3,000円 |
| 要介護2 | 6万6,000円 |
| 要介護3 | 9万2,000円 |
| 要介護4 | 9万7,000円 |
| 要介護5 | 10万6,000円 |
要介護度が上がるほど多くのサービスを必要とし、費用も増加する傾向があります。
施設介護の費用詳細

高齢者施設にはさまざまな種類がありますが、大きく「公的施設」と「民間施設」の2つに大別されます。
公的施設は、地方自治体や社会福祉法人が運営し、行政が管轄する施設です。所得や要介護度を考慮して費用が抑えられるのが特徴です。
代表的な施設:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、ケアハウスなど
民間施設は、民間企業が運営する介護施設です。高級な施設から低価格帯の施設まで幅広く、入居一時金や月額利用料に大きな差があるのが特徴です。希望するサービスや入居する人の経済状況に合わせて選ぶことができます。
代表的な施設:介護付き有料老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅など
施設でかかる費用
施設介護では、入居一時金のほか、施設介護サービス費や居住費(家賃)、食費、医療費といった月額利用料が必要になります。
【入居一時金】
| 公的施設 | 介護保険施設(特養・老健・介護医療院)は0円 |
| 民間施設 | 0円のところもあれば、数百万円単位の一時金が必要な施設もある |
民間施設では、一時金を多く支払うほど、月額料金が安めに設定されているケースもあります。逆に入居一時金ゼロの施設は、毎月の支払いが割高になる傾向があります。
【月額利用料】
月額利用料の内訳は次の通りです。
| 施設介護サービス費 | 施設に入居し、介護サービスを受けるための費用です。介護保険が適用されるため、所得に応じた1~3割を自己負担します。 |
| 居住費 | 部屋の広さや設備・タイプによって差があります。公的施設と民間施設では、金額に大きな開きがあります。 |
| 食費 | 食材費や管理費などが含まれ、施設によっては外部委託の費用なども加わります。 |
| 日常生活費 | 理美容代、イベント参加費、オムツ代などが含まれます。 |
| 医療費 | 診察や投薬など、状態によって異なります。 |
施設タイプ別の費用相場
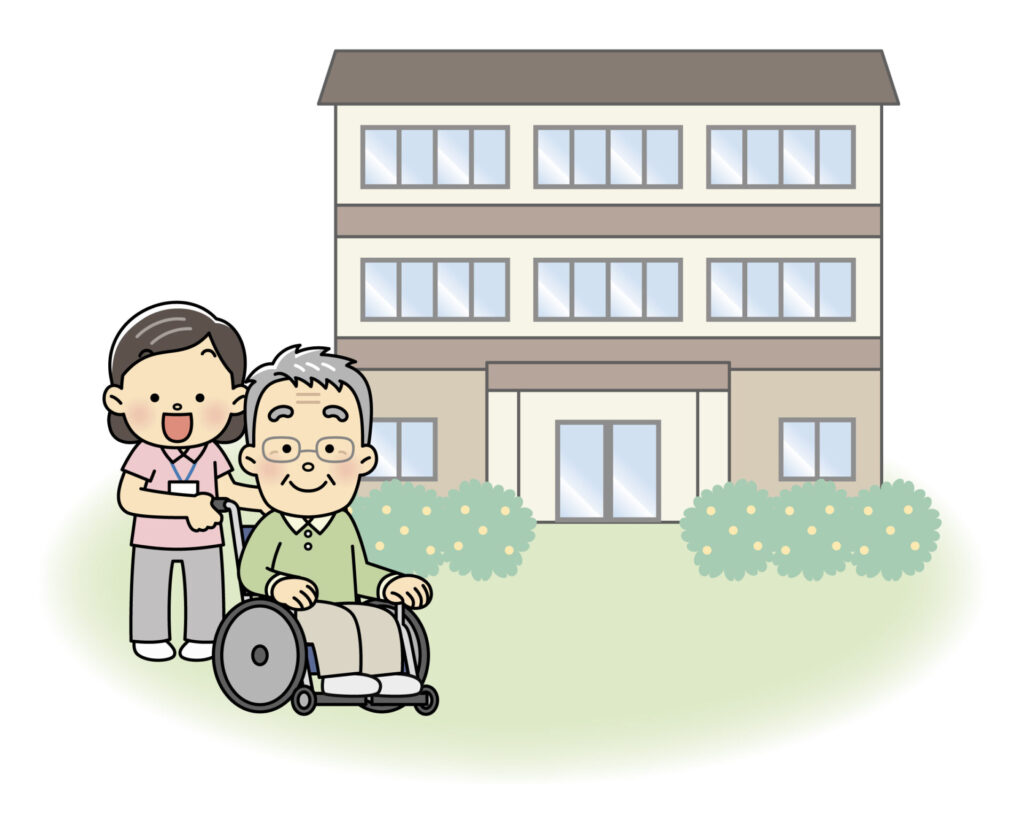
代表的な施設とその費用目安は次の通りです。
特別養護老人ホーム(特養)
| 入居一時金 | 不要 |
| 月額利用料 | 10~15万円程度 |
| 特徴 | 所得に応じた減額制度があり費用は抑えやすい。ただし待機者が多く入居が難しいケースも。 |
介護老人保健施設(老健)
| 入居一時金 | 不要 |
| 月額費用 | 6~16万円程度 |
| 特徴 | リハビリを中心とした在宅復帰支援施設。医療ケアやリハビリの専門職が常駐。ただし原則3カ月程度と短期利用が基本。 |
介護付き有料老人ホーム
| 入居一時金 | 0~数千万円 |
| 月額利用料 | 平均20万円前後。高級施設では100万円以上 |
| 特徴 | 手厚い介護サービスが魅力。入居一時金を抑えるプランもあるが、その分月額費用が高くなる傾向がある。 |
認知症高齢者グループホーム
| 入居一時金 | 0~100万円程度 |
| 月額費用 | 15~20万円程度(家賃・食費・介護サービス自己負担などを合計) |
| 特徴 | 認知症の高齢者向け小規模共同生活施設。自治体により家賃補助制度が利用できる場合あり。 |
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
| 入居一時金 | 0~数十万円程度が多い |
| 月額費用 | 10~40万円ほど |
| 特徴 | 高齢者が安心して暮らせるバリアフリー設計で、安否確認や生活相談などのサービスが付く。介護サービスは外部と連携するケースが多く、必要に応じて利用料が追加発生する。 |
【高齢者施設の費用目安】
| 種類 | 入居一時金の目安 | 月額費用の目安 | 入居対象 | |
|---|---|---|---|---|
| 公的施設 | 特別養護老人ホーム | 0円 | 10〜15万円 | 要介護3〜5(特例で要介護1・2) |
| 介護老人保健施設 | 0円 | 6〜16万円 | 要介護1〜5 | |
| 介護医療院 | 0円 | 6〜17万円 | 要介護1〜5 | |
| ケアハウス | 0〜500万円 | 6〜17万円 | 自立・要支援・要介護 |
| 種類 | 入居一時金の目安 | 月額費用の目安 | 入居対象 | |
|---|---|---|---|---|
| 民間施設 | 介護付き有料老人ホーム | 0〜数千万円 | 20万〜100万円 | 自立・要支援・要介護 |
| 住宅型有料老人ホーム | 0〜数千万円 | 20〜100万円 | 自立・要支援・要介護 | |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 0〜数十万円 | 10〜40万円 | 60歳以上、もしくは要介護認定者 | |
| 認知症高齢者グループホーム | 0〜100万円 | 15〜20万円 | 認知症の診断要支援2〜 |
※参照元:厚生労働省「介護報酬の算定構造」
施設への入居期間は平均5年とされていますが、長期化することもあります。また、どの施設に入居するかによってかかる費用も大きく変わります。そのため、無理なく支払っていける施設を選ぶことが大切です。
親の介護費用は誰が出す?一般的な負担の実態

親の介護費用は「親本人のお金」が基本
親の介護費用は、まず 「親本人のお金」から支出するのが基本です。高齢の親であれば年金を受け取っているケースが多く、これまでの貯蓄を取り崩して介護費用に充てるのが原則となります。
介護施設の費用負担の実態
実際、ある調査によると、介護施設の費用を「入居者本人(要介護の親)」が負担しているケースが約6割と最も多いという結果が出ています。そのため、まずは親本人の収入(年金や不労所得)や預貯金でどこまでまかなえるかを確認する必要があります。
親の収入や貯蓄だけでは足りない場合も
しかし、親の収入や貯蓄だけでは、介護費用をまかないきれないケースも少なくありません。特に、貯蓄が十分でない高齢者も多く、厚生労働省の「国民生活基礎調査」(2019年)によると、高齢者世帯の14.3%が「貯蓄がない」 と回答しています。
不足分は「子ども」が負担することが多い

親の資産だけでは不十分な場合、次に頼るのは子どもによる経済的支援です。調査によると、介護施設の費用を子どもが負担しているケースは24.8%(約4人に1人)にのぼっています。つまり、親の介護費用の約4分の1は子ども世代が負担しているのが現状です。
配偶者が負担するケースも
子ども以外では、介護される人の配偶者(例えば、母親の介護を父親が負担する、またはその逆)が負担するケースもあります。調査では、配偶者が負担している割合は6.4% で、その他(孫や兄弟姉妹、知人、公的扶助など)はごく少数でした。しかし、配偶者も高齢で収入が限られる場合が多いため、やはり不足分は子ども世代が負担する形になりやすいのが実情です。
親の介護費用と「扶養義務」
親の介護費用について考える際に知っておきたいのが、扶養義務に関する法律です民法877条では、「直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と規定されており、これは親子関係にも適用されます。
また扶養義務には、日常の世話などの身体的サポートだけでなく、生活費や介護費用の援助といった経済的扶養も含まれるため、法律上、子どもは親の介護費用を負担する義務があるとされています。
扶養義務の範囲と負担の限界
ただし、ここで重要なのは 扶養義務の程度や範囲です。民法の扶養義務は「自分の生活に余裕がある範囲で」扶養することを求めると解釈されています。つまり、「子どもは自分の生活を犠牲にしてまで親を扶養する義務はない」ということです。
子ども側に経済的余裕がなければ、結果的に親の介護費用を十分に負担できなくてもやむを得ないという考え方になります。そのため、親に年金や貯蓄などの資産がある場合は、原則として親本人の資産から費用を支出するのが自然だと言えるでしょう。
親の介護費用を軽減する公的制度
次に、介護費用の負担を減らすために活用できる制度を紹介します。
介護保険制度

介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支える公的な保険制度です。2000年に創設され、原則40歳以上の方が加入して保険料を納めることが義務付けられています。
介護サービスが必要となったときには、利用者はサービス費用の一部(1~3割)を自己負担し、残りを保険給付でまかないます。また介護保険の対象は、65歳以上の人(第1号被保険者)、40~64歳で特定疾病がある人(第2号被保険者)です。所得に応じて自己負担割合が異なり、原則1割負担ですが、現役並みの所得がある場合は2割または3割負担となります。
介護保険制度を利用するには、お住まいの市区町村の介護保険窓口に申請し、要介護認定を受ける必要があります。
※参照元::厚労省「介護サービス情報公表システム」「介護保険とは」
高額介護サービス費制度
介護保険サービスの自己負担額が月単位で高額になった場合に、一定の上限額を超えた分が払い戻される制度です。
利用者の負担が重くなりすぎないよう、介護保険から超過分を支給して経済的負担を軽減します。例えば、1か月の自己負担合計額が定められた上限を超えたとき、その超過分を後から受け取ることができます。
ただし、福祉用具購入費や住宅改修費、施設の食費・居住費など介護保険給付の対象外となる費用はこの自己負担額に含まれないため、注意が必要です。
高額介護サービス費の対象となる場合、サービス利用月の後に自治体から申請書が送付されます。届いた申請書に必要事項を記入し、市区町村(介護保険担当窓口)へ提出することで払い戻しを受けられます。
※参照元:厚労省「介護サービス情報公表システム」<高額介護サービス費>
生活保護の介護扶助

生活保護の介護扶助は、生活保護を受給している方が介護サービスを利用する際に必要な費用を支援する制度です。生活保護法に基づき、介護サービスや福祉用具の貸与などを提供します。
介護扶助の対象となるのは、生活保護を受給している方で、介護保険法に基づく要介護状態または要支援状態にある方です。具体的には、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者が含まれます。第2号被保険者の場合、生活保護を受給していると医療保険に加入できないため、「みなし2号」として扱われ、同様の条件で介護サービスを受けることができます。
介護保険負担限度額認定制度(補足給付)
介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)に入所またはショートステイを利用する際、介護サービス費の自己負担とは別に発生する食費・居住費(部屋代)の負担を軽減する制度です。
所得や預貯金の額が一定以下の人を対象に、1日あたりの食費・居住費の上限額(負担限度額)を設け、費用負担を軽減します。上限額を超えた費用は、介護保険から支給されます。
負担限度額は、所得区分(第1~第3段階)ごとに異なり、例えば 第1段階(生活保護相当) では、特別養護老人ホームの多床室の居住費は0円、従来型個室は380円、ユニット型個室は880円に減額されます。また、食費は1日あたり(1食あたりではなく1日3食合計)300円に抑えられます。
注意点として、一般の有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅といった民間施設には適用されません。また、減額を受けるには所得だけでなく預貯金等の資産要件も厳格にチェックされます。まとまった預金や不動産を所有している場合は、収入が低くても対象外になることもあるため、あらかじめ理解しておきましょう。
なお、施設によっては入所時にこの認定証の有無を確認されますので、条件に該当する場合は早めに市区町村に申請し取得しておくと安心です。
※参照元:厚労省「介護サービス情報公表システム」<特定入所者介護サービス費(補足給付)>
高額医療・高額介護合算療養費制度

医療保険と介護保険の両方を利用している世帯に対して、自己負担額を軽減するための制度です。
この制度は、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、その合計が設定された限度額を超えた場合に、超過分が払い戻される仕組みです。
この制度の対象となるのは、以下の条件を満たす世帯です。
・医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度)に加入していること
・1年間の医療保険と介護保険の自己負担合算額が、各所得区分に設定された限度額を超えた世帯
なお、基準額(年間自己負担限度額)は、世帯の所得や年齢に応じて設定されています。例えば、一般的な所得(年収156万~370万円程度)の70歳以上の世帯では、年間の上限額は56万円とされており、自己負担額の合計がこの金額を超えた場合に払い戻しを受けることができます。
該当する方には、医療保険者から通知が届きます。ただし、申請しなければ適用されないため、忘れずに手続きを行いましょう。
※参照元:厚労省「介護サービス情報公表システム」<高額医療・高額介護合算制度>
障害者手帳の取得
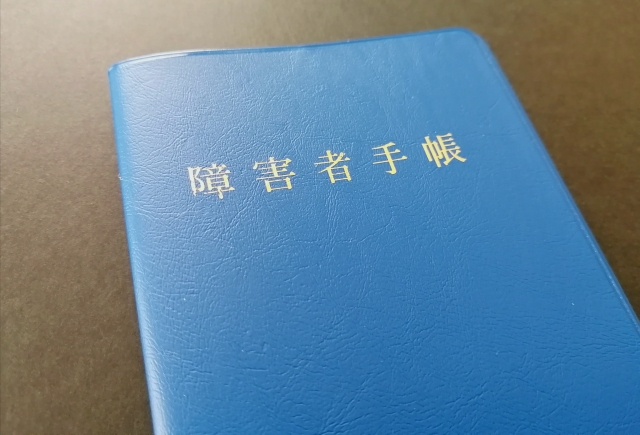
障害者手帳は年齢制限なく申請可能で「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。
例えば、認知症の方で日常生活に支援が必要な方は精神障害者保健福祉手帳の対象に、視覚や聴覚の障がいや、脳卒中後の後遺症で手足のマヒなどがある方は身体障害者手帳の対象です。
障害者手帳を取得すると、高齢者でなくてもさまざまな公的支援や優遇措置を受けられます。具体的には、公共交通機関やタクシー、高速道路料金の割引、NHK受信料の減免など日常生活の費用負担軽減につながるものです。これらは介護費用そのものではありませんが、移動や生活コストを下げることで介護に充てられる家計の余力を増やすことができるでしょう。
加えて、障害者手帳所持者本人やその扶養家族には税制上の優遇(障害者控除)が適用され、所得税・住民税の課税額が減るため経済負担が軽減されます。例えば同居の親が手帳を取得すると、扶養者である子の課税所得から最大75万円(所得税の場合)の控除を受けられます。
※参照元:厚生労働省「障害者手帳」 国税庁「障害者控除」
自治体独自の支援制度

各自治体では、国の制度に上乗せして独自に介護費用を補助する施策を実施しています。以下はその一例です。
家族介護慰労金(例:大阪市)
要介護度が重度(要介護4または5)の高齢者を、介護保険サービスを利用せずに在宅で1年以上介護している家族に対し、自治体が慰労金を支給する制度です。大阪市では、要介護者・介護者とも市内在住1年以上、介護者は同居の親族等、世帯全員が市民税非課税といった条件を満たす場合に年10万円の家族介護慰労金が支給されます。
紙おむつ支給(例:静岡市)
重度の要介護高齢者には、失禁対策などの介護用品費も負担になります。静岡市では在宅の要介護高齢者に対し、紙おむつ引換券を毎月支給する独自制度があります。
介護タクシー券の交付(例:吹田市)
要介護高齢者の通院・外出支援として、タクシー利用料を助成する自治体もあります。吹田市では「通院困難者タクシークーポン券」を発行し、65歳以上・要介護1以上で市民税非課税世帯の在宅高齢者に対しタクシー料金の一部を補助しています。
介護付有料老人ホームの居住費補助(例:江戸川区)
特別養護老人ホーム(特養)の入所待機者の解消を目的として、介護付有料老人ホームの居住費補助を実施しています。この制度では、特養と介護付有料老人ホームの居住費の差額(一律6万円)の2分の1を、月額上限7万円まで補助しています。
以上のように、自治体独自の支援制度は多岐にわたります。各自治体によって制度が異なるため、お住まいの市区町村の窓口で確認するとよいでしょう。
※参照元:大阪市「家族介護慰労金」静岡市「高齢者紙おむつ支給制度」吹田市「通院困難者タクシークーポン券」江戸川区「介護付有料老人ホーム居住費補助(江戸川区特別養護老人ホーム待機者解消対策事業)」
施設に入れたいがお金がないときの対処法
施設入居のための資金が足りない場合、次のような方法を検討しましょう。
①金融機関の介護ローンや国の貸付制度を利用する

銀行や信用金庫などの金融機関が取り扱う介護ローンを利用する方法があります。これは、入居一時金や入居に関わる費用などに充てられるローン商品で、受け取る年金額や将来的な収入を見込んで返済計画を立てることが一般的です。
また、社会福祉協議会が行う貸付制度を利用するのも一つの方法です。一定の所得要件や保証人の有無などを満たすことで、低金利もしくは無利子で借り入れができる場合もあります。介護費用だけでなく、生活費とのバランスも考慮しながら家族やケアマネジャーとよく相談して決定するとよいでしょう。
②自宅を売却して資金に充てる

所有している自宅を売却し、その売却益を施設の入居費用や毎月の支払いに充てる方法も考えられます。
まずは、専門の不動産業者に依頼し、現在の資産価値を査定してもらいましょう。ただし、注意点として、売却価格が予想よりも低くなる場合や、買い手が見つかるまでに時間を要することがあります。そのため、売却後の引越し時期と施設への入居時期を慎重に調整しましょう。
また、譲渡所得税や不動産仲介手数料といった経費も考慮し、実際に手元に残る金額をシミュレーションしておくことも重要です。
③自宅を担保にして融資を受ける

自宅などの不動産を担保にして融資を受ける方法として「リバースモーゲージ」という制度を利用するのも一つの方法です。この制度は、契約者が生存中に支払うのは利息のみで、元金は契約者の死亡後に不動産を売却し、その売却代金で借入金を相殺する仕組みです。
特に、子どもが独立し、実家に住む人がいなくなった場合に活用しやすいといえます。ただし、借入期間が長くなると利息の負担が大きくなるため、注意が必要です。また、多くの場合、利用には相続人の同意が求められるため、事前に家族で十分に話し合っておきましょう。
※参照元:りそなグループ「リバースモーゲージとは?仕組みやメリット・デメリットを詳しく解説」
親の介護に備えて家族間で話し合うべき5つのポイント
介護には想像以上に費用や手間がかかるため、事前に家族間で方針を共有しておくことが大切です。ここでは、親の介護費用について家族で話し合う際に押さえておきたいポイントを紹介します。
①親の希望を確認する

まず、親がどのような介護を望んでいるかを確認しましょう。例えば、住み慣れた自宅で介護を受けたいのか、それとも設備の整った介護施設へ入居したいのか、といった希望です。
親の希望を事前に把握しておけば、その意向に沿った介護プランや費用の準備がしやすくなります。
②資産・収入の把握

介護費用を試算するには、親の経済状況(年金収入、預貯金、加入している保険など)を把握しておくことが欠かせません。
介護費用の目安として、在宅介護では月4.8万円、施設介護では月12.2万円程度かかるとされています。親の年金や貯蓄でどこまでまかなえるか、不足する分を誰が負担するのかについて、家族で話し合いましょう。資産状況を共有しておくことで、いざというときに備えて、子ども側で貯蓄計画を立てることも可能になります。
③兄弟姉妹の役割分担

兄弟姉妹がいる場合は、金銭的な負担だけでなく介護の実務負担も考慮して、家族間で役割分担を決める必要があります。
誰か一人に負担が集中しないよう、各自の状況に応じてできることを話し合いましょう。例えば、親と同居する子どもが日常の介護を担い、遠方に住む子どもは費用面のサポートを多めにする、といった形です。近くに住む兄弟姉妹がいれば、定期的に実家に通って介護を手伝ったり、介護サービスや医療機関との連絡調整役(キーパーソン)を担うケースもあるでしょう。
介護の労力と費用の負担ができるだけ公平になるよう工夫することが望ましいですが、役割を決めても主介護者の負担は大きくなりがちです。そのため、他の家族も定期的に様子を気遣い、サポートしましょう。
介護の状況は時間とともに変化するため、話し合いは一度で終わりではありません。定期的に家族で状況を共有し、必要に応じて役割や負担を見直すことが大切です。
④法的な手続きの検討

将来、親の判断能力が低下した場合に備えて、成年後見制度など法的な手続きを視野に入れておくことも重要です。成年後見制度を利用すれば、認知症などで判断が困難になった親に代わって財産管理や各種契約を行う「後見人」を家庭裁判所が選任してくれます(後見人を誰にするか事前に指定できる任意後見制度もあります)。
こうした制度を活用すれば、親の資産を適切に管理し、介護費用に充てることができます。また、親が元気なうちに信頼できる家族に財産管理を任せることについて話し合っておくのもよいでしょう。
認知症が進行してからでは口座凍結などにより思うように資金を動かせなくなる場合もあるため、早めに対策を検討しておきましょう。なお、具体的な手続きについては専門家に相談しながら進めると安心です。
※参照元:厚生労働省「成年後見制度とは」
③緊急時の対応を決めておく

急な入院や容体の急変など、緊急時の対応方針も事前に決めておくと、いざというときに落ち着いて行動できます。
例えば、親が倒れて救急搬送された場合、誰が病院に駆けつけるのか、他の家族へどのように連絡をとるのかといった手順をあらかじめ決めて共有しておきましょう。
また、延命治療に関する親の意思も確認しておく必要があります。心肺蘇生や人工呼吸器の使用といった延命措置を望むかどうかを事前に確認しておけば、緊急時に介護者が判断を迫られる負担を軽減できます。
家族で話し合った内容は、記録に残し、共有しておくことをおすすめします。メモやメールなどの形で文章にまとめ、兄弟姉妹全員が確認できるようにしましょう。
特に、費用負担の割合や緊急時の連絡担当者などを明確にしておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。記録を残しておくことで、家族全員が同じ情報を共有でき、万が一の際にも冷静に対応しやすくなります。
無理のない介護の選択肢を考えよう

親の介護にかかる費用は、在宅か施設かによって大きく異なります。基本的に、介護費用は親の年金や貯蓄から支払いますが、不足する場合は子どもが負担することもあります。そのため、事前に親の資産状況を確認し、どのくらいの期間・費用が必要になるかを見積もっておくことが重要です。
費用負担を軽減するには、介護保険制度や高額介護サービス費の払い戻し、自治体の補助制度を活用する方法があります。また、施設入居費が足りない場合は、介護ローンやリバースモーゲージの利用も検討できるでしょう。
介護は金銭面の問題だけでなく、家族の負担や自身の仕事・生活とのバランスも関わってきます。まずは、親の希望や資産状況を確認し、利用できる制度などを調べて、無理のない介護の選択肢を考えましょう。
▼ 当サイト「悩ミカタ」ではミドル世代(40代50代)の悩みや不安・ストレスについて各分野の専門家/カウンセラーに相談できるオンラインカウンセリングサービス「悩ミカタ相談室」を展開しています。不安な気持ち、1人で抱え込まずにまずはお気軽に相談してみませんか?

