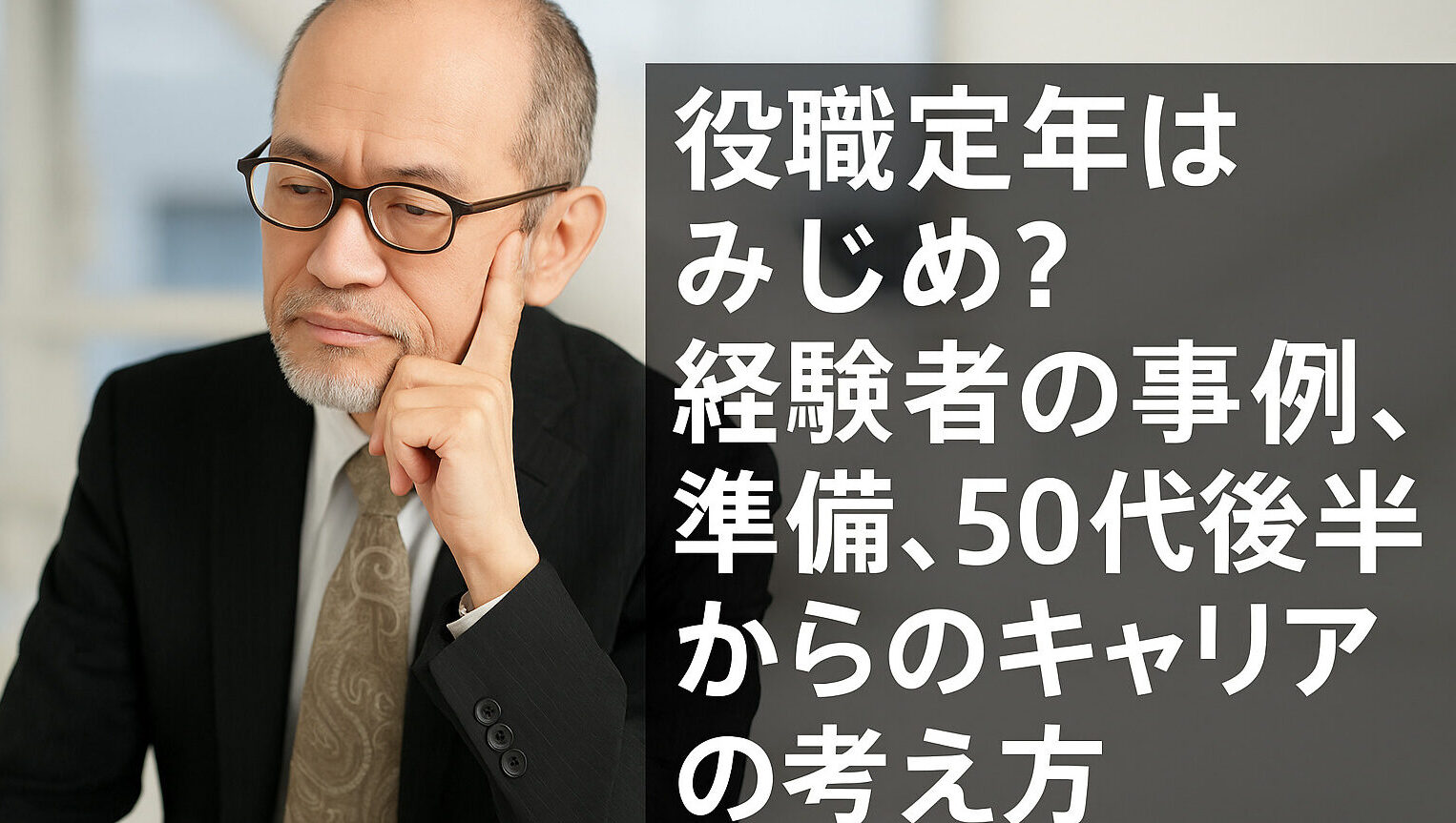「役職定年」と聞いて、あなたはどのような印象を持つでしょうか?「やりがいを失うのでは」「給料が下がるのがつらい」「社内での立ち位置が曖昧になるのでは」「みじめなのでは?」といった不安を感じる方も少なくありません。特に50代前半で近い将来に役職定年を控えている方にとっては、「みじめ」というワードが気になって仕方ないのではないでしょうか。
この記事では、役職定年の基本的な仕組みや、実際に経験した人の声をもとに「なぜ役職定年はみじめと言われるのか?」を紐解いていきます。また、役職定年後の働き方やキャリアの選択肢、今からできる準備まで幅広く解説していきます。

キャリアカウンセラー・ライター
山田葉子さん
キャリアカウンセラー・ライター
国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士
大学卒業後、人材業界で10年以上にわたりキャリア支援に従事。若手からミドル世代まで、多くの人の転職・キャリア相談に携わる。現在はフリーランスとして、企業の人材育成支援やキャリア講座の講師として活動するほか、働く人の悩みに寄り添うライターとしても活動中。得意テーマは「転職・キャリアチェンジ」「中間管理職の悩み」「女性の再就職・副業」。
役職定年とは?年齢や制度の目的を知っておこう

まずは、役職定年という制度の基本的な仕組みや目的について、詳しく見ていきましょう。
役職定年の定義とは
役職定年とは、多くの企業が一定の年齢に達した社員に対し、管理職などの役職から外れるよう定めた制度です。一般的には55歳前後(企業によっては58〜60歳)を目安としており、役職定年後も定年退職までは勤務が継続されるケースが大半です。
あくまで役職を離れるだけであり、退職そのものを意味するわけではありません。この制度は、社員のキャリアにおけるひとつの節目とされており、組織の新陳代謝や若手登用を促すことを主な目的としています。
制度の目的と企業側の意図
企業が役職定年制度を導入する背景には、いくつかの目的があります。
若手登用の促進

役職定年制度を導入することで、上位ポジションに空きが生まれ、若手社員に対して昇進や責任ある業務を任せるチャンスが生まれます。これにより、若手のモチベーション向上や人材育成が加速されるだけでなく、組織内に新しい視点や発想が取り入れられ、イノベーションの土壌が育ちます。
また、年功序列の硬直化を避け、成果や能力に応じた評価文化を醸成する助けにもなります。
組織の活性化
年齢を重ねることでどうしても現場感覚や最新の業務知識が鈍る可能性があります。そうした背景をふまえ、適材適所の人員配置を促す役職定年制度は、組織内の流動性や柔軟性を高める効果があります。
またポジションの見直しにより、それぞれの社員が自分の能力を最大限に発揮できる配置を実現しやすくなり、組織全体のパフォーマンス向上につながります。結果として、マンネリ化を防ぎ、常に成長を続ける風土が生まれるのです。
人件費の適正化

管理職は企業にとって人件費負担の大きいポジションです。そこで役職定年を設けることで、一定年齢以上の社員に対して管理職手当や役職加算の支給を見直すことができ、コスト構造を健全化する手段となります。 その分を若手人材の育成や採用コストに充てることが可能になり、企業全体としての人材投資のバランスが最適化されます。過度な高年齢管理職の維持を避け、財務的な持続可能性を保つためにも、重要な施策です。
人材の流動性を高める施策の一環
役職定年制度は、組織内における人材の停滞を防ぎ、新陳代謝を促進する役割を担っています。 ある役職に長期間同じ人物が就いていると、ポジションが固定化し、若手や中堅のキャリアの通路が塞がれてしまうことがあります。そこで定期的に役職を見直すことで、キャリアパスに多様性が生まれ、社員一人ひとりが自らの成長戦略を描きやすくなります。加えて、異動や配置転換を通じてスキルの再獲得や視野の拡張が促進され、組織全体の人材力が底上げされます。
ただ、会社側からすれば合理的な制度でも、当事者にとっては「自分の価値を否定されたようだ」と感じるケースも少なくないのが現状です。
なぜ『役職定年=みじめ』と感じる人が多いのか
役職定年を「みじめ」と感じるのは、制度の背景だけではなく、実際に起こる変化に理由があります。
ここでは、そう感じやすい代表的な要因を見ていきましょう。
権限や立場が変わり、仕事のやりがいを失いやすい
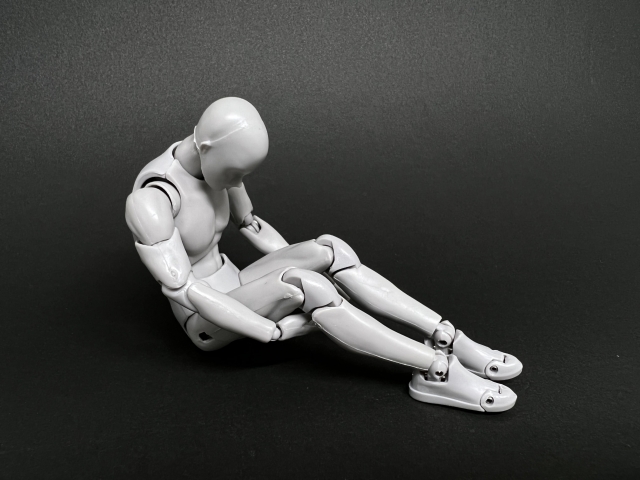
役職を外れることで決裁権や指示権限がなくなり、組織内での影響力も薄れます。その結果、自身の存在価値に疑問を感じたり、疎外感を覚える人も少なくありません。また、役職が外れることで、社内での立場や役割が不明確になり、仕事へのモチベーションが低下することもあります。
収入の減少が大きな負担に

役職定年後は役職手当や管理職給与が減額されるため、月々の手取り収入が大きく下がるケースもあります。家のローンや教育費などの支出が続く家庭では、大きな不安要素となります。 また収入の減少は、生活水準の見直しや将来のライフプランの再考を迫られる要因となります。
周囲の目や社内の扱いの変化
役職者として長く働いていた人ほど、役職を外れることによる“周りからの見られ方の変化”に戸惑うようです。また、後輩や部下だった人が上司になるといった構図も精神的なストレスとなります。そして役職が外れたことで、周囲からの期待や信頼が薄れたと感じる人も少なくなく、職場での居心地が悪くなることもあります。
実際の声に学ぶ:役職定年後のリアルな体験談

ここからは、実際に役職定年を経験した方々の体験談をご紹介します。リアルな声を通じて、制度の実態や心の動きがより具体的に見えてくるはずです。
事例①:大手メーカー勤務・Mさん(56歳)
役職定年を迎え、現場の業務に戻ることになったMさん。最初は戸惑いや屈辱感もあったようですが、現場スタッフとの協力や自分の経験を活かすことで“第二の働きがい”を見つけられたのだそうです。 Mさんは、役職定年後の新たな役割に戸惑いながらも、自身の経験や知識を活かして、若手社員の育成や業務改善に貢献しています。そして、「役職がなくても、自分の価値を見出すことはできる」と語り、前向きな姿勢で仕事に取り組んでいます。
事例②:商社勤務・Yさん(58歳)
役職定年後の給与ダウンを機にライフスタイルを見直し、家計の見直しや副業にも挑戦したYさん。「お金よりも、どう過ごすかを考えるきっかけになった」とのことです。またYさんは副業を通じて新たなスキルを習得し、自身のキャリアの幅を広げています。そして「副業が本業のモチベーションにもつながっている」と話し、役職定年後の生活に充実感を感じています。
役職定年をキャリアの節目ととらえる視点

ネガティブに捉えられがちな役職定年ですが、見方を変えれば新たな可能性を広げる転機にもなります。前向きに受け止めるためのヒントを見ていきましょう。
“みじめ”ではなく“一区切り”と考える
役職定年は、終わりではなく新しい働き方や価値観のスタートと捉えることもできます。会社の枠を超えたスキル活用や学び直し、地域貢献など、新たな可能性を探るタイミングとも言えるでしょう。役職定年後は、これまでの役職にとらわれず、自分の強みや経験を活かして、新たな役割を見つけることが重要です。
50代後半からのキャリアデザイン
人生100年時代において、50代はまだまだ“現役”。役職にとらわれず、自分の経験や強みを活かして活躍できる場は多く存在します。キャリアの再定義には、自分自身の強みや興味を再確認し、それに基づいたスキルの習得や人脈の構築が必要です。
役職定年後の働き方や選択肢とは?

役職を退いたあとのキャリアには、さまざまな道があります。ここでは、代表的な選択肢を順に見ていきましょう。
そのまま現職で勤務を継続する
業務内容や職場環境によっては、役職定年後もやりがいを持って働き続けられる人も多くいます。役職定年後は、これまでの経験を活かして、後進の育成や業務改善に貢献することが求められます。
転職・再就職を考える
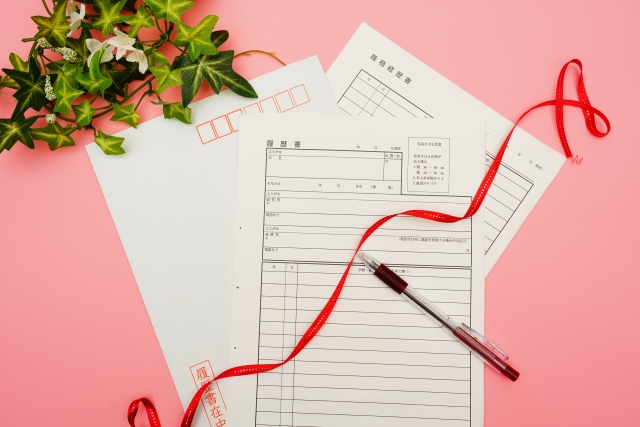
新しい環境を求めて、転職や再雇用制度の活用を視野に入れる方もいます。経験やマネジメント力を必要とする企業も多く、意外と選択肢は広いです。再就職支援サービスの活用や、同業他社への転職なども現実的な選択肢です。
副業・兼業にチャレンジする

役職定年によって収入が減ることに不安を感じている方は、副業や兼業を視野に入れてみるのも有効な選択肢です。近年は副業解禁の動きも進み、かつてよりも自由度の高い働き方が可能となっています。
副業のメリットは、金銭的な補填だけではありません。新たなスキルや人脈を得たり、自分の強みを再認識するきっかけにもなり、「自分にはまだできることがある」と前向きな感情を持つことができるようになります。
役職定年に向けて準備しておきたいこと
役職定年を前向きに迎えるためには、心構えだけでなく具体的な準備が欠かせません。ここでは、今からできる実践的な対策を紹介します。
①経済的なシミュレーション

まず必要なのは、お金の準備です。役職手当のカットによる収入減がどれくらいかを試算し、現時点での家計にどんな影響を与えるかをシミュレーションしましょう。
具体的には、次のような対策が考えられます。
- 家計簿アプリなどで支出を可視化
- ローン返済や保険の見直し
- 子どもの進学・独立までの費用計画
- 老後資金の目標と準備ペースの再設定
準備さえしておけば、たとえ収入が減ったとしても慌てることなく生活を維持でき、精神的にも安定しやすくなります。
②心の準備と情報収集
経済面だけでなく、心理的な備えも重要です。役職を退くことでプライドや承認欲求が揺らぐことは多くの人に起こります。
だからこそ、役職定年後の自分を思い描いてみてください。「どんな生活を送りたいか?」「何に価値を感じたいか?」という内省が、今後の行動指針になります。
加えて、制度や再雇用、副業の選択肢など、情報を集めておくことで不安を減らすことができます。企業の人事制度や社労士への相談、厚労省の資料、セミナー参加など、情報に触れる機会を持ちましょう。
③キャリアや働き方の棚卸し

これまでの仕事で得たスキルや人脈、自分が好きだった業務内容などを振り返り、紙に書き出しておきましょう。これを行うことで、今後の働き方の可能性が見えてきます。
たとえば、以下のような項目を整理します。
- 自分が得意だった業務・成果を出したプロジェクト
- 後輩から頼られてきた場面や内容
- 苦にならずに続けられた仕事
- 社内外でのネットワーク、信頼関係
このように可視化することで、「まだ活かせる強みがある」という気づきが生まれ、新たな道を選ぶ際の軸となるのです。
まとめ:役職定年は“みじめ”ではなく、“再構築”のチャンス

役職定年は、誰にとっても避けられない通過点の一つです。しかし、それを“みじめ”と感じるか、“再スタートの機会”とするかは、あなたの準備と捉え方次第です。
確かに、権限や給与の減少、周囲からの見られ方の変化といった痛みはあるかもしれません。けれど、それらは一時的な感情であり、自分の価値が下がったわけではありません。むしろ、それまで培ってきた経験が再評価される機会にもなります。
むしろ役職定年は、「自分が何を大切にし、どう生きていきたいか」を考えるタイミングです。働き方の自由度が増している今だからこそ、経験や人脈を活かして、柔軟なキャリアを描くことができます。
未来に不安を感じるのは当然のことです。ですが、不安と向き合い、少しずつ準備を重ねていけば、必ず“自分らしいセカンドキャリア”を築くことができるでしょう。
当サイト「悩ミカタ」ではミドル世代(40代50代)の悩みや不安・ストレスについて各分野の専門家/カウンセラーに相談できるオンラインカウンセリングサービス「悩ミカタ相談室」を展開しています。不安な気持ち、1人で抱え込まずにまずはお気軽に相談してみませんか?