「仕事、辞めたいなぁ。」
誰しも一度はそう感じたことがあるのではないでしょうか。特に、30代までは勢いで頑張ってきたものの、40代に入ってから仕事への意欲が低下し、疲れを感じるようになったという方もいるかもしれません。
精神科医ユングは人生を太陽の運行になぞらえ、40歳を「人生の正午」と表現しました。これは単なる折り返し地点という意味ではなく、環境の変化や体力の衰えにより、これまでの価値観や生き方を見直す時期に差し掛かることを示しています。そのため、「自分らしさ」が曖昧になり、迷いが生じやすいのです。
心理学では、40歳頃に生じるアイデンティティの揺らぎを「中年の危機(ミッドライフクライシス)」と呼びます。仕事を辞めたいという気持ちも、この「中年の危機」の一環として起こり得る現象と言えるでしょう。
関連記事はこちら➡ミッドライフクライシスとは?心理士が中年の危機の乗り越え方を解説【チェックリスト有】
もちろん、仕事を辞めるという選択が主体的なものであれば、それ自体は決して悪いことではありません。しかし、辞める前に考えておくべきことや、試してみるべきこともたくさんあります。
今回は、40代で仕事に疲れ、辞めたいと感じている方へ向けて、退職を決断する前にできること・やっておくべきこと をご紹介します。

臨床心理士・公認心理師・キャリアコンサルタント
臨床心理士あやさん
臨床心理士・公認心理師・キャリアコンサルタント。現在は心療内科クリニック(臨床歴10年以上)と従業員数1万名以上の大手企業にて従業員のカウンセリングに従事。
10代半ばの中学生から、成人期のキャリア相談、60代の老年期うつ・慢性期統合失調症のサポートに至るまで、老若男女様々なクライエントの支援にあたる。得意な技法は精神分析を参考にした心理療法。
2023年カウンセリングオフィス東京anoneを開業。
「東京anone」 https://tokyo-anone.com/
40代の離職率とは?

厚生労働省の統計によると、令和3年(2021年)の40代男性の離職率は40~44歳で6.0%、45~49歳で5.0%と示されています。また、令和5年(2023年)の40代男性の転職入職率は40~44歳で6.3%、45~49歳で5.3%でした。いずれも他の年代と比べると比較的低い割合の離職率・転職入職率です。
40代の離職・転職はなくはないけれども、少数にとどまっている印象です。一般的に40代は、30代までに培った専門性をもとに実務をこなしていく年代で、業務内容的にも社内の地位的にも成熟し安定する傾向にあるため、離職率は低い傾向にあるようです。
【参照元】
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/22-2/dl/kekka_gaiyo-03.pdf
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/24-2/dl/gaikyou.pdf
40代が仕事を辞めたくなる原因として多いもの
では、そんな40代が仕事を辞めたくなる原因やきっかけはなんでしょうか。
統計によると離職の主な原因として多い順に「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」、「職場の人間関係が好ましくなかった」、「給料等収入が少なかった」、「仕事の内容に興味を持てなかった」、「会社の将来が不安だった」と続いています。さらに40代特有の環境変化や心理を併せると次のようなことが言えるのではないかと思います。
①労働時間・賃金など労働条件が好ましくない

長時間労働や夜勤、休日出勤が当たり前のようなハードな職場では、疲労が慢性化し、仕事を辞めたいと感じることもあるでしょう。特に、40代に入ると体力の衰えを実感しやすくなり、女性の場合は更年期の影響で心身の不調が現れることもあります。 30代までのように、気力だけで乗り切るのが難しくなることも少なくありません。
また、年次に見合った昇給がない、あるいは給料が労働の対価に見合っていない場合も、不満を感じやすくなります。働く環境や待遇が改善されない限り、「このまま働き続ける意味があるのか?」と考える人が増えるのも無理はありません。
②職場の人間関係が好ましくない

これは年代に関係なく、離職の主な原因として常に挙げられるものの一つです。特に職場の対人関係に問題があると、仕事を続けること自体がストレスになり、辞めたくなることもあるでしょう。
批判的・攻撃的な上司や同僚がいる環境では、常にストレスにさらされ、逃げ場がない状況に陥りがちです。また、職場の風土が改善される見込みがない場合、社員の定着率は低くなりやすく、結果的に 「病んだ職場」ほど離職率が高まる傾向があります。
③専門性の変化・能力を発揮できない

社会人生活の中で、これまで経験のない仕事を急に任されることは少なくありません。突然の部署異動を命じられることもあれば、同じ職種であっても これまでのやり方が通用しなくなる業務に直面することもあるでしょう。
こうした専門性の変化は、これまで培ってきた実績や業務のやり方が急に通用しなくなることを意味します。その結果、戸惑いや混乱が生じ、不安を感じやすくなる のも無理はありません。さらに、新しい業務では実績がゼロの状態からのスタートとなるため、自信を失いやすい時期でもあります。
「急に仕事がうまくいかなくなった」と感じるこの状況では、いっそ辞めてしまいたいと思うこともあるでしょう。また、この変化は心理的に「過去の自分の喪失」につながるため、うつ症状を引き起こしやすい時期でもあります。こうした精神的な負担を軽減するためには、新しい環境に適応する時間を確保し、周囲のサポートを受けながら少しずつ慣れていくことが大切です。
④昇進・出向による責任の増大

昇進と聞くと喜ばしいことのように思われがちですが、心理的には「過去の自分の喪失」にあたり、実は大きなストレス要因のひとつとされています。新しい役割には、これまでとは異なる責任が伴うため、望んでいた昇進であれば、ストレスを推進力に変えて前向きに進むことも可能です。
しかし、もし昇進を望んでいなかった場合、「もう辞めたい、逃げたい」と感じることもあるでしょう。また、本来キャリアアップにつながるはずの長期海外出張や出向も、同じ理由で退職を考えるきっかけになりやすいものです。こうした環境の変化に直面した際は、自分の気持ちと向き合い、無理をしすぎないことが大切です。
⑤育児・介護などの家庭との両立

家庭環境の変化によって、退職を悩む方も少なくありません。
育児の場合、子どもの生活リズムに合わせた働き方が求められ、実際に社会復帰してみないと、仕事と両立できるかどうかわからないという不安を抱えることもあるでしょう。一般的には子どもが成長するほど働きやすくなると言われますが、小学校入学後に学童保育の不足や学校生活への適応問題が発生し、子育てを優先するために退職を考えるケースもあります。
介護の場合、社会的なサポートの有無や家族の協力体制によって、一人にかかる負担が大きく変わるものです。もし介護のキーパーソンとなり、十分な支援を得られない状況なら、仕事と介護の両立に疲弊し、退職を決断せざるを得ない こともあるでしょう。
家庭の事情による離職は、単なる選択ではなく、ライフステージの変化によって避けられない決断になることも多いのが現実です。
⑥キャリアアップ・独立・起業

40代になると自分の専門性が明確になる一方で、社内での成長の限界や、今後のキャリアの方向性が見えてくることがあります。スキルをさらに磨き、キャリアアップを目指したい場合、今の会社にいることが物足りなく感じたり、「このままでいいのか」と悩むこともあるでしょう。
これまで深く考えずにこなしていた業務についても、その意義や価値を意識するようになり、「自分にとって意味があるのか?」と疑問を抱くことが増えるかもしれません。考えすぎるあまり、「もう疲れた、辞めたい」と思う瞬間もあるでしょう。
40代はキャリアの転機になりやすい時期。仕事の意義を見出せなくなったときこそ、自分の本当にやりたいことや、新たな挑戦の可能性について向き合うチャンスかもしれません。
40代が仕事を辞めるべきかの見極め方
仕事を辞めたいと思っても、それが辞めていいタイミングなのかどうかの見極めは悩ましいものです。結論からいうとケースバイケースなのですが、一般的にすぐ辞めない方がいいときもあれば、むしろ具体的に離職に向けて取り組んだ方がよいときもあります。
そこでここからは「すぐに辞めないほうが望ましい」ケースと「退職に向けて準備を進めたほうが望ましい」ケースそれぞれについて、紹介していきます。
すぐに辞めないほうが望ましいケース
①すでに心身ともに疲労しており、何らかの症状がある

うつの兆候があるときは、大きな決断を避けることが重要です。
疲労困憊や睡眠・食欲の異常が続いていると、正常な判断力が低下し、勢いで決断すると後悔を招き、症状を悪化させる原因になりかねません。特に、次のような症状が 2週間以上続き、日常生活に支障をきたしている場合は要注意です。
【要注意症状】
✅ 身体面の変化
- 食欲不振、過食
- 体重の急な増減
- だるさや慢性的な疲労感
- 頭痛、耳鳴り、腹痛、便秘・下痢
✅ 精神面の変化
- 気分の落ち込みや急な涙
- 思考力・集中力の低下
- 無価値感や希死念慮(死にたい気持ち)
✅ 睡眠の問題
- 入眠困難、中途覚醒(夜中に目が覚める)
- 早朝覚醒(普段より早く目が覚めて再び眠れない)
このような状態が続く場合、まずはしっかり休養をとり、可能であれば心療内科を受診し専門医の意見を仰ぐことが大切です。
【職場復帰に向けた準備】
休養・治療によって症状が改善しても、「うまく仕事をこなせるか」という不安を抱えることも少なくありません。復帰をスムーズに進めるためには、リワークプログラム(職場復帰支援)やカウンセリングを活用 するとよいでしょう。
| リワーク | 出社を想定した活動を行い、社会復帰のリハビリを進める。休職者同士の体験共有や、再休職の予防策を考える機会もある。 |
| カウンセリング | 休職・復職について専門家と相談し、不安の整理や対策を考える。 |
②部署内・社内制度でまだ工夫を試みていないとき

仕事を辞めたいと思うのには、必ず何かしらの理由があるはずです。しかし、その悩みを誰にも相談せず、ひとりで抱え込んでいませんか?
もし今の職場環境に悩んでいるなら、その問題をオフィシャルにすることで、部署内の調整や社内制度の適用によって状況が改善される可能性があります。
例えば、育児や介護と仕事の両立に悩んでいる場合や、通院が必要な場合も、一人で抱え込まず、まずは上司や先輩に具体的な状況を伝えてみることが大切です。プライベートな事情を話すのに抵抗を感じるかもしれませんが、不測の事態や急な通院が必要になった際には、周囲の協力が欠かせなくなることもあります。
早めに周りの理解を得て、少しでも働きやすい環境づくりを試みることで、仕事との両立もしやすくなるでしょう。
③自分のコミュニケーションのあり方や考え方を見直す前
たとえ環境を変えられなくても、物事に取り組む姿勢や対人関係のあり方を見直すことで、今よりもストレスを軽減できる可能性があります。また、物事の捉え方を変えることで、不安を必要以上に煽ったり、過度に責任を感じたりすることを防ぐこともできるでしょう。
もし心理的な側面に対する「傾向と対策」をまだ試していないのであれば、仕事を辞める前に、専門家のカウンセリングを受けるなどして対処法を探るのも一つの方法です。焦って決断するのではなく、まずは 自分の心の状態と向き合うことが大切かもしれません。
④労働者としての市場価値を調べていないとき

本格的な転職活動を始める前でも、まずはエージェントに登録し、今の年齢や条件でどのような求人があるのかを調べてみましょう。 現在の仕事と、転職先での給料・休日・福利厚生などを比較することで、より冷静に判断できます。
調べてみると、「意外と今の職場の方が条件が良い」と気づくこともあれば、「思ったより求人が少なく、転職は慎重に進めるべき」と考え直すこともあるかもしれません。
退職後に焦って転職活動を始めると、目先の求人に飛びついて後悔するリスクもあるため、在職中に市場調査をしておくことが重要です。 まずは現状を把握し、冷静に次のステップを検討しましょう。
退職に向けた準備を具体的に進めたほうが望ましいケース
①自分がやりたいことが現在の職場で叶えられないことが明確であるとき
ステップアップのための転職を考えているなら、まずは情報収集を進めましょう。
| 起業を目指す場合 | 資格取得・専門職への転向の場合 | |
| 家族の理解 | ・事前に家族の理解を得ることが不可欠。 ・軌道に乗るまでの生活費の確保を具体的に検討する。 | ・プライベートな事情も含め、家族と将来について話し合う。 |
| ビジネスプラン | ・起業家セミナーやコンサルティングを活用し、ビジネスプランをブラッシュアップする。 | ・必要な専門知識や技術、資格に関する情報収集を行う。 |
| 副業の活用 | ・現在の職場で副業が認められているなら、まずは週末起業でビジネスを試して、実際の運営を体験する。 | ・オンライン講座や専門学校、大学院への進学も検討し、一人前になるまでの「修行期間」を把握する。 |
| 将来のキャリアビジョン | ・起業が成功した場合のライフプラン(生活費や収入の安定性)をしっかり見据える。 | ・資格取得後、一人前として働けるまでの期間や、定年までに活かせるかどうか、10年・20年先のビジョンを考える。 |
②生活における仕事の優先順位を下げたいとき

育児や介護を理由に仕事を辞めたいと考えたときは、家計費をどうするかを家族と検討していきましょう。自宅があり生活費に困らないという場合は無理して働かなくてもよい場合もあります。
③十分休養をとりリハビリをしたけれども職場復帰が困難なとき
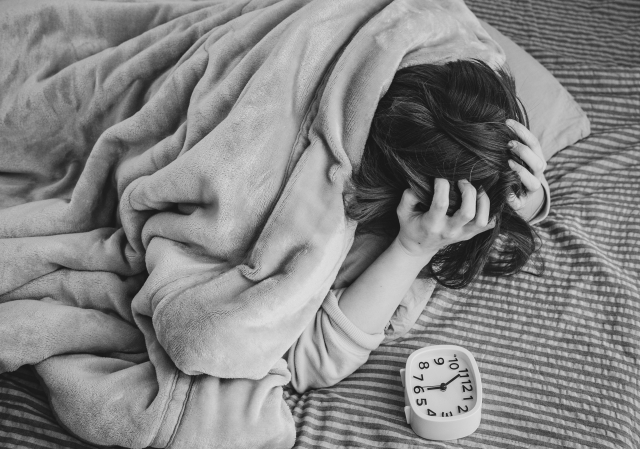
一定の期間をかけても心身の不調や生活リズムが整わない場合、回復にはさらに時間が必要になることがあります。もし所定の休職期間が満了するまでに十分に回復できなければ、復帰するか退職するかを選択しなければなりません。
しかし、フルタイムでの勤務に耐えられる体力が戻っていない場合、一般的には医師から「就業が難しい」と判断されることが多く、退職を検討せざるを得ないケースもあります。その際は焦らず、まずは失業手当を活用しながら、しっかりと心身を回復させ、準備が整った段階で転職活動を始めるのが望ましいでしょう。
回復のスピードには個人差があります。無理に急ごうとせず、「今は休むべき時期だ」と受け入れ、自分を責めずにしっかり休養することが何よりも大切です。
40代で仕事を辞めるリスクや注意点

40代で仕事を辞めるとなると、いつくかのリスクが伴います。リスクがあるから仕事を辞めない方がよいというわけでは決してなく、リスクを知った上で自己決定することが重要です。リスクを考慮に入れていると、もしうまくいかない状況に置かれても自分の納得が伴うため比較的精神的安定を保つことが可能だからです。
リスク1 年齢が理由で求人数が限られる可能性がある
まずは年齢が理由で次の職が見つかりにくい可能性を考慮にいれましょう。求人によっては30代までのみ募集をしている案件もあります。
また40代以降となると管理職を前提に即戦力を求めているものもあり、いままでのキャリアを活かしてステップアップするならばいいのですが、未経験の業界に飛びこみたいとなると年齢がハンデとなり新規の仕事が見つかりづらいかもしれません。
リスク2 待遇ダウンのリスク

求人を見つけたとしても、例えば今の職場よりも給料がかなり落ちたり、休日数が減ってしまう可能性も考えられます。
転職全般に言えることですが、人間関係や実際の業務の流れは実際に入ってみないとわからないことが多いものです。そのため、入職してみたら給料面も対人関係面も以前の職場より悪化してしまう可能性がある、ということは常に考えておかなければなりません。
リスク3 キャリアの一貫性が絶たれるリスク

転職をすると、これまでの実績が思うように活かせない場合があることを念頭に置きましょう。入職時に聞いていた仕事内容と、実際に求められる業務が異なることも珍しくありません。
また、異業種への転職では、それまで積み上げた経験がリセットされ、一から実績を作り直す必要が出てくるため、一時的に自信を失いやすい環境に置かれる可能性があります。たとえ前職の嫌な部分から解放されても、転職先が必ずしも理想的な環境とは限らず、新たなストレスやキャリアの停滞を招くリスクも考慮することが大切です。
転職を決断する際には、「本当に今の職場を離れるべきなのか」「転職先で自分のスキルやキャリアを活かせるか」を慎重に見極め、長期的な視点で判断することが重要です。
リスク4 やりたいことが期待通りに実現しないリスク
ステップアップのために転職あるいは起業したとしても、それがスムーズに実現できないかもしれません。
特に起業の場合、開業時の赤字を抱えながら事業を軌道に乗せなくてはなりませんし、生活のためのダブルワークも考慮するとサラリーマンよりもハードな生活を覚悟しなくてはならないかもしれません。
自由になるために起業したけれども、やってみたらかえって自由が少なかった…という可能性もあります。
仕事を辞める前に確認しておきたいこと
どうしても仕事を辞めたいという気持ちが強まった時、辞める前に次のことができないか、具体的に確認しておきましょう。
①辞めたい理由の原因を、社内制度や環境調整で改善できないかどうか確認する

「仕事を辞めるべきかの見極め方」でも触れましたが、誰にも相談せずに退職を決めることは、後々「逃げだったのでは…」と後悔するリスクがあるため注意が必要です。
例えば、業務量の多さや休みの取りづらさ、ハラスメントのような対応を受けている場合は、まずは部署内での環境調整や部署異動の可能性を相談してみましょう。
対人関係の問題が直属の上司にある場合は、さらに上の上司や人事に相談するのが有効です。定期的な人事考課があるなら、そのタイミングを活用するのも一つの手です。また、ハラスメントが疑われる場合は、発生した出来事や会話の記録をメモしておくことが重要です。
余談ですが、休養・休職後に復帰する際も、しっかりと環境調整の話し合いを行うことが大切です。勇気がいることかもしれませんが、働きやすい環境を整えるために、できる限りの対策を講じましょう。
【環境調整のための話し合いのコツ】
会社側に要望を出す際、自身ができないことややめてほしいことを中心に伝えてしまいがちですが、一方でご自身ができることも明確にして双方妥協点を探るようにすると話がまとまりやすいです。
例えば「現在の職場は長時間労働なので別の部署に異動を希望したいが、○○という職種については長年やっているため多少未経験でも適応できると思います。」などという言い方がよいでしょう。
1回で要望が通ることもあるかもしれませんが、会社は組織なので調整まで時間がかかることもあるかもしれません。その場合、定期的に要望を上司に伝え続けることも大切です。
②自身の物事の捉え方やコミュニケーションの工夫などで、事態の改善や悪化の予防ができないかどうか確認する
こちらも先のトピックで取り扱いましたが、変えることができない環境でもあなたの気持ちや考え方次第でいくらかしのぶことができるかもしれません。
ただしこれは心身ともに健康である状態で行ってください。そして無理して我慢しつづける必要もありません。よくある悩みと具体的な対応について、下にいくつか述べます。
対人関係の悩みをきっかけに生じている不安や悩みと向き合う方法

「高圧的な人がいる」「コミュニケーションがうまく噛み合わない人がいる」など、対人関係の悩みはいつでもどこでも絶えないものですが、そういった人に出会うたびに転職するわけにもいきませんよね。
自分と合わない人、嫌な人に出会った時は一般的にはまずは次のようなことを心がけて実践するとよいでしょう。
・周囲の人間関係よりも、自分の仕事に集中することをこころがける
・同じように感じている仲間を増やす
・やっている業務の論拠を説明できるように、あらかじめ言葉で準備しておく
・なるべく関わらないようにする
・コミュニケーションが噛み合わない人、指示がうまく伝わらない人は想像力が欠如していることが多いため、具体的な指示出しに徹する。この場合相手に多くを求めない気持ちを持つ
昇進・配置換えに伴う不安や悩みと向き合う方法
| 状況・背景 | 詳細 | 対策・考慮点 |
| 業務量・責任の増加に対する恐怖 | ・これまで経験してきたやり方が通用しなくなる ・昇進・部署異動などで新たな役割が求められる | ・上司や人事に相談して環境調整や役職据え置きの可能性を探る |
| 責任感が強すぎることによる自己追い込み | ・「すべて自分で背負わねばならない」「昇進したからミスは許されない」と過剰に責任を感じる ・固定観念にとらわれ、理想と現実のギャップに苦しむ | ・自分の考え方を見直し、必要以上に責任を感じないようにする ・専門家やカウンセリングを通じて自己理解を深める |
| 昇進や配置換えによる不安・「辞めたい」気持ち | ・新しい業務で実績ゼロの状態からスタートするため、自信を失いやすい ・環境変化が過去の自分の喪失に感じられる | ・継続的なカウンセリングで自信回復を図る ・自己分析と冷静な判断を重ね、焦らず納得のいく決断をする |
| 仕事を降りるという選択肢 | ・責任の大きな仕事を自ら引き受けるのが困難な場合、あえてその役割から身を引く可能性もある ・ただし、逃げと後悔しないように、自分のキャリアプランを見据えて判断する必要がある | ・自己納得の上で判断する ・事前に専門家や信頼できる上司、同僚に相談し、選択肢を検討する |
③辞める理由がポジティブな理由で説明できることを確認する
色々悩んでみて退職に至るということも一つの結論です。ただしその場合は必ずポジティブな理由で辞めるようにしましょう。
ネガティブな理由というのは、例えば「上司が嫌だからやめた」、「仕事が嫌だから辞めた」、「責任を負うことが嫌だから辞めた」といったものです。一方でポジティブな理由は「いまよりも労働環境の条件がよいところに行きたいから辞める(給与・休日含む)」、「○○の仕事がしたいから辞める」、「家庭に入りたいから辞める」、「働く必要がなく、のんびり暮らしたいからやめる」などが挙げられます。
前の職場から逃げを連想させるような理由づけは、失敗体験と自信喪失体験を作ることになるため避けましょう。
仕事を辞めた後の選択肢とは?
では実際に仕事を辞めたあとの選択肢にはどういったものがあるでしょうか。性別やそれまでの労働状況によって大きくことなるため、千差万別といってもよいでしょう。40代はあらゆる分岐の年代かもしれません。
①これまでのキャリアを活かして同業他社に転職する

これが心理的に健康を保った一番おすすめの方法です。転職は環境のリセットなので、多かれ少なかれ自己喪失と自信喪失が生じますが、それを少しでも軽減させるためにはこれまでの実績をなるべく活かすようにしましょう。
また社風の変化も考慮に入れて転職活動をしましょう。例えば長年大きな会社の変化の少ない部署に勤めていた場合、臨機応変さや変化への適応力を求められるベンチャー企業に転職すると戸惑いやすいかもしれません。
一方で、大きな企業でも混沌とした部門を取りまとめる役割を担っていた場合は、秩序を作ることに慣れているためある程度流動的な環境でも適応しやすいでしょう。
②未経験の業界にへ転職、または独立・起業する
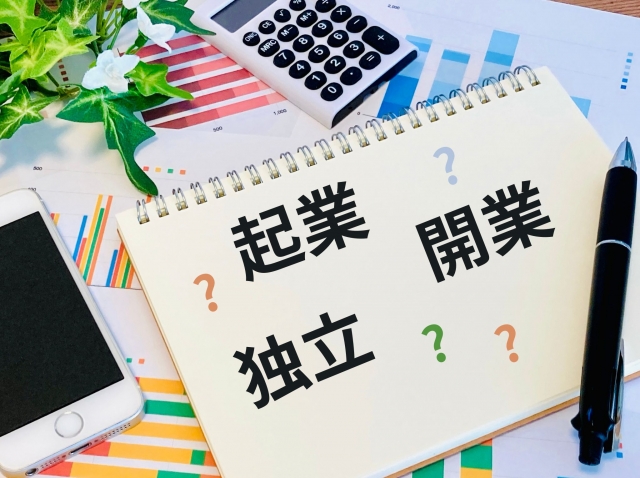
特に40代前半は、未経験の分野に挑戦できる最後のチャンスと感じる方もいるかもしれません。
もちろん、同居する家族との相談は欠かせませんが、一般的に「やって後悔するよりも、やらずに後悔するほうが心残りになる」と言われます。そのため、新たな挑戦を選択肢の一つとして考えるのもよいでしょう。さらに、自分で納得して始めたことは、たとえ結果的に諦めることになっても、気持ちの整理がつきやすいものです。
③専門学校・大学・大学院に入学しセカンドキャリアの形成をはかる

ある種の資格取得のために学校に入学する方もいます。時間的にも費用的にもコストが伴いますし、資格取得後すぐに独り立ちできる場合とそうでない場合もあるため、自己実現まで長い道のりかもしれません。しかし定年退職が関係ない資格の場合は、自分が引退を決めるまで働けるという利点もあります。
④家庭に入る

家族と過ごせる時間は、実は限られています。子どもや親に寄り添えるのは「今この瞬間」かもしれません。人生において何を優先するかは常に選択を迫られますが、ときには家族との時間を大切にする選択をしてもよいのではないでしょうか。
また、働き方を見直し、雇用形態を変えて仕事を続けることも可能です。これまでのキャリアを活かしながら、ライフスタイルに合った働き方を選ぶことで、無理なく仕事を続けることができます。たとえ短時間の労働でも、積み重ねた実務経験は将来のキャリアにも良い影響を与えるでしょう。
⑤いったん仕事から離れる

もし経済的に切迫していないのであれば、思い切って仕事を離れるという選択肢もあります。社会では「一生懸命働くことが正しい」と考えられがちですが、それが必ずしも個人の幸せにつながるとは限りません。会社は最終的にあなたの人生に責任を持ってくれるわけではないため、「いつまで、どう働くか」は常に自分自身で決める必要があります。
経済的な問題がなければ、無理に働く必要はありません。最近では、「FIRE(Financial Independence, Retire Early)」という経済的自立を達成し、早期退職するライフスタイルも注目されています。大切なのは、働いていないことに引け目を感じるのではなく、自分の価値観に基づいた生き方を選び、精神的な幸福を大切にすることです。
今の仕事を辞めずに乗り切るための方法
これまでの内容を踏まえ、「本当に辞めるべきか?」 を判断するための流れを整理しました。仕事の悩みを抱えながらも、できれば現在の環境で頑張りたいと考えている方は、以下のフローを参考にしてください。
問1: 仕事を辞めるかどうかを考え抜く体力と精神力はありますか?
ない場合は、まずは休養や治療をしましょう。症状が2週間以上続いているならば専門家や心療内科で相談しましょう。健全な思考は健全な体からです。ある場合は次の問いに進みましょう。
問2: 職場の環境面や対人関係に問題があり辞めたい場合、それを職場に相談して環境調整の検討を依頼しましたか?
職場環境を改善したい場合、まずは悩みをオフィシャルにすることが大切です。その際、具体的な証拠を準備しておくと、より効果的に交渉できます。
①証拠を準備する
交渉をスムーズに進めるため、以下のような記録を残しておきましょう。
✅ 出勤簿や勤怠記録(労働時間の証明)
✅ 職場での問題発言やハラスメントの記録(メモ・メール・録音など)
②相談前に「台本」を作る
話す内容を整理し、事前に 相談用の原稿を作成しておくと、落ち着いて交渉ができます。
●現状の問題点:「現在、業務量が多く、体調にも影響が出ています」
●これまでの工夫:「業務効率化のために◯◯を試しましたが、解決に至りません」
●会社に求める対応:「業務分担の見直しをお願いできないでしょうか?」
●自分ができること:「私も◯◯の範囲で努力を続けるつもりです」
③会社が対応しやすい形で提案する
相談の際は、感情的な不満ではなく、会社が動きやすい提案をセットにしましょう。
⚠ NG例:「仕事が多すぎてムリです。減らしてください」
⭕ OK例:「現在の業務量では品質の低下が懸念されます。業務分担の見直しをご検討いただけませんか?」
④相談は一度では終わらない
要望を一度伝えただけでは、すぐに状況が変わらないこともあります。そのため、定期的にフィードバックを続け、継続的に訴えましょう。
再度相談する際の例
- 「以前相談した件ですが、まだ改善の兆しが見えません」
- 「追加で◯◯の影響も出始めているので、再度検討をお願いしたいです」
問3: 変わらない環境に適応するために、あなた自身の考え方や物事の受け取り方、コミュニケーションの取り方を振り返りましたか?
もし、これまでに自分の心の状態をじっくり振り返ったことがなく、現在も心身ともに健康であるなら、一度カウンセリングを利用して自身の心理的な要因を検討してみるのも一つの方法です。
継続的なカウンセリングを受けることで、自分では気づかなかった思考のクセやストレスの要因を整理できる可能性があります。すでに心療内科を受診している方は、カウンセリングを併用することでより効果的なサポートを受けられため、特におすすめします。
カウンセリングの選び方

現在は、以下のように さまざまな形式のカウンセリングサービスが提供されています。
✅ 対面カウンセリング:直接対話しながら深く掘り下げられる
✅ リモートカウンセリング(オンライン・電話):移動不要で気軽に相談できる
また、カウンセラーごとに得意なテーマや専門分野が異なるため、自分の悩みに合ったカウンセラーを選ぶことが大切です。費用や時間、通いやすさも考慮しながら、無理のない形で利用してみるとよいでしょう。
▼ 当サイト「悩ミカタ」ではミドル世代(40代50代)の悩みや不安・ストレスについて各分野の専門家/カウンセラーに相談できるオンラインカウンセリングサービス「悩ミカタ相談室」を展開しています。不安な気持ち、1人で抱え込まずにまずはお気軽に相談してみませんか?
40代50代のお悩み” は専門家に相談しよう「悩ミカタ相談室」
仕事を辞めたい気持ちは自然なこと——あなたに合った選択を見つけよう

「仕事を辞めたい」と思うことは決して悪いことではなく、退職も人生を豊かにする選択肢のひとつです。一般的に40代の離職率はそれほど高くありませんが、生活環境や価値観は人それぞれ異なるため、一概に「辞めない方がいい」と決めつけることはできません。
一方で、 「すぐには辞められない」「できれば辞めたくない」という方もいらっしゃるでしょう。本記事では、困難な状況でも今の職場で頑張りたい方向けに、いくつかの対処法をご紹介しました。
ただし、状況は人によって異なるため、自分に合った方法を選ぶことが大切です。現在の状況を整理し、どうすべきかを見極めるために、専門家に相談するのも有効な手段です。

