「上司と部下の板挟みがつらい」「結果を出さなければならないプレッシャーが重い」「ストレスの原因や対処法を知りたい」「このストレスから解放されたい」——こうした悩みを抱えていませんか?
中間管理職になってから強いストレスを感じるようになったというケースは決して珍しくありません。実際、昇進によるストレスが原因で体調を崩す「昇進うつ」という言葉もあるほどです。
たとえ「昇進して嬉しい」「やりがいがある」と感じていても、上司と部下の間での調整役としての負担、増え続ける仕事量、重くのしかかる責任は、大きなストレス要因となります。
この記事では、中間管理職に求められる役割やスキルを整理し、なぜストレスが生じやすいのかを解説します。また、ストレスを軽減するための具体的な対処法についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
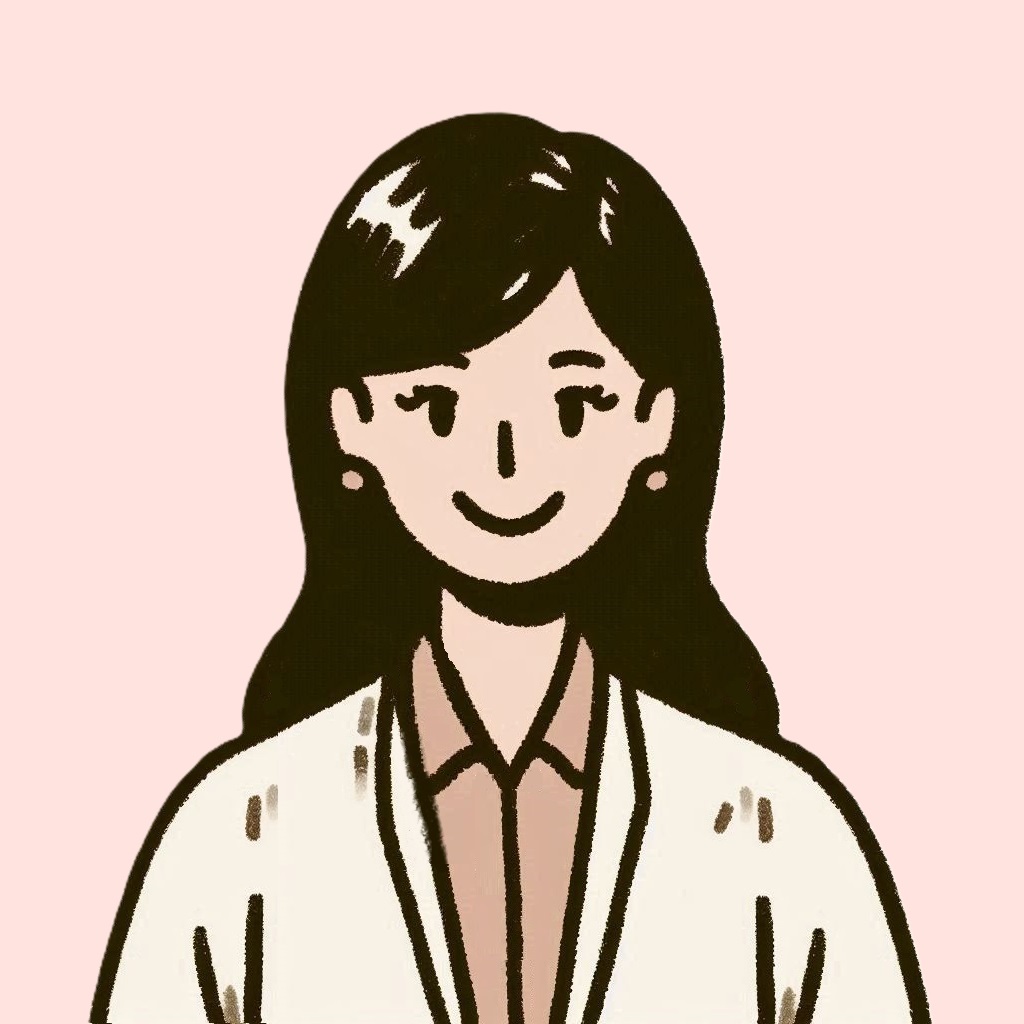
臨床心理士・公認心理師
あらいひさきさん
大学院修了後、「心穏やかに過ごせるように」という信念のもと企業にて研究員としてメンタルヘルスサービスの開発に携わる。認知行動療法を専門とし、精神科での心理相談にも従事する。うつや不安、職場でのメンタルヘルスや発達障害、不登校など幅広いケースのカウンセリングを担当。
中間管理職の役割や求められることとは
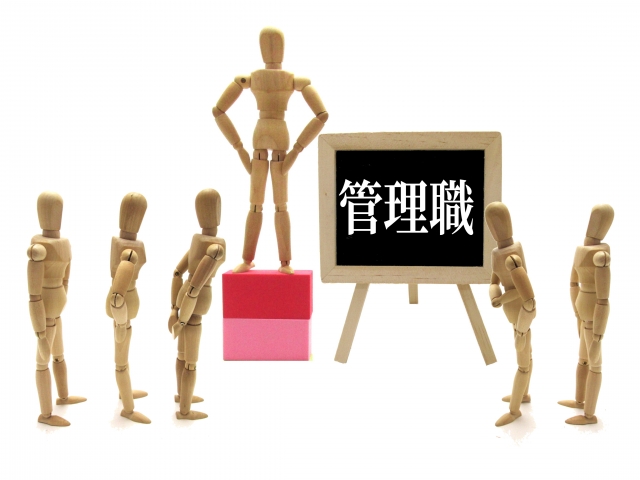
中間管理職の主な役割
中間管理職の役割を一言で言えば、組織内で上層部と下層部をつなぐ橋渡し役です。具体的には以下のような役割があります。
①部下のマネジメントと育成
部署の仕事を部下に割り振り、適切に業務が進むよう調整します。また部下の適性や能力を見極め、成長を促すことも求められます。
②経営層と現場の橋渡し
経営層の方針やビジョンを現場に共有し、また現場の肌身で感じられる課題や意見があれば経営層に伝え、改善策を考える必要があります。
③業務の管理と遂行
業務の進捗を把握し、必要に応じて部下の業務分担を調整したり、納期や品質をチェックしたりして円滑に業務が進むように管理を行います。
④業務の中で生じた問題の解決
業務の中で発生するさまざまな問題に対し、迅速かつ適切に対応することが求められます。原因を分析し、最適な解決策を導き出す力が必要です。また、同じ問題が再発しないように、仕組みの改善にも取り組むことが重要です。
⑤他部署との連携や調整
業務の内容によっては、組織全体の業務をスムーズに進めるために、他部署との連携を密にし、情報共有や調整を行うことも求められるでしょう。
中間管理職に求められる能力

上述したような役割を果たすために、以下のような能力が必要とされます。
①リーダーシップ
チームをまとめ、目標達成に向けて導く力が必要です。単に指示を出すのではなく、部下の意見を尊重しながら、方向性を示し、主体的に動ける環境を整えることが求められます。
②コミュニケーション能力
経営層・部下・他部署との意思疎通を円滑に行うためには、高いコミュニケーション力が不可欠です。単に情報を伝えるだけでなく、相手の立場を理解しながら適切な伝え方を工夫することが大切です。
③問題解決能力
業務上の課題を的確に把握し、効果的な解決策を考える力が求められます。発生した問題に対し、冷静に状況を分析し、長期的な視点を持って解決策を講じることが重要です。
中間管理職がストレスを抱えやすい要因

具体的に、中間管理職はどのようにしてストレスを抱えていくのでしょうか?
ここでは、主任に昇進してからストレスを感じるようになったAさんのケースをもとに、中間管理職特有のストレス要因をみていきましょう。
Aさんのケース
Aさんは、これまで営業職として積み重ねた成果が評価され、主任へと昇進しました。
しかし、新任主任としての最初の大きな課題は、部署の営業成績の改善でした。上層部からは厳しい改善要求が突きつけられ、毎月の報告会議では具体的な対策を求められる日々。
一方で、部下からは業務量の多さや進め方への不満が上がり、成果を求める上層部との板挟みに。部下のモチベーションを維持しつつ、適切な業務配分を模索する苦労が続きました。
さらに、新たに配属された新人の育成も任され、Aさんの負担はますます増大。その影響で自身の業務ミスが増え、顧客対応にも支障が出始めました。
他の部下も手一杯の状況を察し、Aさんに仕事を頼むのをためらうように。結果として、Aさんの残業や休日出勤は増えていきました。
かつてはフットサルや漫画を楽しむのが趣味でしたが、最近は意欲が湧かず、帰宅後はスマホで動画を見ながらお酒を飲み、そのまま寝落ちする日々。夜中に目が覚めることも増え、朝起きるのがつらくなってきました。
Aさんの例を見てみると、次のような要因があることが見えてきます。
①上司と部下との間で板挟みになってしまう
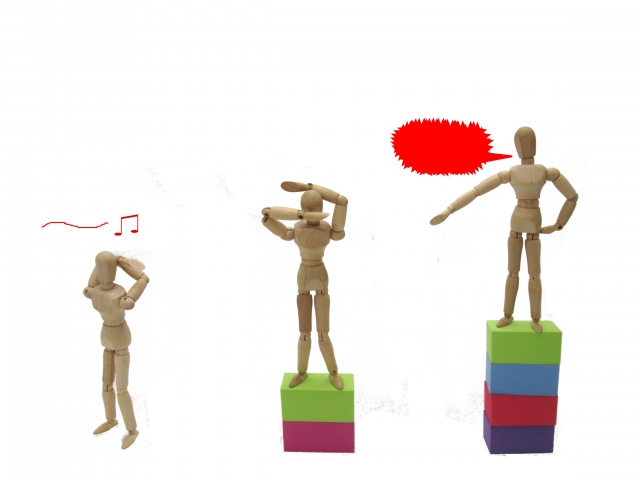
上層部からは厳しい指示やプレッシャーを受ける一方で、部下からは業務量の調整や不満を訴えられることが多く、両者の間で調整役を担うことが強いストレス要因になります。
②業務量が増える

これまでの自分の業務に加え、部下の管理・育成、会議や報告業務など、多岐にわたる業務をこなす必要があります。そのため、仕事が終わらず長時間労働になりがちです。
③責任が増える

自身の成果だけでなく、チームや部署全体の業績が評価の対象となるため、より大きな責任を背負うことになります。また、重要な意思決定を求められる場面も増え、精神的なプレッシャーが強まります。
④気軽に相談できない
これまでは同じ立場の同僚と気軽に愚痴をこぼせていたものの、管理職になると周囲の目を気にして「弱音を吐けない」と感じやすくなります。その結果、悩みを抱え込んでしまい、精神的に追い詰められることがあります。
このように、中間管理職は多くの責任を抱えながらも、孤独な立場になってしまい強いストレスを抱えてしまうことが少なくありません。
ストレスを軽減するためにできる対処法や相談先
それでは、中間管理職のプレッシャーやストレスにはどう対処すればいいのでしょうか?ここでは具体的な対処法を紹介します。
ストレス軽減のための対処法のポイント
①タスクを洗い出して優先順位をつける

業務内容が増えていくと、どこから手をつけてよいかわからなくなったり、時間配分がうまくいかず、重要な仕事が後回しになってしまうことがあります。そこで、まずは仕事の優先順位をつけることから始めましょう。
例えば、タスクを次の①~④の番号で分類し、タスクリストに番号を振っておくのがおすすめです。リストを自動で番号順に並べ替えられる設定にしておけば、リストの上から順にこなしていくだけで効率的に仕事に集中できますよ
1.緊急かつ重要
2.緊急だが重要度は低い
3.緊急ではないが、重要
4.緊急でも重要でもない
②自分をケアすることも「仕事」と考えてみる

中間管理職でストレスを抱えている人は、真面目な方が多く、仕事が忙しくなると自分のことを後回しにしてしまう人が少なくありません。しかし、心身の回復のためには自分を大切にする時間がとても大切です。
仕事よりも自分を優先することに抵抗がある方は、「仕事のパフォーマンスを維持するために必要な時間」と考えてみるとよいでしょう。
例えば、「早く帰宅してゆっくりお風呂に入る」といった行動も、「緊急かつ重要な仕事」と捉えてみてください。ストレス発散や楽しみの時間をスケジュールに組み込むことが、計画を継続するコツです。
③完璧を目指さない

「管理職だから、すべて完璧にこなさなければ…」と思っていませんか?
何でも100%を目指そうとすると、かえってストレスが増えてしまうことがあります。頑張りすぎてキャパオーバーになれば、結局どの仕事もうまく回らなくなってしまうかもしれません。「できる範囲でベストを尽くせばOK」と考えてみましょう。
すべてのタスクに同じ熱量を注ぐ必要はありません。優先度が低いものは後回しにすることも大切です。
また、「優先度が高いものでも、完成度80%で良しとする」という考え方を取り入れてみるのもおすすめです。「100%じゃないとダメ!」とこだわりすぎると、時間がいくらあっても足りません。ある程度形になったら次のタスクに移る柔軟さを意識しましょう。
④仕事を人に任せる

「自分でやったほうが早いから…」と、つい仕事を抱え込んでしまうことが続くと業務量が増え、ストレスも蓄積していきます。他の人に頼める仕事は積極的に 「任せる」 ことが大切です。
任せるときのポイント1:「チームの成長のために任せる」と考える
仕事を任せることは、部下の成長につながり、ひいてはチーム全体の成長にも貢献します。
任せるときのポイント2:細かく指示を出さず、大枠で任せる
最低限のポイントを伝えたら、相手のやり方を尊重するようにしましょう。
任せるときのポイント3:適度にフォローをする
細かい指示は出さない代わりに、 進捗を確認し、必要に応じてフォロー できる体制を整えておきましょう。
⑤人に相談したり愚痴を話すようにする

仕事の悩みや愚痴を誰かに話すだけで、気持ちがスッと軽くなります。職場の人であれば仕事に関する詳しい話ができ、仕事に無関係なプライベートな関係の人であれば、情報が外に伝わる心配やしがらみを気にせずに話すことができます。
「悩んでいるのは自分だけじゃない」「話を聞いてくれる人がいる」と感じることで、気持ちが少し前向きになります。
⑥休息をしっかりとる

「休むこと=悪」ではありません。むしろ、適切な休息は、仕事のパフォーマンス向上にもつながります。「休むことも仕事のうち」と考え、心身をしっかり回復させましょう。
休息をとるときのポイント1:質の高い睡眠をとる
休息の基本は睡眠です。少なくとも6時間以上、できれば7時間は睡眠時間を確保できるとよいですね。深い眠りを得るために寝る前のスマホをほどほどにしておくなど、寝室環境を整えることも大切です。
休息をとるときのポイント2:休みの日は仕事のことを考えないようにする
休日には仕事のことをできるだけ考えないようにし、完全にリフレッシュできる時間を確保しましょう。心身の回復には切り替えが重要です。メールをチェックしたり、仕事の調べ物をする場合は時間を決めて行うとよいでしょう。
利用できる相談先

「自分だけではどうにもならない」と感じたら、次のような専門家に相談するのも一つの方法です。
①産業医
社内に産業医がいる場合、気軽に相談してみるのも良いでしょう。また、信頼できる上司がいれば、業務の調整や相談をしてみるのも有効です。
しかし、会社の制度や方針によっては、うまく対応してもらえないこともあるかもしれません。その場合は次の項目のように外部の医療機関やカウンセリングを検討しましょう。
②医療機関やカウンセリング機関、オンラインカウンセリング
眠れない、食欲がない、集中できないなどのストレス症状が続いたり、自分一人で対処するのが難しいと感じた場合、無理をせず専門機関を頼ってください。
特に、睡眠障害や落ち込みなどのうつ症状が続く場合は、心療内科や精神科の医療機関を早めに受診することが大切です。
また、カウンセリングを受けることも有効です。話を聞いてもらうだけでも気持ちが整理され心が軽くなることがあります。
▼ 当サイト「悩ミカタ」ではミドル世代(40代50代)の悩みや不安・ストレスについて各分野の専門家/カウンセラーに相談できるオンラインカウンセリングサービス「悩ミカタ相談室」を展開しています。不安な気持ち、1人で抱え込まずにまずはお気軽に相談してみませんか?
40代50代のお悩み” は専門家に相談しよう「悩ミカタ相談室」
辞めたいと思ったとき、退職や転職などを判断するポイント
「このまま続けるのは無理かもしれない…」と感じたとき、辞めるべきかどうか迷うこともありますよね。そんなときにチェックしておきたいポイントを紹介します。
①体調に異変がないか?

まずは自分の体調をチェックしてみましょう。仕事のストレスは、体調に大きな影響を与えることがあります。例えば、以下のような症状が続いていませんか?
・夜眠れない、または途中で目が覚める
・食欲がない、または過食してしまう
・集中力が低下し、ミスが増える
・以前楽しんでいたことが楽しめなくなる
これらは、心と体が疲れているサインです。この状態では思考力や判断力が低下し、ネガティブな気持ちが強まりやすくなります。 そのため、大きな決断は避けたほうがよいとされています。体調が回復した際に、その決断を後悔してしまうことがあるためです。
まずはしっかり休養をとり、体調が回復してから判断するようにしましょう。休職ができると心と体をしっかり休めることができます。
休職が難しい場合は、一時的にでも負担を減らせる方法を考えてみましょう。例えば、
仕事量の調整、リモートワークの活用、信頼できる人に相談するなど、まずは自分を休めることを最優先に行動してください。
②職場が相談に応じてくれるか?

職場にストレスや悩みを相談し、業務量を調整してもらえたり、気にかけてもらえたりすると、もう少し頑張ろうと思えることもあります。
しかし、次のような状況が続く場合は、転職を視野に入れるのも選択肢の一つです。
・相談しても業務量が変わらない
・パワハラやモラハラの環境が改善されない
・上司が信頼できず、会社全体のサポート体制が弱い
「相談しても何も変わらない…」と感じる場合、会社があなたを大切にしていない可能性があります。このまま働き続けても、ストレスが積み重なっていくだけかもしれません。
③ 業務の内容は自分に合っているか?

仕事量を調整できたとしても、そもそも業務内容が自分に合っていない場合、ストレスが続くことがあります。例えば、「中間管理職のマネジメント業務が合わない」と感じるなら、無理に続けるのはつらいものです。
その場合は、役職を降りてプレイヤーに戻る、または別の業務をしている部署へ異動するのも方法の一つです。それが難しければ、転職を考えてもよいかもしれません。
「今の環境で本当に自分らしく働けるのか?」を、一度じっくり考えてみることが大切です。
まとめ
この記事では、中間管理職が抱えるストレスの原因とその対処法について解説しました。
①部下のマネジメントと育成
②経営層と現場の橋渡し
③業務の管理と遂行
④業務の中で生じた問題の解決
⑤他部署のと連携や調整
①リーダーシップ
②コミュニケーション能力
③問題解決能力
①上司と部下との間で板挟みになってしまう
②業務が増える
③責任が増える
④気軽に相談ができない
①タスクを洗い出して優先順位をつける
②自分をケアすることも「仕事」と考える
③完璧を目指さない
④仕事を人に任せる
⑤人に相談したり愚痴を話すようにする
⑥休息をしっかりとる
①産業医
②医療機関やカウンセリング機関
①体調に異変がないか?
②職場が相談に応じてくれるか?
③業務の内容は自分に合っているか?
もしも現在の環境が合わないと感じる場合は、転職を視野に入れるのも選択肢の一つです。無理をせず、自分に合った働き方を見つけていきましょう。

