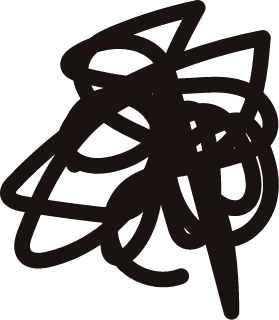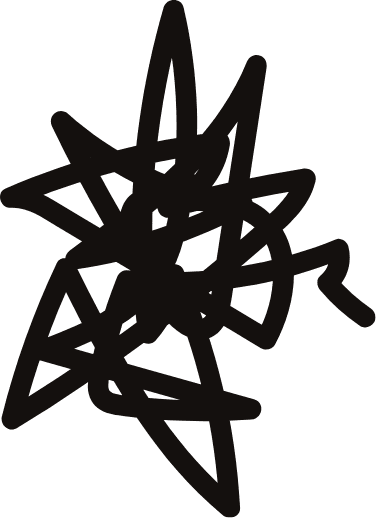前よりもいい条件・新しい環境を求めてやっと掴み取った新天地。一般的に転職はおめでたいことで、新しい環境への期待で気分も前向きになることが多いですが、新しい環境に立ち向かう時は誰しも心身の負担がつきものです。
ストレスという言葉は元々物理学の用語でしたが、ここではストレスを心身に負担をもたらす要因(=ストレッサー)やその反応(=ストレス反応)を含むものとして広く捉えてお伝えします。ストレス反応は例えば憂うつ・緊張・不安・疲労・焦りなどの精神身体両面の諸症状があります。
では、なぜ新しい環境にはストレスがつきものなのでしょうか。言葉で理由を考えると意外と説明が難しいものです。
そこで今回は、転職に伴うストレスのピークはいつ頃まで続くのか、なぜ転職後はストレスを感じやすいのか、ストレスや心身の不調を最小限に抑えるためにはどうしたらよいかをお話しします。

臨床心理士・公認心理師・キャリアコンサルタント
臨床心理士あやさん
臨床心理士・公認心理師・キャリアコンサルタント。現在は心療内科クリニック(臨床歴10年以上)と従業員数1万名以上の大手企業にて従業員のカウンセリングに従事。
10代半ばの中学生から、成人期のキャリア相談、60代の老年期うつ・慢性期統合失調症のサポートに至るまで、老若男女様々なクライエントの支援にあたる。得意な技法は精神分析を参考にした心理療法。
2023年カウンセリングオフィス東京anoneを開業。
「東京anone」 https://tokyo-anone.com/
転職後、ストレスがピークに達するのはいつ?しんどい時期はいつまで続く?

転職に伴う心身のストレス反応は、転職後の時間経過や状況によって質が変わってくると考えられますが、入社後半年を超えるあたりまではストレスを感じやすい時期と言えるでしょう。
以下、おおよその時間経過に伴うストレスの違いをみていきましょう。
入社後すぐ〜2ヶ月ごろ:初めての状況に自分を奮い立たせて立ち向かう時期
転職はこれまでの慣れ親しんだやり方や文化を捨てて新しい環境に飛び込むことでもあります。最初は気合を入れて、緊張感をもって取りくむと思いますが、それは必要以上に自分を奮い立たせている状態です。この時期のストレスは体が「新たな環境」というストレッサー (=ストレスを引き起こすもの)に晒され、そこに争うことで生じます。
転職直後に通勤だけでも疲れ、「たいした仕事はしていないはずなのに帰りはぐったりしている」と感じるのはこのせいです。あるいは、小さな例ですが、ボールペン一つ購入してもらうだけでも誰かに発注してよいかどうかお伺いをたてたり、手順を教えてもらわなくてはなりません。一つ一つのことは些細なことかもしれませんが、知らず知らずのうちにストレッサーになっていることがあります。
入社後3ヶ月〜6ヶ月ごろ:情報過多で疲れも多く出やすい時期
入社から1ヶ月経つと、「会社に慣れる」から「仕事に慣れる」に目標がシフトしていきます。
通勤や会社の雰囲気に少しずつ慣れてくる時期ですが、一方で実務上知らないことはまだまだ多いです。業務のインプットに苦労し、それがストレッサーになりやすい時期と言えるでしょう。一方で入社3ヶ月を超えてくると入社直後の力みが程よく抜けてくる分、溜まっていた疲れも実感しやすいかもしれません。
入社後6ヶ月すぎたころ:業務の難易度が上がりストレスを感じやすい時期
業務にも少しずつ慣れてきて、コツがつかめる業務も出てきます。一方で、少し応用的な仕事やイレギュラーな案件も任されやすくなり業務の難易度が上がりやすいかもしれません。上司や同僚などと連携をしながら進めなくてはならず、自分のペースで思い通りに進められない、予想以上の修正を求められる仕事も増えてきます。
この時期は、これまでやってきた6ヶ月のパターンが通用せず、またしても試行錯誤が求められるため心身のストレス反応をきたすこともあります。また入社前の想像と入社後に実際感じたことの間のギャップを実感しやすく、それがストレスになり悩む場合もあるかもしれません。
転職後に多いストレスの要因とは

そもそもどうして転職直後にストレスを感じやすいのでしょうか。転職し環境が変化すると、今までの経験や実績が通用しないことに多く出会います。たとえ前職と業務内容が似ていたとしても、人間関係・職場環境はもちろん、コミュニケーションの取り方の違い、オフィスの動線、新しい通勤経路など様々な面で違いがあることが考えられ、多かれ少なかれこれまでの自分自身を見失う体験をします。この体験を心理学的には自己喪失と言い、転職後のストレスを感じやすい要因の一つとなっていることも多いです。
また自己喪失の状態では、自分がやっていることに自信を持てなくなり、緊張・不安・自責などのストレス反応が生じやすくなります。ですから、例えば深刻でないミスでも必要以上に気にしてしまうこともあれば、相手からの評価がひとつひとつ気になり、ストレスを感じやすくなるといったことも起こります。
転職後のストレスを解消する方法

では転職後のストレスをできるだけ解消し、最小限に抑えるにはどういったことを心がければよいでしょうか。いくつかセルフケアの方法を紹介します。
方法① ストレスをゼロにすることを諦める
ストレスに打ち勝つにはどのような心持ちが望ましいと思いますか?一般的にいわれる「強メンタル」になるコツがあるのでしょうか?
結論からいうと、ストレスに立ち向かおうとすればするほど、ゼロにしようとすればするほど一般的にはストレス反応は大きくなり悪化します。なぜならばストレスは誰しもが多かれ少なかれ感じて当然なものだからです。ですので、ストレスをやっつけるのではなく、理解して冷静に付き合いましょう。
まずはご自身の心身の不調や違和感を見て見ぬふりせず、「あぁ、今ストレス感じているんだなぁ」と理解し、落ち着いて対処することがストレス反応を最小限に抑えるための大切な一歩になります。
方法② 3つのRの実践
ストレスのセルフケアとして「3つのR」の実践が推奨されています。セルフケアとは、自分の体調や心の状態をしっかりと把握し、ストレスとうまく付き合っていくために自分で予防や対処をすることです。そして3つのRとは、「Rest(休息)」「Recreation(遊び・余暇活動)」「Relaxation(リラクゼーション)」の3つです。
ちゃんと休みましょうですって?そんなこと、基本中の基本じゃないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、意外としっかり実践できていないことも多いのです。
「Rest(休息)」…心身を休ませることで、主に休息・休養・睡眠

休日は休めているはずと思いがちですが、例えば休みの前の日にダラダラ夜更かしや深酒をしてしまったり、あるいは休むつもりだったけど外出や予定を詰め込んでしまったり…といった経験は誰しもありますよね。元気なときはそれでも良いのですが、転職したばかりで疲れが溜まりやすい時期は控えめにしておきましょう。もし週2日休みがあるならば1日は体を休める時間を作るようにしましょう。
あるいは、育児や介護で一人の時間を作ることが難しいかたもいらっしゃるかもしれません。そういった時はベビーシッターやレスパイトサービスなどを積極的に活用して、自分だけの時間確保に努めましょう。
「Recreation(遊び・余暇活動)」…趣味や気晴らし

休みの日も仕事のことを考えてしまう方には、強制的に気分転換することをおすすめします。
趣味というと何か大そうなことをしなくてはいけないと思うかもしれませんが、元々あなたが好きなものを積極的に取り入れればよいのです。
「どうせやるならば仕事に活かせるもの、将来の役にたつことをしよう」といった損得勘定はプレッシャーと、できなかったときの罪悪感になるので、できるだけ捨てることが望ましいです。軽い運動で心身のバランスを整えることが理想的ですが、例えば漫画を読む・料理・食べ歩きなど、気分が変わるものであれば構いません。ギャンブルや飲酒など心身の健康被害のリスクのあるものは避けましょう。
「Relaxation(リラクゼーション)」…自分で自分を癒す

リラクゼーションとは、主体的に心身が元来もつ調整力に働きかけて心と体の緊張を緩めることです。具体例としては、好きな香りを楽しむ(アロマテラピー)、温かい飲み物を飲む、マッサージを受ける、ストレッチやヨガ、ペットと戯れるなど五感に働きかけるものも多いです。また自律神経に直接働きかける呼吸法といったアプローチがあります。
もし食べること・飲むことがお好きでしたら、ちょっといいチョコレートを食べたり、ゆっくりコーヒーを入れて味わってみても良いかもしれません。
方法③ 呼吸法

呼吸法は深呼吸を通して自分の感覚や気持ちに耳を傾けるリラクゼーションです。まずは気軽に1分間取り組んでみましょう。
【1分間呼吸法のやり方とコツ】
- なるべく静かで、一人になることができ、落ち着いて呼吸ができる場所を探す。
- 軽く目を閉じ、胸を大きく膨らませるようなイメージをしながら、鼻から空気を大きく吸って鼻から出すことを繰り返す。このとき呼吸に集中しましょう。体の隅々まで新しい酸素が行き渡るようなイメージをしてみましょう。
呼吸法は自律神経を整えます。自律神経は私たちの意思と関係なく24時間稼働していますが、本来であれば自分で調節することができません。しかし呼吸のみ自律神経に主体的に働きかけることが可能と言われています。自律神経系は興奮状態のときに賦活される交感神経と、緊張緩和状態をもたらす副交感神経があります。緊張していると優位になる交感神経を、呼吸法を通して緩和してみましょう。
方法④ 心の持ちようを変えてみる

人間関係を気にするよりも先に、仕事を覚えることに専念する
転職すると色々なことが気になることと思います。業務内容はもとより職場の人間関係は否が応でも毎日目にし、耳にしますから気になりますよね。周囲の目や人間関係を気にして疲れやすい方は、まずは目の前の業務を覚えることに集中することをお勧めします。業務という「職場の共通言語」を通じて周囲との仲を深めていきましょう。
過去の実績を再評価する
転職の前後で「環境」はリセットされてしまいましたが、あなたの「業績」「経験」はリセットされていません。転職したばかりの時期はできないことに目が向いてしまいやすく、自信が一時的に低下しやすいです。ですがそんな時こそ、それまで頑張ってきたことや乗り越えてきたことを今一度棚卸しをしてみましょう。プレッシャーを感じつつも乗り越えた仕事、嫌な上司や同僚がいつつも何とか仕事を頑張ってきた経験、未経験の仕事をやりきった経験など、どんなに些細なことでも構いませんので思い出しましょう。
知らないこととできないことは別物と理解する
新しい環境に置かれると何かとわからないことだらけですし、判断を誤ったり、一人で解決できないことも多々あるかもしれません。至らない点は印象に残りやすいので、退勤後にもやもやと引きずるかもしれません。しかしそれは本当にあなたができないことでしょうか。もしかしたら「よく知らなかった」ことではないでしょうか。知らないことはできなくても当然ですので自分を責めないように心がけましょう。
一方で、口頭で業務の説明を受けたとしても、それがスムーズにできるようになるには時間と経験が必要ですので、そちらも焦らないように心がけましょう。
体調不良など転職後に注意したほうがいいストレスのサインは?
ここでは注意した方がよいストレス反応についてお話しします。その前に、ストレスは実は必要不可欠なものでもあることにも触れておきましょう。
① 健康的なストレスと不健康なストレス

ストレスというとどこかネガティブなイメージを抱きやすいものですが、緊張感や張り合いがないと何事もダラけてしまいかねませんので、実は適度にあったほうが望ましいのです。ちょっとした張り合いやちょっとした見栄も物事の原動力になることもありますよね?それはそれで健康に作用するものです。
「適度」なストレスの程度や内容は人によって異なりますが、頑張ればこなせると思える質・量、自分の強みや実績が活かされる状況、納得して引き受ける仕事、などのようにストレスを抱えつつも自分で状況や心持ちをコントロールができる場合はストレスが前向きな原動力に変わりやすいでしょう。
しかしながら、心身ともにストレス反応が生じて日常生活に支障がでる場合、それは不健康なストレスである可能性も高いです。以下が心身のストレス反応の要注意サインです。
② 不健康なストレス反応の一例
【おもな身体症状】
食欲の問題(食欲不振、過食)、睡眠の問題(入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒)、倦怠感、疲労感、肌荒れ、便秘、下痢、胃痛、月経異常、性欲減退など
ポイント:長引く肩こりや頭痛、朝なかなか起きられない、休日でも疲れが取れない状態も症状の一つの可能性があり、黄色信号かもしれません。
【おもな精神症状】
憂うつ、不安、焦り、イライラ、涙もろくなる、罪悪感、思考力低下、集中困難、自分が価値のない人間だと思ってしまう、無気力など
ポイント:精神症状の出方はさまざまです。落ち込む一方で、気分が高まってイライラそわそわするといったように、鎮静と興奮が同時に起こることもあります。
【逸脱行動】
酒量が増える、タバコの量が増える、ギャンブル、散財など
ポイント:酒量が増えていなくても、ビールがワインなどアルコール度数の高いものに内容が変化している場合も要注意です。
これらが2週間以上持続して続く場合や、日常生活に支障をきたしている場合は緊急度が高めです。専門家に話を聞いてもらう、あるいは心療内科の受診を検討しましょう。
③ セルフケアをしても「もやもや」が消えない場合も要注意かも

おそらく多くの方はストレスを感じたら何かしらのセルフケアを試みるかと思いますが、それでも体調不良が改善されず、仕事関連のことをぐるぐる考え続けるということであれば、一人でプレッシャーやストレスを抱えきれなくなっているのかもしれません。また再転職が頭によぎる場合も同様です。
転職後のストレスがセルフケアで解消されないときは専門家に話してみましょう。一人で抱えきれなくなったストレスは、他者に話して整理することをおすすめします。
話す相手は利害関係が生じないカウンセラーなどの専門家が望ましいですが、まずは家族や友人など身近な人に話してみてもよいでしょう。この時、家族や友人に話す場合は解決を求めないように注意しましょう。また共感が得られない可能性も考慮にいれましょう。
専門家は、企業であれば会社の福利厚生でカウンセリング窓口や社内の健康管理センター、産業医面談を利用できるかもしれません。もし社内で話すことを避けたい場合は、民間のカウンセリングサービスの利用を検討してもよいでしょう。近年はオンラインでのカウンセリングサービスも充実しています。
なお身体・精神症状が2週間以上続き、日常生活に支障をきたしているようであれば心療内科の受診をおすすめします。
▼当サイト「悩ミカタ」では、ミドル世代(40代50代)の悩みや不安・ストレスについて各分野の専門家/カウンセラーに相談できるオンラインカウンセリングサービス「悩ミカタ相談室」を展開し、公認心理師など国家資格を保有する専門家が多く登録しています。つらくて不安な気持ち、1人で抱え込まずにまずはお気軽に相談してみませんか?
40代50代のお悩み” は専門家に相談しよう「悩ミカタ相談室」
まとめ

転職に伴うストレスは多かれ少なかれ自然と感じるものですが、その背景にはこれまでのあなたの文化や価値観が通用しない状況から生じる側面も大いにあると考えられます。まずは心身のセルフケアにつとめみて、それでも難しいようでしたらカウンセラーなどの専門家とともに一度状況整理をしてみてはいかがでしょうか。もしすでに心身の症状が持続しているならば心療内科の受診をおすすめします。