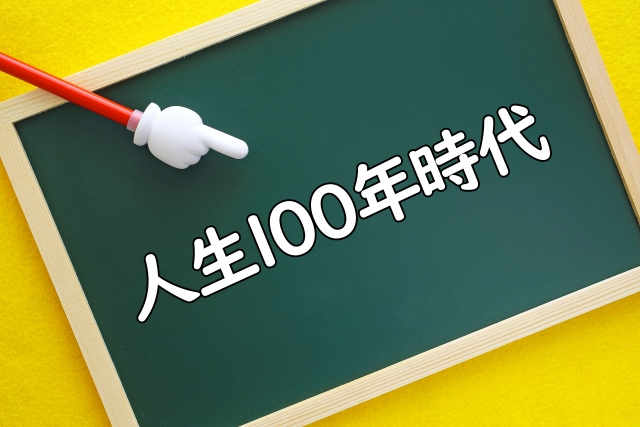私たちの人生観が大きく変わろうとしています。「人生100年時代」という言葉を耳にする機会が増え、多くの方が戸惑いや不安を感じているのではないでしょうか。平均寿命の延伸、テクノロジーの進歩などにより「教育→仕事→引退」という直線的なライフプランではない生き方が増えています。
そこでこの記事では、人生100年時代に向けてしておくとよいことや考えておきたい働き方など、漠然とした不安を具体的な行動に変える方法についてお伝えします。
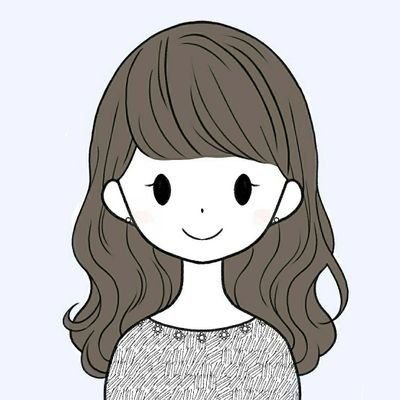
梅田ミズキさん
認定心理士、サービス介助士。大学で臨床心理学・産業組織心理学・発達心理学などを学び、卒業後は公的施設にて精神疾患の方のケアや介助業務、ご家族の相談対応などに従事しながら、ホームページ掲載用のコラムやミニ新聞を執筆。現在はフリーライターとして独立し、くらしにまつわるエッセイの執筆、臨床心理・発達支援・療育関連のコンテンツ制作および書籍編集に携わりながら、心理カウンセラーも務めている。趣味は読書、映画鑑賞、気まぐれで向かうプチ旅行。
人生100年時代とは何か
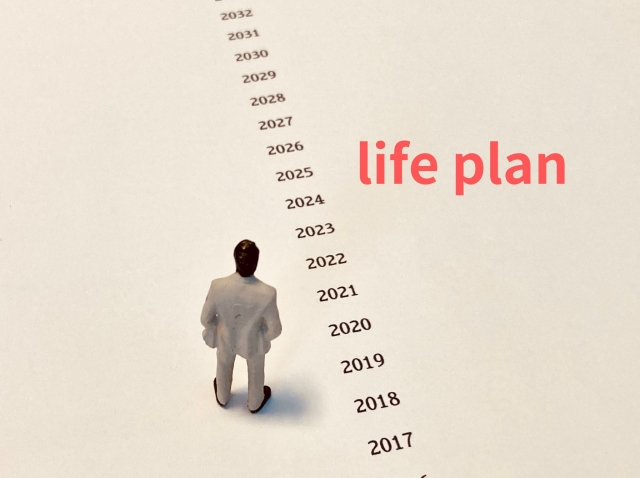
「そもそも『人生100年時代』ってどういうもの?」と疑問を持たれている方に向けて、この言葉が用いられるようになった背景や寿命が伸びている理由などについてみていきましょう。
日本人は寿命が長い
「人生100年時代」とは、平均寿命が延び、多くの方が100歳まで生きる時代を指します。イギリスのリンダ・グラットン教授が、100年生きうる時代をどう生き抜くかを描いた著書「LIFE SHIFT(ライフ・シフト)」で提唱しました。
厚生労働省の「簡易生命表(令和5年)」によると、2023(令和5)年の日本人の平均寿命は男性が81.09歳、女性が87.14歳です。これは、2022(令和4)年と比較して、男性が0.04年、女性が0.05年上回っています。
また「平均寿命の国際比較」を見てもわかるように、日本は諸外国と比較しても平均寿命が高いといえます。
出典:平均寿命の国際比較|厚生労働省
さらに、厚生労働省の「『人生100年時代』に向けて」によると、ある海外の研究では、2007年に日本で生まれた子供の半数が107歳より長く生きると推計されており、日本は健康寿命が世界一の長寿社会を迎えているようです。年齢に関係なく誰もが活躍でき、生きがいを持って暮らせる社会をつくることが、人生100年時代の大きな課題とされています。
「人生100年時代」は単なる長生きではない
人生100年時代の具体的な背景として、以下のようなものが挙げられます。
- 医療技術の進歩
- 栄養状態の改善
- 生活環境の向上 など
例えば、再生医療や遺伝子治療の発展、予防医学の進歩により、これまで治療が難しかった疾患への対応が可能になりつつあります。また、AIやロボット技術の発展により、高齢者の生活支援や医療ケアの質も大きく向上しているといえるでしょう。
単に長生きするだけでなく、健康で活躍できる期間が大幅に拡大することが、この時代の特徴です。従来の「人生80年」を前提とした生き方や働き方が常識ではなくなってきている一方で、個人の人生設計を根本から見直せるよい機会ともいえます。
人生100年時代で抱える課題
人生100年時代で直面するさまざまな課題は、単に年齢を重ねるのではなく「自分が納得できる人生をどのように送るか」に関わる大切なものです。具体的な課題と向き合い、解決策を考えていきましょう。
課題1. 経済的な不安と資金計画

100年生きることが前提の場合、大きな課題の一つが「経済面」です。退職金や年金だけでは、長い老後の生活をまかなうのが難しい方もいらっしゃるでしょう。現在の40代・50代の方々は、老後に最低でも30年分の生活費を準備する必要があります。
医療費や介護費用を考慮すると、若いうちからの計画的な資産形成が非常に大切です。
課題2. 新しいスキルを常に求められやすい
技術革新のスピードが速く、10年も経てば求められるスキルが大きく変化する時代です。そのため、常に学び、キャリアチェンジできる柔軟性が求められます。
例えば、ITやデジタル技術の急速な進歩から「求められるスキルが劇的に変化している」と感じている方も多いのではないでしょうか。社会で長く過ごしていくには、プログラミングやデータ分析、デジタルマーケティングなど、新しいスキルを継続的に学ぶ姿勢が求められやすくなるかもしれません。
課題3. 健康的な身体の維持

人生100年時代では、寿命が延びても身体的・精神的に健康でなければ、生活の充実や社会参加が難しくなります。一方で、社会にいる期間が長くなると仕事や人間関係などでどうしてもストレスがかかりやすく、健康を損ないやすくなるのも特徴です。
単に長生きするだけでなく、自分らしく活躍していつまでも豊かな人生を送るためには、健康が不可欠といえます。
人生100年時代の働き方や生き方とは?
テクノロジーの進化と社会構造の変化により、私たちの働き方や生き方は大きく変わろうとしています。人生100年時代を健やかに過ごすには、どのような働き方や生き方をすればよいのでしょうか。
さまざまな活動に挑戦できる
前述したとおり「教育→仕事→引退」の直線的なキャリアプランは通用しにくくなるかもしれません。言い換えると、複数の仕事を経験したり、起業したり、社会貢献活動に携わったりと、人生の各ステージでさまざまな活動に挑戦できる時代になります。
例えば、50代でフリーランスに転身してコンサルタントとして活躍した方や、60代で起業して新たなビジネスにチャレンジする人もいらっしゃいます。また、NPOや地域活動など、収入を目的としない社会貢献活動で生きがいを見出す人も多くなっているのが特徴です。
学習で活動の幅が広がる

キャリアと人生を安定させながら過ごすには、新しいスキルを常に学び続ける姿勢が大切です。近年では、オンライン教育や学び直しの機会が増え、年齢に関係なく学べる環境が整いつつあります。
「オンラインプラットフォームで新しいスキルを学んでみた」と話される方も少なくありません。また、大学が提供している社会人向けのリカレント教育プログラム(※①)を活用し、キャリアチェンジや自己実現に取り組んでいる方もいらっしゃいます。
※① 学校教育を終えた後も社会人として必要なタイミングで学び直し、スキルを磨いていくためのプログラム
多様な働き方を選択できる

フルタイム、パートタイム、フリーランス、起業など、働き方の選択肢が広がりやすいのも、人生100年時代と呼ばれる現代の特徴です。年齢や環境に応じて柔軟に働き方を変えられる社会への移行が進んでいます。
また、テレワークやギグエコノミー(※②)の拡大により、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方も一般的になりつつあります。クラウドソーシングなど、年齢に関係なく仕事を獲得できるプラットフォームを活用する方もいらっしゃるようです。
※② インターネットやアプリを活用して、企業に所属せず単発や短期の仕事を請け負う働き方
人生100年時代を生き抜くために必要なことや力とは?
常に変化する社会で自分の可能性を最大限に発揮するには、常識にとらわれない「新しい力」が求められます。人生100年時代を生き抜くために必要なことや力は何か、以下でみていきましょう。
学びの姿勢を忘れない
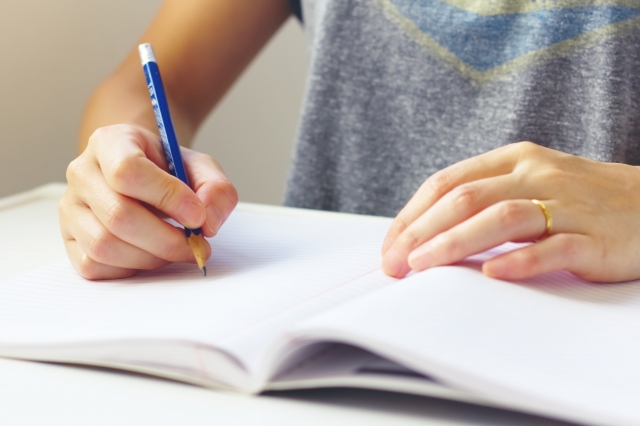
新しいことに興味を持ち、学びを楽しみながらさまざまなことに挑戦してみましょう。
例えば、最新のデジタル技術や趣味の分野で新しいスキルを身につけることで、自分の可能性を広げられます。パソコン教室やオンライン講座を活用したり、資格取得にチャレンジしたりすることで、自信と新しい可能性を見出せるかもしれません。
社会の変化に柔軟に対応できる力を身につける姿勢が、これからの時代を生き抜く鍵となります。学ぶことへの興味と好奇心を持ち続け、人生をより豊かにしていきましょう。
人とのつながりを大切にする

年齢を超えたつながりや多様な方たちとの関係性は、キャリアや生活の支えになります。多地域活動やボランティア、趣味のコミュニティなどに参加することで、新しい出会いや学びを見つけてみましょう。
例えば、地域の防災活動に参加したり趣味のサークルで交流したりすることで、貴重な人間関係を築いていくのも一つです。異なる世代や背景を持つ方たちとの交流は、自分の視野を広げ、新たな機会やアイデアを生み出すきっかけになります。
身体と心の健康へ投資する

健康的な食生活、運動、メンタルヘルスケアなど、若いうちから継続的に取り組むことが長寿社会を豊かに生きる秘訣です。
▼人生100年時代を健やかに過ごすために心がけたい生活習慣
・定期的な健康診断
・適度な運動
・バランスの取れた食事
・十分な睡眠
・ストレスマネジメント など
上記のように、総合的な健康管理が求められます。また、瞑想やマインドフルネス、趣味を通じたストレス解消など、心の健康への配慮も大切です。
人生100年時代に向けて今からできること
「人生100年時代がどういうものかは理解できたけど、ミドル世代はどう備えたらいい?」
ここまでお読みになり、そう感じている方も多いのではないでしょうか。ここでは、40代・50代の方々が人生100年時代に向けて今からできることを、具体例も交えながら挙げていきます。
「どのように老後を過ごしたいか」を書き出してみる

理想の老後をイメージして、具体的に紙に書き出してみましょう。旅行をしたい、趣味に没頭したい、地域活動に参加したい、孫と過ごす時間を楽しみたいなど、自分らしい老後の姿を想像できるでしょうか。
例えば、A4用紙に「60代・70代・80代・90代」とページを分け、各年代でやりたいことや目標を書き出します。60代は海外旅行、70代は地域のボランティア活動、80代は家庭菜園や趣味の教室、90代は家族との時間を大切にするなど、自分らしい具体的な計画を描くのが理想です。
もしかすると、立てた計画通りには進まないかもしれません。しかしこの作業を通じて、いきいきと充実した人生を送るための計画が明確になります。またお金、健康、スキル、人間関係など、さまざまな角度から理想の老後に向けて準備を始めやすいのもメリットです。
計画的な資産形成
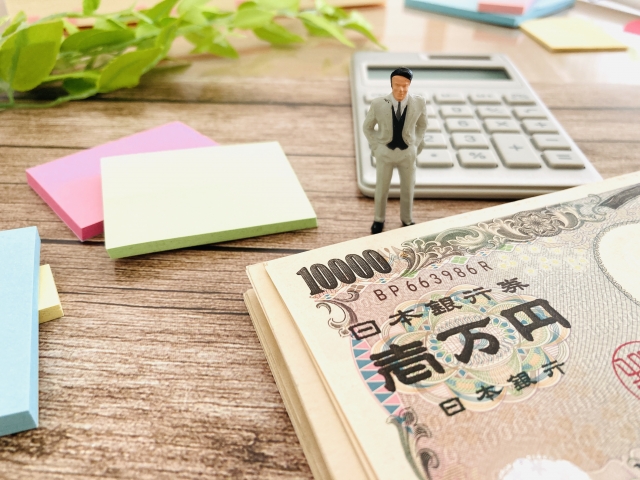
会社の退職金は以前と比べて減っているだけではなく、なかには退職金制度がない会社もあり、多くの方が理想的な老後の資金を準備できていないのが現状です。退職金がもらえたとしても、住宅ローンや突然の医療費で簡単に使ってしまう可能性があります。
このような状況を乗り越えるには、老後に向けての早めの資産準備が鍵です。投資信託やiDeCo、つみたてNISAなど、自分に合った方法で少しずつ資産を増やしていきましょう。
例えば、毎月の給料から一定額を貯蓄や投資に回すことから始められます。銀行の資産形成相談や、信頼できる金融アドバイザーに相談するのもよいでしょう。
また、複数の資産運用方法を組み合わせ、リスクを分散させることが大切です。ミドル世代の今から少しずつ計画的に資産を育てていくことで、人生100年時代への不安を減らせます。
スキルアップと学び直し
オンライン講座やセミナー、職場の研修などを活用し、自分のキャリアに役立つスキルを、いまのうちから学んでおくのもおすすめです。
もちろん、もう少し年を重ねた先でさらに新しい技術が求められる可能性はあります。しかし、パソコンやスマートフォンの操作、データ分析、語学、ビジネススキルなど、幅広い分野で学んでおけば、スムーズに対応しやすくなるのがメリットです。
さらに、経験を深めるために会社を変えたり、新しく興味を持った分野で副業を始めてみたりするのも選択肢の一つといえます。「将来、自分の体力やペースに合わせて無理なく働くためにはどのようにキャリアを形成していきたいか」を普段から考えておくとよいでしょう。
健康的なライフスタイルの確立
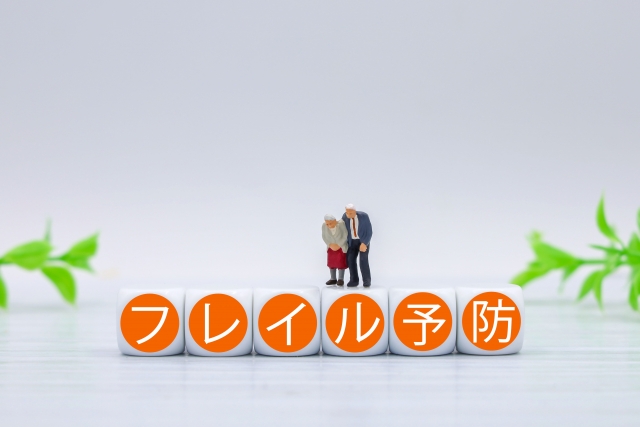
年齢に伴う身体機能の低下を最小限に抑えるには、適度な運動、バランスの取れた食事、ストレス管理が重要です。近年注目されている「フレイル予防」の観点から、40代・50代のうちから筋力トレーニングや栄養管理に取り組むことが推奨されています。
例えば、週に3回30分程度のウォーキングや軽い筋トレ、野菜を多く取り入れた食事、睡眠時間の確保などが挙げられます。趣味や社会活動を通じて心の健康も保ち、ストレスと上手に付き合うことで、より豊かな人生を目指していきましょう。
希望を持って挑戦できる未来へ

一つの仕事や場所に留まり続けるのではなく、さまざまな仕事や活動を行き来しながら人生を歩む人生100年時代。人間関係も変化が速く「つながりを持つのが難しい」と感じる機会が多いかもしれません。
だからこそ、自分の人生は自分で考えながら道を選んでいく必要があります。変化を恐れず柔軟に、そして前向きに、100年という長い旅路を希望あふれるものにしていきましょう。
▼ 当サイト「悩ミカタ」ではミドル世代(40代50代)の悩みや不安・ストレスについて各分野の専門家/カウンセラーに相談できるオンラインカウンセリングサービス「悩ミカタ相談室」を展開しています。不安な気持ち、1人で抱え込まずにまずはお気軽に相談してみませんか?