老後に対する不安は、誰もが持つものです。しかし、特に独身の場合は配偶者や子どもといった家族のサポートが期待できない分、経済的な自立と備えがより重要になります。
そこでこの記事では、独身の老後資金として必要な金額や準備の方法などを具体的に解説します。
「独身の自分はいくら貯めればいい?」「このままで将来は大丈夫?」と不安な方は、ぜひご覧ください。
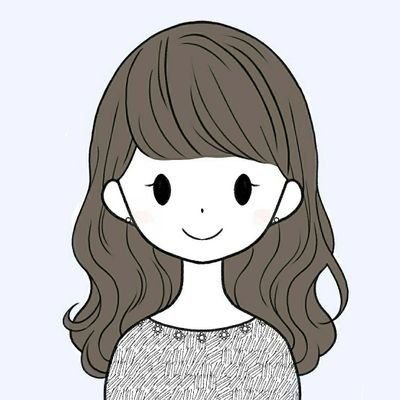
梅田ミズキさん
認定心理士、サービス介助士。大学で臨床心理学・産業組織心理学・発達心理学などを学び、卒業後は公的施設にて精神疾患の方のケアや介助業務、ご家族の相談対応などに従事しながら、ホームページ掲載用のコラムやミニ新聞を執筆。現在はフリーライターとして独立し、くらしにまつわるエッセイの執筆、臨床心理・発達支援・療育関連のコンテンツ制作および書籍編集に携わりながら、心理カウンセラーも務めている。趣味は読書、映画鑑賞、気まぐれで向かうプチ旅行。
老後とはいつからいつまで?独身者が意識すべき「期間」
健康状態や生活の質を長く保つために、まずは「老後」という期間の認識を明確にしてみましょう。
老後の定義とは?

「老後は〇歳から」の捉え方は人それぞれですが、一般的には定年退職後から人生の終わりまでの期間を指すことが多いでしょう。
かつては60歳定年が一般的でしたが、今では65歳まで働くことが当たり前になりつつあり、70歳以降も働き続ける「生涯現役」を目指す人も増えています。実際、厚生労働省の調査でも、65歳以上で働いている人は年々増加傾向にあります。
しかし、いくら働く意欲があっても、年齢とともに収入が減少するリスクは避けられません。特に体力や健康状態によって働ける時間や職種が限られる場合もあり、若い頃と同じように稼ぎ続けることは難しいのが現実です。
そのため、老後の経済的備えは「何歳まで働けるか」ではなく、「働けなくなったとき」や「収入が大幅に減る時期」から逆算して準備することが重要です。
独身の方は配偶者の収入や家族からの支援が期待しにくいため、特に60〜65歳頃からの収入減少をどう乗り切るかが、老後資金計画の大きなポイントとなります。
平均寿命と健康寿命
平均寿命(令和5年データ)…男性:81.09歳・女性:87.14歳
健康寿命(令和4年データ)…男性:72.57歳・女性:75.45歳
参照:健康寿命の令和4年度値について|厚生労働省
平均寿命と健康寿命の差は、男性で約8年、女性で約12年あります。この期間は、何らかの支援や介護が必要になる可能性が高い時期です。独身の場合、配偶者による介護の可能性がないため、この期間の経済的・身体的なサポートをどうするかが課題です。
そのため、
- 誰に介護を頼むのか(子ども、兄弟姉妹、行政、民間サービスなど)
- 介護サービスや施設利用にかかる費用をどう確保するか
- 住まいをどうするか(自宅での生活継続、施設入居など)
といった「おひとりさま期間の備え」が重要になります。
介護費用は公的保険があるとはいえ、自己負担も発生しますし、生活費も別途必要になってきます。
独身の老後資金はいくら必要?目安は2000万円?それとも5000万円?

「老後資金はいくらあれば足りるのか」は生活環境や健康状態で異なりますが「2,000万円あっても心配」との声も聞かれます。
よく聞く「老後資金2,000万円問題」とは?
令和元年に金融庁の審議会が発表した「市場ワーキング・グループ報告書」では、“夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦の場合、公的年金以外に2,000万円程度の蓄えが必要”とされました。
なお、この試算の前提は以下のとおりです。
- 毎月の赤字額:約5.5万円
- 老後期間:30年
- 5.5万円 × 12ヶ月 × 30年 ≒ 2,000万円
しかし、上記の試算はあくまで「夫婦世帯」を想定したもので、独身者にはそのまま当てはまりません。
実は足りない?独身者が5000万円必要と言われる理由
独身の場合、夫婦世帯よりも多くの老後資金が必要だといわれています。その主な理由は、以下のとおりです。
- 配偶者による介護の可能性がないため、介護サービスや施設利用に対する費用が必要
- 病気や怪我など「もしも」の際に支え合いができない
- 相続や遺族年金などの制度を活用できない
上記の要因から、独身者の場合は3,000万円から5,000万円程度の蓄えが必要だという試算もあります。
ただし、これは平均的な目安です。実際は、生活スタイルや健康状態、住居の状況などによって大きく異なります。
独身者の老後にかかる支出とは?項目別に解説
前述しているとおり、独身の場合、全ての費用を一人で賄う必要があります。そのため「どの項目にどれくらいのコストがかかるか」を把握しておけると安心です。
ここでは、老後資金を具体的にイメージできるよう、主な支出項目ごとの一例を挙げてみます。
生活費の一例

住居費
- 持ち家(ローン完済):管理費・修繕積立金で月3〜5万円
- 持ち家(ローン返済中):ローン返済額+管理費で月10〜20万円
- 賃貸:都市部で月6〜10万円、地方で月4〜7万円
食費
- 自炊中心:月3〜5万円
- 外食中心:月5〜8万円
光熱費
電気・ガス・水道:月2〜3万円
通信費
スマホ・インターネット:月1〜1.5万円
日用品・衣類
月1〜2万円
上記を合計すると、最低でも月12〜15万円程度の生活費が必要です。
医療・介護費用の一例

医療費
- 70歳未満:3割負担(上限あり)
- 70歳以上:1〜3割負担(所得により異なる)
健康状態にもよりますが、慢性疾患がある場合、月1〜3万円程度の医療費がかかる場合もあります。
介護費用
- 在宅介護:月1〜10万円(サービス利用度による)
- 施設入居:特別養護老人ホームで月10〜15万円、有料老人ホームで月20〜40万円
介護が必要な場合、年間で120〜480万円の費用がかかる可能性があります。
レジャー・交際費などの一例

充実した老後生活を送るために、趣味や交流のための費用も確保しておきたい方は多いのではないでしょうか。「生きがい」や「楽しみ」のための出費は、心身の健康維持にもつながる大切な投資であり、老後の生活をより豊かにしてくれる要素でもあります。
交際費
友人との食事や旅行:月1〜3万円
趣味・娯楽
習い事や趣味活動:月1〜5万円
旅行
- 国内旅行(年2回):年10〜20万円
- 海外旅行(年1回):年20〜40万円
上記を合計すると、年間で36〜96万円、30年で1,080〜2,880万円となります。
不測の事態に備える「予備費」の一例
「いざというとき頼れる家族がいないのは心配」と話される独身の方もいらっしゃいます。そのため、万が一に備える「予備費」の確保も大切です。
住居の修繕
持ち家の場合、大規模修繕に数百万円
緊急の医療費
高度医療や先進医療:数十万〜数百万円
急な引越し
住環境の変化に伴う費用:50〜100万円
上記の不測の事態に備えて、少なくとも300〜500万円程度の予備費の確保が望ましいでしょう。これは、いざという時に備える「安心のための資金」です。もちろん、全てを一度に準備する必要はありませんが、定年までの間に少しずつ積み立てていく意識が大切です。
「使わずに済めばラッキー」くらいの気持ちで、心の余裕を持つための備えとして意識しておくと良いでしょう。
独身者の老後の収入とは?もらえるお金をチェック
自分自身の収入源だけで老後生活を支えるために、支出に対してどれくらいの収入が見込めるのかも把握しておきましょう。
公的年金の平均受給額(厚生年金・国民年金別)
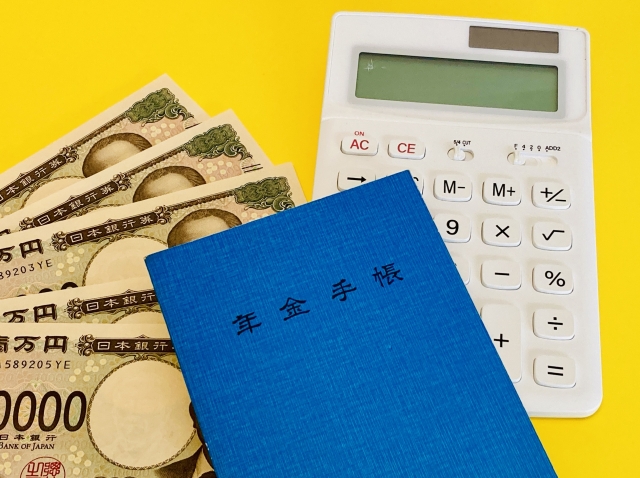
国民年金(基礎年金)のみの場合
- 満額で月約6.5万円(年間約78万円)
- ただし、納付期間が40年未満の場合は減額される
厚生年金(会社員)の場合
- 平均的な収入で40年間加入した場合、月約15〜18万円(年間約180〜216万円)
- 独身者の場合、遺族年金の加算はなし
上記の年金額は、あくまで平均的な数字です。実際の受給額は、加入期間や納付した保険料によって異なります。「ねんきんネット」で、自分の年金見込額を確認するのがおすすめです。
退職金や企業年金は期待できる?

退職金や企業年金の有無・金額も、勤務先の制度や勤続年数によって大きく異なります。
退職金
- 大企業(正社員):1,500〜2,500万円程度
- 中小企業(正社員):500〜1,500万円程度
なお、非正規雇用の場合は、退職金はほとんど期待できないケースが多いでしょう。
企業年金
- 確定給付企業年金:月数万円程度
- 確定拠出年金(401k):積立金額による
上記の金額も、あくまで一例です。退職金や企業年金が気になる方は、お勤め先の退職金規定や企業年金制度をチェックしておきましょう。
貯蓄・資産運用・不労所得
老後の経済的自立のためには、貯蓄や投資による収入を確保しておくことも重要です。現実問題として、公的年金だけでは生活費をまかなうのが難しいと言われており、年金にプラスして使えるお金をいかに作っておくかが、老後資金計画の大きなカギとなります。
預貯金

低金利環境ではあまり期待できない(年利0.001〜0.1%程度)
投資信託・株式
長期分散投資で年平均3〜5%程度のリターンが期待できる
不動産投資

物件によるものの、年利回り3〜6%程度
個人年金保険
加入内容によるものの、月数万円程度の給付が期待できる
【シミュレーション】独身の老後資金、実際いくら必要?

「どのような生活をしたいか」「どのような住まいで暮らすか」によって、老後に必要な金額は大きく変わります。たとえば、都心の賃貸住宅に住み続けるか、地方に住居を構えて持ち家で暮らすかでも、住居費や生活費に大きな差が生まれます。
具体的なケースを想定して、老後資金を試算してみましょう。
モデルケース①:年金+少額の貯蓄で暮らす場合
【前提の条件】
- 65歳退職、85歳まで生存
- 公的年金:月15万円
- 貯蓄:2,000万円
- 持ち家(ローン完済)
- 健康状態は比較的良好
【月々の収支】
- 収入:年金15万円+貯蓄取崩し5万円 = 20万円
- 支出:生活費15万円+趣味・交際費3万円+医療費2万円 = 20万円
【必要な老後資金】
- 貯蓄取崩し:5万円×12ヶ月×20年 = 1,200万円
- 予備費(緊急時対応):500万円 計1700万円
このケースでは、2,000万円の貯蓄があれば何とかやりくりできます。しかし、介護が必要な場合や住居の大規模修繕が必要な場合などに不安が残りやすいでしょう。
モデルケース②:年金+十分な資産運用をしている場合
【前提の条件】
- 65歳退職、85歳まで生存
- 公的年金:月15万円
- 貯蓄:5,000万円(うち3,000万円を運用)
- 資産運用:年利回り3%(年間90万円、月7.5万円)
- 持ち家(ローン完済)
【月々の収支】
- 収入:年金15万円+運用益7.5万円+貯蓄取崩し2.5万円 = 25万円
- 支出:生活費15万円+趣味・交際費5万円+医療費3万円+予備費2万円 = 25万円
【必要な老後資金】
- 運用資金:3,000万円(元本は維持)
- 貯蓄取崩し:2.5万円×12ヶ月×20年 = 600万円
- 予備費(緊急時対応):1,000万円 →合計4.600万円
資産運用による収入があるため、ゆとりある生活が可能なケースです。また、元本は維持されるため、相続や寄付などにも活用できます。
モデルケース③:家賃がかかるor介護施設を想定する場合
【前提の条件】
- 65歳退職、85歳まで生存
- 公的年金:月15万円
- 貯蓄:6,000万円
- 賃貸住宅(月7万円)または75歳から介護施設入居(月25万円)
【月々の収支(65歳〜74歳)】
- 収入:年金15万円+貯蓄取崩し10万円 = 25万円
- 支出:家賃7万円+生活費10万円+趣味・交際費5万円+医療費3万円 = 25万円
【月々の収支(75歳〜85歳)】
- 収入:年金15万円+貯蓄取崩し20万円 = 35万円
- 支出:施設費25万円+個人的な生活費5万円+医療費5万円 = 35万円
【必要な老後資金】
- 65〜74歳の貯蓄取崩し:10万円×12ヶ月×10年 = 1,200万円
- 75〜85歳の貯蓄取崩し:20万円×12ヶ月×10年 = 2,400万円
- 予備費(緊急時対応):400万円 →合計4.000万円
住宅費用や介護施設費用がかかるため、より多くの資金が必要となります。特に介護施設に入居する場合、月々の支出が大幅に増加するため、十分な貯蓄が必要です。
以上3つのモデルケースから、独身者の老後資金は最低でも2,000万円、ゆとりある生活や介護に備えるなら4,000〜5,000万円程度が目安になるといえるでしょう。
今からでも間に合う!40代・50代の独身者が老後資金を準備する方法
「理想の老後資金が分かっても、いまからでは準備が間に合わない…」
ここまでお読みになり、そう思っている方もいるかもしれません。しかし、40代・50代からでも効果的な準備は可能です。具体的なステップをみていきましょう。
STEP1:現在の支出と資産を「見える化」する
まずは、以下のような方法で現状把握から始めましょう。「なんとなく大丈夫」と思っている方も、数字にしてみると意外な気づきや見直しポイントが見えてくるはずです。
現状を正しく知ることが、将来への不安を解消する第一歩になります。
家計簿をつける

- 3か月程度、全ての支出を記録する
- スマホアプリやエクセルなどを活用
- 固定費と変動費を分けて分析
資産を棚卸しする
- 預貯金、投資商品、保険、不動産など資産をリストアップ
- 退職金の見込額も確認
- 年金見込額を「ねんきんネット」で確認
この段階で「毎月いくら貯められるか」「現在の資産はいくらか」「退職までにいくら貯められるか」が見えてきます。
STEP2:支出を見直す
支出と資産の現状を把握したところで、支出を見直して、貯蓄に回せる金額を増やします。「大きく稼ぐ」ことが難しくても、無駄を減らして手元に残す工夫は誰にでも始められる資産形成の第一歩です。
将来のために、“今の暮らし”を少しだけ見直す勇気を持つことが、老後の安心につながります。
固定費の見直し

- 必要に応じて住居の住み替えや借り換えを検討
- 保険の掛け金と保障内容のバランスを見直す
- 不要な通信サービスを解約
- サブスクは必要なものだけに絞る
生活習慣の見直し
- 外食を減らす
- 趣味や娯楽の費用を見直す
- 衝動買いを控える
多くの場合、固定費の見直しだけで月1〜3万円、変動費の見直しで月2〜5万円程度の節約が可能です。これだけでも、年間36〜96万円の貯蓄増加につながります。
STEP3:投資・資産運用を学び、積立を始める

貯蓄だけではなく資産運用も取り入れると、より効率的に老後資金を準備できます。とはいえ、「投資は怖い」「自分には難しそう」と感じる方も多いかもしれません。
しかし、長期・分散・積立という基本を守れば、初心者でもリスクを抑えながらコツコツ増やしていくことが可能です。
投資の基礎知識を身につける
- 書籍やセミナー、動画などで学ぶ
- 投資の目的とリスクを明確にする
- 分散投資の重要性を理解する
積立投資を始める
- つみたてNISA
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
- 通常の投資信託 など
40代から月5万円を年利3%で運用した場合、20年後には約1,600万円になります。50代からでも、月10万円を同条件で運用すれば、10年後に約1,400万円になります。
STEP4:年金以外の収入源を検討する
収入源を年金のみに依存していると、減少したり途絶えたりした場合に大きな影響を受けます。リスクを分散させる意味でも、複数の収入源を持っておくと安心です。特に独身の方は、生活や将来設計をすべて自分ひとりで支える必要があるため、年金以外の「自力で得られる収入源」をできるだけ多く持っておくことが、老後の不安を和らげる大きなポイントになります。
副業・複業の検討

- スキルや趣味を活かせる仕事を探す
- オンラインでできる仕事を検討
年金受給開始年齢の繰り下げ
- 70歳まで繰り下げると、月々の年金額が42%増加
- 健康状態や就労可能性を考慮して判断する
定年後の就労継続

- 同じ会社での再雇用
- 別の企業での就労
- フリーランスとしての働き方を検討
独身者が老後に備えるために知っておきたい制度・サービス
独身で老後に備えるには、さまざまな制度やサービスも活用していきたいものです。ここでは、特に知っておくと便利な制度やサービスをご紹介します。
iDeCo・新NISAの活用

40代・50代からでも、少額から始められる資産形成の方法はあります。特に注目したいのが「iDeCo(個人型確定拠出年金)」と「NISA(少額投資非課税制度)」です。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
- 掛金が全額所得控除になる
- 運用益が非課税
- 受取時も税制優遇あり
- 60歳までの加入で利用可能
- 掛金上限は月2.3〜6.8万円(職業による)
新NISA(2024年〜)
- 投資益が非課税
- 積立投資枠:年間120万円まで
- 成長投資枠:年間240万円まで
- 非課税保有限度額:1,800万円
- 非課税期間:無期限
例えば「iDeCoで所得控除を受けながら、新NISAで非課税の投資をする」といった組み合わせは、より効率的な資産形成が可能です。
高齢者向け住まい・介護保険制度の基本

独身者の場合、自宅での介護が難しいケースも多くみられるため、早めに高齢者向け住まいや介護サービスについての情報を収集しておくことが重要です。
高齢者向け住まい
- サービス付き高齢者向け住宅
- 有料老人ホーム
- グループホーム
- 特別養護老人ホーム など
介護保険制度
- 40歳から保険料を支払う
- 65歳以上で要介護認定を受けると各種サービスが利用可能
- 自己負担は1〜3割(所得による)
- 訪問介護、デイサービスなどの在宅サービス
おひとりさまでも頼れる「終活支援」「成年後見制度」など
「頼れる家族がいない独身の自分はどうしたらいいんだろう」と心配な方でも、以下のような制度やサービスを知っておくと、いざという場合スムーズに対応しやすくなります。
「まだ元気だから」と先送りにせず、元気なうちから選択肢を知っておくことで、いざというときに焦らず自分らしい暮らし方を選べるようになります。
終活支援サービス
- エンディングノートの作成支援
- 葬儀・墓じまいのサポート
- 遺品整理のアドバイス
- 相続・遺言のサポート
成年後見制度

- 判断能力が低下した際に財産管理や契約などをサポート
- 法定後見:すでに判断能力が低下している場合
- 任意後見:将来の判断能力低下に備えて事前に契約
見守りサービス
- 自治体の見守りサービス
- 食事配達、緊急通報システムなど民間企業の見守りサービス
- 地域のコミュニティ活動
特に、あらかじめ「任意後見契約」を結んでおくと、将来の安心につながります。
まとめ:独身の老後資金は「不安」ではなく「計画」で解決できる

独身者の老後に必要な資金は、住居の状況や健康状態、生活水準、収入などによって大きく左右されます。
40代・50代からでも「現状の把握」「支出見直し」「資産運用」「収入源の多様化」の4つのステップで十分な準備が可能です。具体的な数字を把握して計画的に準備することで、独身でも安心して迎えられる老後を実現しましょう。
老後資金は「一気に貯めるもの」ではなく、「毎月コツコツ積み上げるもの」です。行動を先延ばしにすればするほど、準備に使える時間は減っていきます。逆に、「いま始めれば、これから変えられる未来」があるのです。
不安なまま手を止めるのではなく、できることから始めてみましょう。ご自身の未来は、今の選択と行動で、いくらでも変えていけます。
なお、老後の豊かさは単にお金だけで決まるものではありません。経済的な準備と並行して、趣味や人とのつながり、健康なども意識していきたいものです。
▼ 当サイト「悩ミカタ」ではミドル世代(40代50代)の悩みや不安・ストレスについて各分野の専門家/カウンセラーに相談できるオンラインカウンセリングサービス「悩ミカタ相談室」を展開しています。不安な気持ち、1人で抱え込まずにまずはお気軽に相談してみませんか?

