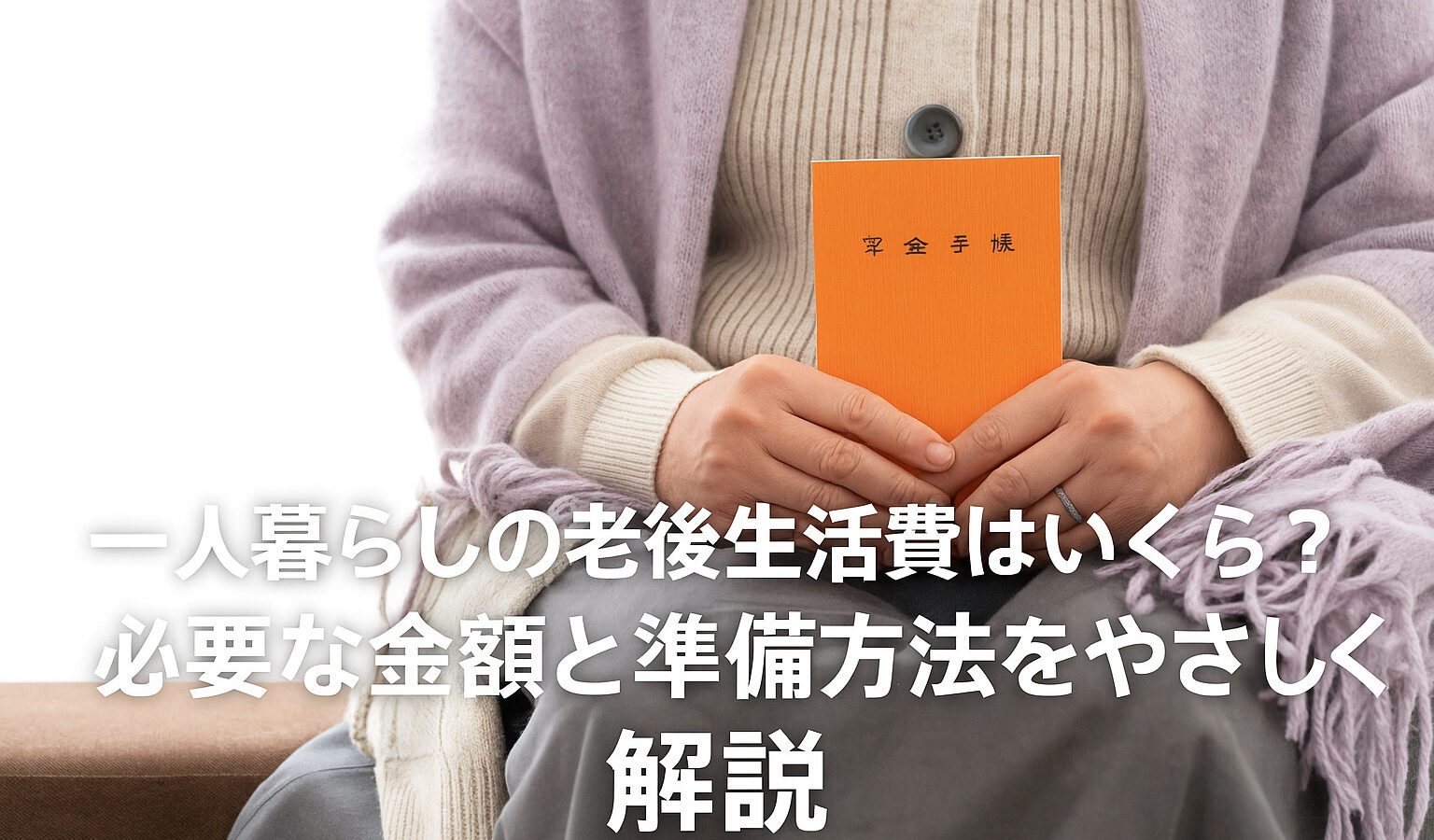「老後の一人暮らし、いまの貯蓄で大丈夫だろうか…」そんな不安を抱えていませんか。例えば持ち家がある方でも、年金だけで快適な老後生活を送れるのか心配になるのは自然なことです。
そこでこの記事では、老後に必要な生活費の目安から準備方法まで、50代からでも間に合う対策を解説します。「老後一人暮らしの生活費っていくらくらい?」「どう準備したらいい?」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
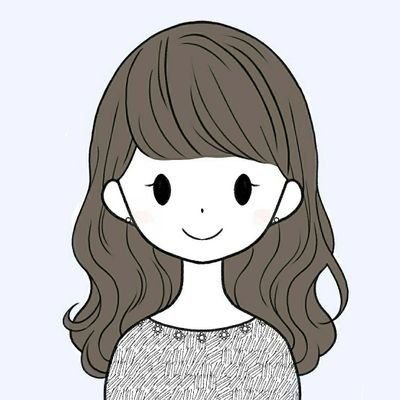
梅田ミズキさん
認定心理士、サービス介助士。大学で臨床心理学・産業組織心理学・発達心理学などを学び、卒業後は公的施設にて精神疾患の方のケアや介助業務、ご家族の相談対応などに従事しながら、ホームページ掲載用のコラムやミニ新聞を執筆。現在はフリーライターとして独立し、くらしにまつわるエッセイの執筆、臨床心理・発達支援・療育関連のコンテンツ制作および書籍編集に携わりながら、心理カウンセラーも務めている。趣味は読書、映画鑑賞、気まぐれで向かうプチ旅行。
一人暮らしの老後…生活費はいくらかかるのか?

総務省の家計調査によると、老後の一人暮らしにかかる平均的な生活費は、月に約15万円程度とされています。しかし、これはあくまで平均値です。住んでいる地域や生活スタイル、健康状態などによって大きく変わるといえます。
例えば、持ち家があれば家賃の心配はありませんが、固定資産税や修繕費などの支出は継続的に発生しますよね。また、年齢を重ねるにつれて医療費や介護関連の出費が増える可能性も考慮する必要があります。
「今は元気だから大丈夫」と思っていても、将来の不測の事態に備えておくと安心につながりやすいでしょう。老後の生活費を具体的に把握することは、これからの人生設計において非常に重要なステップなのです。
老後の収入と支出はどれくらい?生活に困らないために必要な金額の考え方
老後の生活を安心して送るためには、収入と支出のバランスを理解する姿勢が大切です。年金収入だけでは足りない部分をどう補うか、支出をどう管理するかを考えていきましょう。
一人暮らしの老後の平均収入

総務省統計局が2024年に公表した「家計調査報告[家計収支編]」によると、高齢者の一人暮らし世帯(65歳以上の単身無職世帯)の月の平均収入額は、約13万円です。
老後の主な収入源は公的年金といえますが、これは加入期間や納付状況、退職前の収入によって大きく異なります。国民年金のみの場合、満額でも生活費を賄うには難しい金額です。
年金以外の収入としては、退職金の運用益や資産運用からの配当、パートタイムでの就労収入などが考えられます。また、持ち家を活用したリバースモーゲージや空き部屋の賃貸なども選択肢の一つです。
大切なのは、年金見込額を正確に把握すること。「ねんきんネット」などのサービスを利用して、自分の年金受給見込額を確認しておきましょう。
一人暮らしの老後の平均支出

次に、高齢者の一人暮らし世帯(65歳以上の単身無職世帯)の月の平均支出額ですが、同じく「家計調査報告[家計収支編]」によると、約15万円です。
食費は月約4万円、住居費が約1万円、光熱費は1〜2万円が目安といえます。医療費は健康状態によって大きく変わりますが、月に0.5〜2万円程度見ておくと安心でしょう。
持ち家があれば家賃は不要ですが、固定資産税や管理費、修繕積立金などで月に1万円前後の出費は見込んでおく必要があります。また、10年に一度程度の大規模修繕や設備の更新なども必要になるため、そのための貯蓄も欠かせません。
さらに、娯楽費や交際費、被服費なども生活の質を保つために必要な支出です。特に一人暮らしの場合、社会とのつながりを維持するための交際費は、精神的な健康のためにも重要な支出といえるでしょう。
老後に向けて今からできる資金の準備方法
老後の生活に必要な資金を確保するためには、現在の生活を見直しながら計画的な準備が大切です。一人ひとりのライフスタイルや価値観に合った方法で、無理なく継続できる対策を考えていきましょう。
自分に必要な老後の資金を計算する

老後に必要な資金を準備するためには、まず具体的な目標金額の設定が重要です。一般的には「老後資金は2,000万円必要」などと言われますが、これはあくまで平均的な目安にすぎません。自分自身のライフスタイルや価値観、健康状態などによって必要額は大きく変わってきます。
計算方法としては「月々の必要生活費」から「年金などの定期収入」を差し引き、それに「老後の期間(年数)」をかけるという基本的な式があります。
▼例えば
月15万円の生活費に対して年金が月10万円→差額の5万円×12ヶ月×20年(65歳から85歳まで)で1,200万円が必要
また、この基本額に加えて、住宅の大規模修繕費用や医療・介護費用の備え、旅行などのライフイベント費用を上乗せして考えるのも大切です。老後の具体的なビジョンを実現する金額を積み上げていくことで、より現実的な目標設定ができるでしょう。
持ち家にかかる費用や介護費用を考えておく

持ち家があると家賃の心配はありませんが、住宅関連の費用は継続的に発生します。固定資産税、都市計画税などの税金、マンションであれば管理費や修繕積立金が毎月必要です。
また、10〜15年に一度は給湯器やキッチン、浴室などの設備更新や外壁塗装などの大規模修繕が必要となり、一度に数百万円の出費が生じる場合もあります。
特に気をつけたいのは、築年数が経過した持ち家の場合、老後に大規模な修繕や設備更新のタイミングが重なる可能性があることです。現在50代であれば、老後に入る頃には住宅も20〜30年経過していることになり、さまざまな箇所の劣化が進んでいると予想されます。
さらに、介護費用も大切な検討項目です。公的介護保険でカバーされる部分もありますが、要介護度や利用するサービスによっては自己負担額が月に数万円から十数万円に上ることもあります。
特に一人暮らしの場合、介護が必要になった際のサポート体制や費用負担について早めに考えておくと安心です。
できるだけ長く仕事を継続できる環境を整える

できるだけ長く収入を得続けるのも、老後の経済的な安定を図る効果的な方法の一つです。特に50代からであれば、健康状態や体力に合わせて、フルタイムからパートタイム、専門知識を活かした副業など、働き方を徐々に調整しながら70代まで何らかの形で働き続けられる可能性もあります。
まずは、現在の仕事を継続できる環境を整えることから始めましょう。健康管理はもちろん、デジタルスキルなど時代の変化に対応するために学び続ける姿勢も大切です。
また、これまでの経験やスキルを活かした新たな働き方の可能性も探ってみるのもよいでしょう。例えば、趣味や特技を活かした小規模ビジネスや、オンラインでのコンサルティングなど、体力的な負担が少なく自分のペースで取り組める仕事があるかもしれません。
長い期間を経済的にも精神的にも充実させるためには、「引退」という概念ではなく「緩やかな移行」として働き方を見直していくのが理想的です。
資産運用などを活用して計画的に貯蓄する

老後資金を効率的に準備するために、貯蓄だけではなく、資産運用の視点を取り入れてみるのもおすすめです。特に長期的な視点で考えると、低金利環境では預貯金だけでは資産が目減りしてしまうリスクもあります。
初心者におすすめなのは、少額から始められる積立投資です。投資信託やiDeCoなどの制度を活用することで、専門知識がなくても分散投資が可能になります。
iDeCo
- 税制優遇があり、掛け金が全額所得控除になるほか、運用益も非課税になるのがメリット
- 50代からでも60歳まで続けると、一定の資産形成が期待できる
NISA
- 年間の投資枠内であれば、運用益が非課税になる
- 特に長期的な資産形成を目指す場合は、複利効果も期待できるため、早めに始めるのがおすすめ
ただし、資産運用には元本割れのリスクも伴います。自分のリスク許容度を理解したうえで、無理のない範囲で取り組むことが大切です。必要に応じて、ファイナンシャルプランナーなどの専門家への相談も検討してみましょう。
関連記事はこちら→資産運用は誰に相談すべき?初心者におすすめの相談先と選び方ガイド
公的支援制度や民間保険の活用も検討する
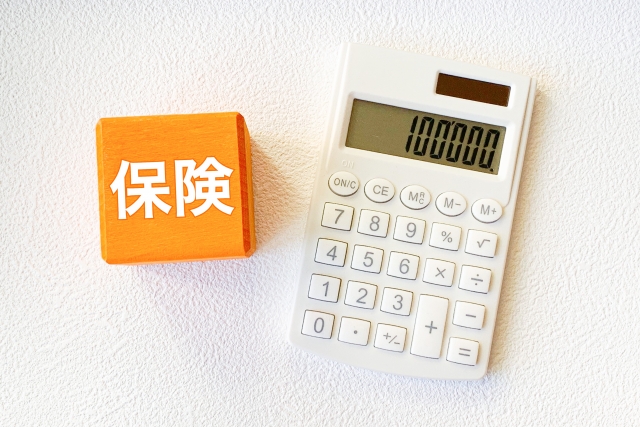
公的支援制度や民間保険などを活用するのも、老後の経済的な安心を確保する方法です。
公的支援制度
- 低所得者向けの「年金生活者支援給付金」
- 医療費の自己負担を軽減する「高額医療費制度」
- 介護保険サービスの自己負担額に上限を設ける「高額介護サービス費制度」など
上記以外でも、自治体独自の高齢者向け支援制度もあるため、お住まいの地域の制度を調べておくとよいでしょう。
民間保険
- 医療保険
- 介護保険
- 個人年金保険 など
特に、50代からでも加入しやすい「終身医療保険」や短期払いの「介護保険」などは検討する価値があります。ただし、保険料と保障内容のバランスを考慮し、本当に必要な保障は何かを見極めるのが大切です。
公的制度と民間保険をうまく組み合わせると、より安心できる老後の経済基盤を構築しやすくなります。自分の状況に合った最適な組み合わせを考えるために、必要に応じて専門家のアドバイスを受けるのも有効な方法です。
一人暮らしの老後の収支シミュレーション例
老後の生活をイメージするために、いくつかの具体的なシミュレーション例を見ていきましょう。自分の状況に近いケースを参考に、将来の収支バランスをより現実的に考えられます。
ケース1:年金中心の最低限の生活を送る場合
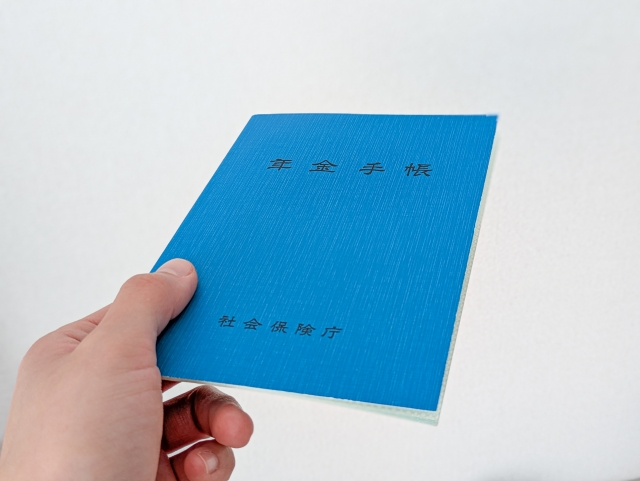
年金を主な収入源として最低限の生活を送る場合、収入と支出の内訳例は以下のようになります。
収入例
社会保障給付が月に12万円程度
支出例
- 食費3万円
- 光熱費1.5万円
- 通信費0.8万円
- 医療費1万円
- 固定資産税等(月割)0.5万円
- 生活用品費1万円
- 交通・交際費1万円
- その他雑費1万円
→合計9.8万円
このケースでは、月に2万円程度の余裕が生まれる計算になります。しかし、住宅の修繕費や突発的な医療費、介護費用などの臨時出費には対応できない可能性があるでしょう。また、旅行や趣味など生活の質を高める支出も制限されやすい状況といえます。
ポイント①住宅の緊急修繕や入院費用など、突発的な出費に対応するための「緊急資金」を確保しておく
たとえば、急な入院や家電の買い替え、住宅の修繕などは、いつ発生するか予測できません。こうした費用を年金だけでまかなうのは難しいため、最低でも生活費の3〜6か月分程度の現金を「いざというときのための備え」として準備しておくのがおすすめです。定期預金や即時に引き出せる普通預金など、すぐに使える形で確保しておくと安心です。
ポイント②生活の質を少しでも向上させたい場合、何らかの形で追加収入を得る工夫が必要
たとえば、これまでの経験や趣味を活かしてできる在宅ワークや、週に数日の短時間アルバイト、地域のシルバー人材センターへの登録などが挙げられます。また、不用品の販売や、空き部屋の貸し出しといった方法も視野に入るでしょう。
無理のない範囲で収入源を確保できれば、趣味や外食、旅行など、生活に彩りを添える支出にも余裕が生まれ、日々の満足感や生きがいにもつながります。
ケース2:ゆとりある老後生活を送る場合

ある程度ゆとりのある老後生活を送るケースの場合、収入と支出の内訳例は以下のようになります。
収入例
- 社会保障給付が月に12万円程度
- パートタイム収入が5万円
- 貯蓄や投資からの運用収入が3万円
→合計20万円
支出例
- 食費4万円
- 光熱費1.5万円
- 通信費1万円
- 医療費1.5万円
- 固定資産税(月割)0.5万円
- 生活用品費1.5万円
- 交通・交際費3万円
- 趣味・娯楽2万円
- その他雑費1.5万円
→合計16.5万円
このケースでは、月に3.5万円の余裕が生まれるため、旅行や趣味などの楽しみにも予算を割きやすくなります。また、余剰金を貯蓄に回すことで、将来の大きな出費にも備えられるでしょう。
ポイント①年金だけではなく追加収入の確保が必須
公的年金だけでは生活費や楽しみの支出をまかなうのが難しいため、パートタイムの仕事や在宅ワークなどで、無理のない範囲で安定的な収入を得る工夫が求められます。また、資産運用による収入も視野に入れるとよいでしょう。
たとえば、リスクを抑えた定期預金や個人向け国債、投資信託などを組み合わせておくことで、毎月の生活にプラスαの安心感を持つことができます。収入の柱が複数あることで、経済的にも精神的にもゆとりのある老後を実現しやすくなります。
ポイント②健康状態が許す限り、70代前半までは何らかの形で働き続けるのが理想的
働くことは、単に収入を得るためだけでなく、生活のリズムを整えたり、人とのつながりを持ち続けたりする意味でも非常に重要です。特に高齢期は社会との関わりが減りがちですが、仕事を通じて役割ややりがいを感じられることが、心身の健康にも良い影響を与えます。
無理のない範囲で、自分の得意分野や興味のあることを活かせる仕事を見つけることで、より充実した老後を過ごせるでしょう。週数日だけの勤務や、自宅でできる軽作業、地域活動の延長のような働き方も選択肢のひとつです。
ケース3:健康状態が悪化した場合

最後に、健康状態が悪化し、介護サービスを利用する必要が生じた場合のケースも考えておきましょう。
収入例
- 社会保障給付が月12万円程度
- 貯蓄取り崩しからの月5万円程度
→合計約17万円
支出例
- 食費3万円
- 光熱費1.5万円
- 通信費0.8万円
- 医療費3万円
- 介護サービス利用料3万円
- 固定資産税(月割)0.5万円
- 生活用品費1.5万円
- 交通・交際費1万円
- その他雑費1.5万円
→合計15.8万円
上記のケースでは、収支は何とかバランスが取れています。しかし、貯蓄の取り崩しが前提のため、長期間この状態が続くと貯蓄が枯渇するリスクがあります。また、要介護度が上がると介護費用も増加するため、さらに厳しい状況になる可能性も否定できません。
ポイント①健康状態の悪化は誰にでも起こりうること
健康状態の悪化は年齢に関係なく誰にでも起こりうるものであり、特に老後は予測が難しい突発的な変化に備えておくことが大切です。元気なうちから「もしものとき」の生活を想定しておくことで、心の準備ができ、慌てずに対応しやすくなります。
介護サービスの内容や費用、利用方法を事前に調べておくことや、地域の包括支援センターなど相談先を把握しておくことも、安心して老後を迎えるための備えとなるでしょう。
ポイント②ある程度まとまった貯蓄(少なくとも500万円以上)を確保しておくのが望ましい
介護が必要になった場合、想定以上に出費が増える可能性があります。たとえば、介護用の住環境整備や医療費、通院・訪問介護の交通費など、公的な支援だけではカバーしきれない費用が発生することも。
長期化することも見越して、最低でも500万円以上の貯蓄を確保しておくと、万一のときにも安心です。可能であれば、自分が要介護状態になったときの希望や準備について、家族とも話し合っておくとよいでしょう。
ポイント③介護保険や医療保険なども検討する
将来の介護リスクに備える手段として、公的介護保険だけでなく、民間の介護保険や医療保険への加入も一つの選択肢です。特に、要介護状態になったときに一時金や年金形式で給付が受けられる保険は、家計の負担を軽減する助けになります。
また、医療費がかさんだ際に備えて、入院や手術に対応できる医療保険を見直すことも大切です。保険は早めに加入することで保険料が安く済む場合もあるため、元気なうちから検討を始めておくと安心です。
老後の一人暮らしは「資金計画」が安心の鍵

老後の一人暮らしに向けた準備は、早ければ早いほど選択肢が広がります。しかし、50代からでも十分に対策は可能です。大切なのは、具体的な収支イメージを持ち、計画的に行動を始めることといえます。
一人で悩まず、必要に応じて専門家に相談しながら、自分らしい老後生活を実現するための一歩を今日から踏み出してみませんか。
▼ 当サイト「悩ミカタ」ではミドル世代(40代50代)の悩みや不安・ストレスについて各分野の専門家/カウンセラーに相談できるオンラインカウンセリングサービス「悩ミカタ相談室」を展開しています。不安な気持ち、1人で抱え込まずにまずはお気軽に相談してみませんか?