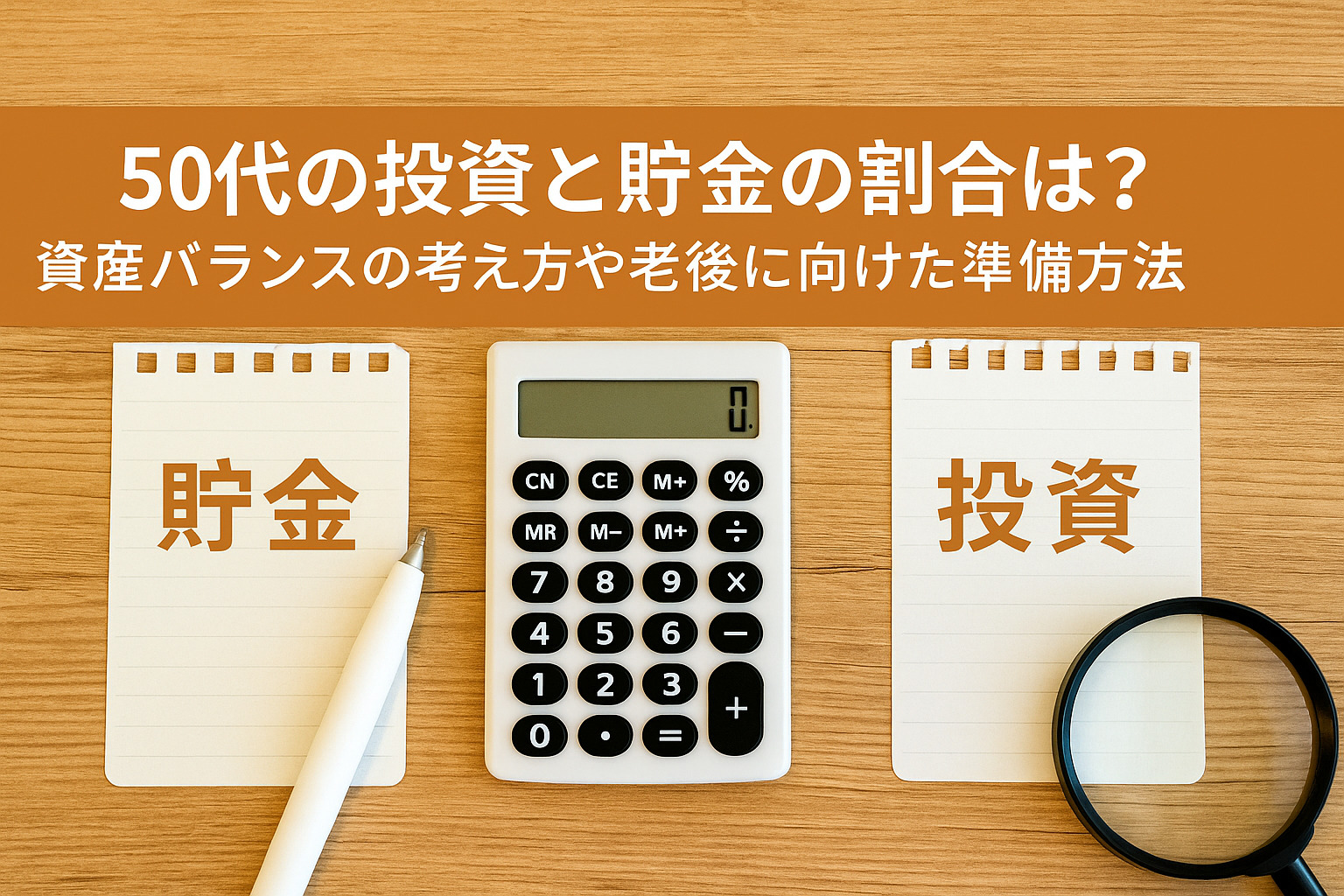50代になると、働き盛りのピークを迎えつつも、老後が少しずつ現実的に感じられる年代です。「このままの資産配分で大丈夫だろうか?」「貯金をどのくらい残しておけば安心なのか?」と悩む方も多いのではないでしょうか。特に、ある程度の貯金がある方ほど、資産をどのように振り分けるかが重要になってきます。
そこで本記事では、貯金と投資の割合に悩む50代男性に向けて、資産配分の考え方や老後に向けた準備方法を解説します。

キャリアカウンセラー・ライター
山田葉子さん
キャリアカウンセラー・ライター
国家資格キャリアコンサルタント/2級FP技能士
大学卒業後、人材業界で10年以上にわたりキャリア支援に従事。若手からミドル世代まで、多くの人の転職・キャリア相談に携わる。現在はフリーランスとして、企業の人材育成支援やキャリア講座の講師として活動するほか、働く人の悩みに寄り添うライターとしても活動中。得意テーマは「転職・キャリアチェンジ」「中間管理職の悩み」「女性の再就職・副業」。
50代の家計事情とは?収入と支出の特徴

まずは、今の自分の家計がどんな状態なのかを整理しておきましょう。収入と支出の傾向を知ることで、どれだけの資産を投資に回せるのか見えてきます。
子育て・住宅ローン・教育費のピークが落ち着く時期
50代は、ライフイベントが一段落しやすい時期です。子どもの教育費が終わりに近づき、住宅ローンの返済もゴールが見えてくる方が多いのではないでしょうか。
その一方で、親の介護、体調の変化による医療費、趣味や交際費の増加など、別の支出がじわじわと増えてくる傾向もあります。
年収や可処分所得の平均
50~54歳男性の平均年収は約689万円、55~59歳男性の平均年収は約712万円というデータ※があります。ただし、役職定年や早期退職制度など、将来的な収入ダウンのリスクを見越した資産設計が求められます。
※参照元:令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況(厚生労働省)
50代から増える支出項目とは?
人生の後半戦に差し掛かる50代は、これまでとは異なる種類の支出が増え始める時期でもあります。見落としがちな支出項目をあらかじめ把握しておくことが、資産配分を考えるうえでの第一歩です。
健康管理のための医療費・サプリ代
50代になると、定期検診や通院の機会が増え、医療費がじわじわと家計を圧迫し始めます。また、健康を意識してサプリメントや機能性食品にお金をかける人も多く、気づけば月数千円〜1万円以上の出費になることも珍しくありません。
両親の介護にかかる費用
親の介護が現実的になる年代でもあり、施設の入居費やヘルパーの利用料など、突発的に大きな出費が発生する可能性があります。公的介護保険を利用しても自己負担はゼロではなく、月額数万円単位での出費が続くケースもあります。
趣味や交際費
子育てが一段落し、時間や心のゆとりができると、趣味や旅行、人付き合いにお金をかけたくなるもの。特に同年代との交際費が増える傾向にあり、これらも長期的に見ると無視できない支出となります。
老後に向けた保険や資産運用の見直し費用
生命保険や医療保険、年金保険など、老後に備えるための保障内容を見直す時期でもあります。また、投資信託やNISA、iDeCoの活用など新たな資産運用を始める際には、口座開設や運用手数料といったコストもかかる点に留意が必要です。
これらを踏まえ、「今が資産配分を見直すラストチャンス」という意識を持つことが大切です。
50代の資産配分はどうあるべき?投資と貯金の適切な割合

家計の現状を把握できたら、次は「貯金と投資のバランス」を考えていきましょう。ここでは、年代に応じた資産配分の基本と、貯金・投資それぞれの役割を整理します。
一般的な資産配分の考え方
「年齢=債券の比率」という考え方は、昔からある資産運用の目安のひとつです。たとえば、50代なら「安定資産50%、リスク資産50%」が一つの参考値になります。ただし、最近では「自分のリスク許容度やライフプランに応じて調整する」ことが重視されており、一律のルールにこだわる必要はありません。
貯金と投資、それぞれの役割と目的を整理する
- 貯金(現金):病気や災害など、緊急時の「生活防衛資金」としての役割
- 投資:将来に向けた「資産を増やす手段」。インフレ対策としても有効
この2つをしっかり切り分けて考えることで、無理のないバランスが見えてきます。
「生活防衛資金」はいくら確保すべき?

生活費の6〜12ヶ月分を現金で持っておくのが一般的な目安です。たとえば月30万円の生活費なら、180万〜360万円は現金でキープしておくと安心です。
目安としての資産バランス:貯金60%・投資40%?それとも逆?
- リスクを抑えたい人:貯金60%・投資40%
- 積極的に増やしたい人:貯金40%・投資60%
大切なのは、「リスク許容度」「資産状況」「将来のキャッシュフロー」をふまえて自分に合った比率を決めることです。
老後を見据えた資金計画:どれくらい準備すれば安心?

資産配分を決めるには、「老後にいくら必要か」というゴールを明確にすることが不可欠です。ここでは、老後の支出や年金の受取額をもとに、不足分をどう補うかを考えていきます。
老後の生活費のシミュレーション…月額いくら必要か
総務省の家計調査によると、高齢夫婦無職世帯の平均支出は約27万円/月、独身の場合でも、家賃や医療費を含めると20〜25万円/月が目安※となります。
※参照元:家計調査のしくみと見方(総務省統計局)
公的年金でまかなえる金額はどれくらい?

50代男性の将来の年金見込み額は、月14〜16万円程度が平均とされています※。つまり、毎月5〜10万円程度の不足が生じることになります。
不足分をどう補う?貯蓄・投資・退職金の活用
老後の生活費における不足分をカバーするためには、複数の手段をバランスよく活用することが重要です。ここでは代表的な3つの方法について見ていきましょう。
定期預金や保険による備え

定期預金や個人年金保険などは、リスクを抑えてお金を貯めたい人に適した方法です。利率は低めですが、元本保証があることから、安定性を重視したい50代には心強い選択肢です。
投資信託や株式、ETFなどでの運用
投資信託やETFは、つみたてNISAやiDeCoといった制度を利用すれば、月1,000円程度の少額から始められます。制度を活用することで、非課税のメリットを得ながら、分散投資によってリスクを抑えることが可能です。ある程度の運用期間を確保できる50代後半までは、資産の一部をこうしたリスク資産で運用するのも効果的です。
退職金を活かした資産配分の見直し

退職金は老後資金の柱となるまとまった資金です。一括で使うのではなく、「生活費用」「医療介護対策」「投資・運用」など目的別に分けて管理するのが基本です。特に退職金の一部を投資に回す際は、元本保証型の商品や安定資産と組み合わせるなど、慎重な運用設計が求められます。
資産を切り崩す前提ではなく、「資産に働いてもらう」仕組みが大切です。
50代に適した投資の選び方とは?リスクを抑えた資産運用
老後資金を効率的に増やすには、投資の活用も重要です。ただし、50代には50代に合った投資のスタイルがあります。ここでは、具体的な投資の方法や注意点を紹介します。
投資信託やETFなどの分散投資が基本

1つの商品に偏らず、複数の資産に分けて投資する「分散投資」は、リスクを下げる最も基本的な方法です。50代であれば、インデックス型の投資信託やETFなどを活用するのが賢明です。
特に、国内外の株式・債券・不動産などに幅広く投資できるバランス型ファンドは、資産全体のリスクを抑えながら安定的なリターンを期待できます。また、ETF(上場投資信託)は手数料が比較的安く、長期保有にも適しています。リスク許容度に合わせて、自分に合ったポートフォリオを構築していくことが大切です。
債券・定期預金・保険商品の活用も選択肢に

大きなリターンは見込めませんが、安定資産として債券や定期預金、年金保険なども組み合わせることで、より堅実なポートフォリオが作れます。
特に、資産全体のうち一定割合を安全資産に振り分けることで、株価の急変動にも冷静に対応できる余裕が生まれます。定期預金や個人向け国債は元本保証があり、リスクを最小限に抑えたい方に適しています。年金保険などは受取時期や保障内容を確認しながら、長期的な収入源の一部として検討するのが良いでしょう。
50代に向いていない投資とは?
50代はリスクを取りすぎず、着実に資産を守ることが重要な時期です。以下のような投資は、損失の可能性が高く、慎重な判断が求められます。
仮想通貨など価格変動の大きい商品

仮想通貨は値動きが極めて激しく、短期間で資産が大きく上下する可能性があります。少額なら挑戦する余地もありますが、老後資金の中核に据えるのは非常にリスキーです。
FXや信用取引などレバレッジをかけた投資

少ない元手で大きな取引ができる反面、わずかな値動きで大きな損失につながるのがレバレッジ取引です。退職後の収入が限られる50代以降にとっては、精神的な負担も大きく、安定運用には不向きといえます。
無計画な個別株投資
情報や根拠のないまま話題性や感覚だけで株を買うと、大きな損失につながるリスクがあります。特に、退職金などまとまった資金を一気に投入してしまうのは避けたいところです。個別株に投資する場合でも、企業分析や分散投資を徹底する必要があります。
これらは短期的な損失リスクが高いため、慎重な判断が必要です。
具体的にどう振り分ける?ケース別・資産配分の例
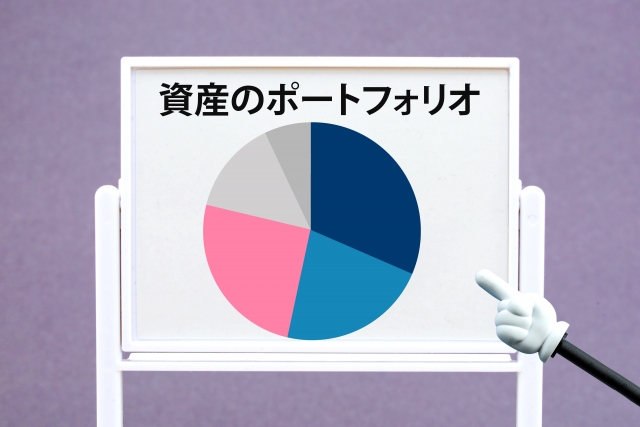
資産配分の基本を学んだら、あとは「自分に合ったバランス」を見つけて実行するのみです。ここでは、状況別におすすめの配分パターンをご紹介します。
ケース①貯金が多めでこれから投資を始めたい人
資産の80%が現金という方なら、まずは投資信託やつみたてNISAなどから始め、10〜20%を投資に移すことをおすすめします。
すでに十分な生活防衛資金がある場合は、残りの一部をリスクを抑えた投資に回すことで、将来の資産形成にもつながります。いきなり大きな金額を動かすのではなく、毎月一定額をコツコツ積み立てるスタイルが安心です。たとえば「毎月3万円だけ投資信託を買う」といった小さな一歩でも、長期的には大きな差になります。
ケース②すでに投資をしているがバランスを見直したい人
資産の50%以上を株に偏らせている方は、債券や現金を増やして安定性を確保しましょう。
株式市場は好調なときはリターンが大きい一方、下落時のダメージも大きくなります。50代は退職や老後資金の引き出し時期が近づくため、資産全体を安定化させることが重要です。年齢に応じてリスク資産の比率を少しずつ下げ、資産を守る意識に切り替えていくことが将来の安心につながります。
ケース③収入に余裕があり、積極的に資産を増やしたい人
生活費や緊急資金を確保したうえで、投資比率を60〜70%に引き上げるのもひとつの戦略です。
特に、教育費や住宅ローンの支出が落ち着き、可処分所得にゆとりが出てきた50代は、今後10年で効率的に資産を増やすラストチャンスとも言えます。株式やREIT、インデックス型の投資信託などを活用しつつ、分散と長期運用を基本にすれば、将来に向けた資産形成を着実に進めることができます。自分のライフプランと照らし合わせながら、計画的に投資比率を高めていきましょう。
まとめ:50代の今だからこそ、堅実な資産設計を

50代は、まだ資産形成に間に合う最後のタイミングです。これまでの働き方や支出を振り返り、これからの暮らしを見据えて資産のバランスを整えることが、将来の安心につながります。
老後に対する漠然とした不安は、何も特別なことではありません。ただし、不安を不安のままにせず、具体的な数字や行動に落とし込むことで、備えに変えることができます。
貯金と投資の「目的」を分けて考え、まずは自分に合った資産配分をシミュレーションしてみましょう。もし判断が難しければ、専門家に相談するのも良い選択です。
「安心できる老後」とは、万全な準備ではなく、「できる範囲で手を打ってある」状態のこと。まずは手元の資産と支出を見える化することから始めてみましょう。それだけでも、老後の不安はぐっと軽くなるはずです。この記事が、あなたの資産形成を見直すきっかけになれば幸いです。
▼ 当サイト「悩ミカタ」ではミドル世代(40代50代)の悩みや不安・ストレスについて各分野の専門家/カウンセラーに相談できるオンラインカウンセリングサービス「悩ミカタ相談室」を展開しています。不安な気持ち、1人で抱え込まずにまずはお気軽に相談してみませんか?