住宅ローンや子どもの教育費で貯蓄ができていない50代の方は少なくありません。「いまからでは遅いのでは?」と不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、老後に必要な金額や資金の具体的な準備方法などをご紹介します。「お金に困らずに老後生活を送りたい」という方は、ぜひ参考にしてみてください。
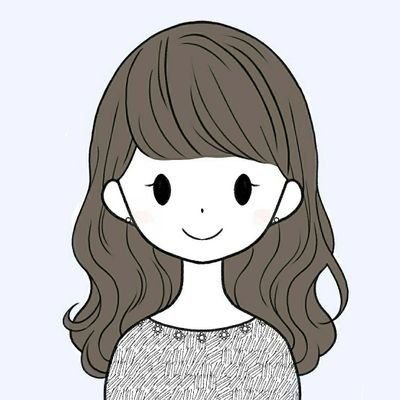
梅田ミズキさん
認定心理士、サービス介助士。大学で臨床心理学・産業組織心理学・発達心理学などを学び、卒業後は公的施設にて精神疾患の方のケアや介助業務、ご家族の相談対応などに従事しながら、ホームページ掲載用のコラムやミニ新聞を執筆。現在はフリーライターとして独立し、くらしにまつわるエッセイの執筆、臨床心理・発達支援・療育関連のコンテンツ制作および書籍編集に携わりながら、心理カウンセラーも務めている。趣味は読書、映画鑑賞、気まぐれで向かうプチ旅行。
50代で貯金がないのはまずい?リアルな現状とリスクとは

実は、50代で「貯金がほとんどない」と感じている方は珍しくありません。住宅ローンの返済や子どもの教育費など出費が重なる時期を乗り越えてきた結果、手元に残るお金が少ないのは自然なことです。
しかし、このまま対策をとらずに定年退職を迎えると、以下のようなリスクが挙げられます。
- 収入が激減する一方で、生活費や医療費などの支出は続く
- 予期せぬ出費に対応できない
- 生活の質を大きく下げざるを得ない状況に陥る可能性がある
まずは自分の現状をしっかり把握し、できる対策を着実に進めていくことが重要です。
老後の収入と支出はどれくらい?生活に困らないために必要な金額の考え方
年金だけでは足りないといわれる老後の生活費。実際にどのくらいの準備が必要なのか、また50代から対策を始める効果についてみていきましょう。
50代で「貯金ゼロ」はどれくらいいる?世間の平均と比較

「50代で貯金がゼロの人なんてほとんどいないはず」と思っている方もいるかもしれません。しかし、令和5年の50代の金融資産非保有、いわゆる貯金ゼロの世帯の割合は、二人以上世帯で27.4%、単身世帯で38.3%との結果が出ています。
背景には、子どもの教育費や住宅ローンといった大きな出費に加え、親の介護費用が重なるケースがあるようです。また、近年は非正規雇用の増加や景気低迷の影響もあり、思うように収入が増えないまま50代を迎える方も少なくありません。
「自分だけがお金に困っている」と思い詰める必要はありませんが、同時に「みんなそうだから大丈夫」と対策を先延ばしにするのも避けるべきでしょう。
【参考】家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査] 令和5年調査結果 各種分類別データ シート4|知るぽると 金融広報中央委員会
家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査] 令和5年調査結果 各種分類別データ シート4|知るぽると 金融広報中央委員会
このままでは危険?老後に直面するお金のリスク

個人差はあるものの、平均的な年金支給額と一般的な生活費の差額は、月に5〜10万円ともいわれています。これが年間で60〜120万円の不足となり、20年間では1,200万円から2,400万円もの金額です。
また、年齢を重ねるにつれて医療費や介護費用も大きな負担になります。特に70代以降は突発的な入院や介護サービスの利用が増える傾向にあり、公的保険でカバーされない部分の自己負担は決して小さくありません。
さらに、住宅の修繕費や家電の買い替えなど、大きな出費への備えも必要です。こうしたリスクに対応するための貯蓄がないと、子どもに経済的負担をかけたり、質素な生活を強いられたりする可能性が高まります。
「もう遅い」は本当?今からでも対策できる理由

とはいえ「50代で貯金がほとんどないから手遅れだ」と諦める必要はありません。
まず、50〜60代前半にかけては、一般的に収入がピークを迎える時期でもあります。この時期の収入を上手に貯蓄に回すと、短期間でもある程度の資金を蓄えられるでしょう。
また、子どもの独立や住宅ローンの完済などで、徐々に支出が減少していく時期でもあります。さらに、資産形成など公的な制度を味方につけるのも一つです。資産形成については、後ほど説明いたします。
何より大切なのは「いまからでは間に合わない」と考えて何もしないよりも「できることから始める」という前向きな姿勢です。たとえ理想的な金額に届かなくても、今後10年間で着実に準備を進めると、老後の生活の質は変わりやすくなります。
老後にいくら必要?生活費と収入のリアルな目安
老後の生活を安心して送るためには、実際にどれくらいのお金が必要になるのでしょうか。
年金だけでは足りない?老後の主な収入と不足額

老後の主な収入源は、公的年金です。しかし、年金は加入期間や報酬額によって大きく変動します。
総務省統計局が2024年に公表した「家計調査報告[家計収支編]」によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯(夫婦高齢者無職世帯)の平均月間収入は約25万円です。一方、平均月間支出は約26万円となっており、年金だけではカバーしきれない「不足額」が生じます。
この差額を埋めるためには、以下のような収入源の確保が重要です。
- 退職金の計画的な活用
- 個人年金
- 貯蓄からの取り崩し
- 定年後の就労収入 など
まずは、ご自身の年金見込額を「ねんきんネット」で確認し、具体的な不足額の把握から始めてみましょう。
生活費はどれくらいかかる?一人暮らし・夫婦それぞれのケース

「家計調査報告[家計収支編]」に基づく、一人暮らし・夫婦世帯の老後の生活費は、以下のとおりです。
| 支出項目 | 65歳以上の夫婦のみの世帯 | 65歳以上の単身世帯 |
| 食費 | 約8万円 | 約4万円 |
| 住居費 | 約2万円 | 約1万円 |
| 光熱・水道費 | 約2万円 | 約1.5万円 |
| 保健医療費 | 約2万円 | 約1万円 |
| 交通・通信費 | 約3万円 | 約2万円 |
| 平均月間支出 | 約26万円 | 約15万円 |
特に注目なのは、年齢が上がるにつれて医療費や介護関連費用が増加する傾向にある点です。また、趣味や旅行などの娯楽費、冠婚葬祭費なども考慮する必要があります。都市部と地方では物価差もあるため、ご自身が住む地域に合わせた試算が重要です。
また、退職後には通勤費や仕事関連費用が不要になる一方、自宅で過ごす時間が増えることで光熱費が増加するなど、支出の変化も考慮すべきでしょう。
少なくとも月々の不足額×12ヶ月×予想される老後期間(20〜30年)の貯蓄が理想的です。
老後の「備え」がないとどうなる?ありがちな3つの失敗
老後の備えが不十分だと、多くの方が以下のような状況に陥りがちです。
予想外の出費に対応できない
① 住宅の修繕や家電の買い替え
築年数が経過した住宅では、屋根や外壁、水回りの修繕といった高額な工事が必要になることがあります。また、冷蔵庫や洗濯機、エアコンなどの家電も10年を超えると買い替えが発生しやすく、数十万円単位の支出になることも。
年金収入だけではこうした突発的な支出に柔軟に対応できず、生活費を切り詰めざるを得ない状況に陥ることもあります。
② 突然の入院など予想外の出費
高齢になると病気やケガによる入院・手術のリスクも高まります。高額療養費制度などで一定の軽減はされるものの、差額ベッド代や通院交通費、付き添いサービスなど保険が効かない支出も多く、家計に大きな負担となります。
これらの費用をまかなう備えがないと、急な出費に対処できず不安が増す一方です。
子どもや親族に経済的負担をかける
① 次の世代の生活設計にも影響
自分の老後資金が不足していると、子どもに仕送りを頼らざるを得なかったり、生活の一部を支援してもらう必要が出てきます。そうなると子ども世代の貯蓄や住宅ローン、教育費など将来設計に大きな影響を及ぼし、経済的な連鎖負担を生んでしまいます。
② 親の介護と自分の老後の両方を心配する「ダブルケア」問題も深刻
特に50代〜60代の世代では、親の介護と自分たち夫婦の老後の備えが重なる「ダブルケア」が深刻化しています。経済的に余裕がない場合、介護費用や生活費が捻出できず、心身ともに大きな負担を抱えるケースも少なくありません。
選択肢が限られる生活を強いられる
① 趣味や旅行などの楽しみを諦めざるを得なくなる
限られた年金収入や貯蓄で日々の生活をまかなう必要があるため、趣味や旅行、外食といった「心のゆとり」につながる支出を削ることになりがちです。結果として、楽しみの少ない毎日を送ることになり、生活の満足度や幸福感も低下しやすくなります。
② 住み慣れた家を売却して狭い住居に引っ越さざるを得なくなる
住宅ローンの返済や固定資産税、維持費などが負担になり、やむを得ず住み慣れた家を手放す高齢者もいます。資金確保のために不本意な住環境の変化を強いられることは、精神的にも大きなストレスとなり、暮らしの質の低下につながります。
老後は、人生の3分の1を占める大切な時間といえます。経済的な理由で選択肢を狭めず自分らしい生活を送るためにも、いまからできる備えを始めるのがおすすめです。
50代からでも間に合う!今からできるお金の備え方
繰り返しになりますが、老後の備えは、50代からでも決して遅くありません。まずは現状を正確に把握し、収入を増やして支出を見直す具体的な方法を見ていきましょう。
まずは「収支の見える化」から始めよう

老後の資金準備を始める最初のステップは、現在の家計の収支を明確にすることです。
①給与明細や通帳、クレジットカードの明細などを集める
②月々の収入と支出を書き出す
③支出を「固定費」と「変動費」に分けて整理する
固定費:住宅ローン、保険料、通信費など
変動費:食費、日用品、交際費など
④家計簿アプリを活用
⑤年間を通じた大きな支出もリストアップ(子どもの学費、車検、旅行費用など)
⑥ねんきんネットで将来の年金受給見込み額を確認
⑦現在の生活水準を維持するためにはいくら不足するかを計算
上記のような過程では「老後までにいくら貯める必要があるか」「毎月いくら貯蓄に回せればよいか」が明確になります。具体的な数字を見ると、不安が増す場合があるかもしれません。しかし、現状を正確に知ることが、効果的な対策への第一歩です。
収入を増やす方法

50代でも専門性や経験を評価される職種は多く、年収アップにつながるケースもあります。50代から収入を増やす方法の一例は、以下のとおりです。
本業でのキャリアアップ
- 職場での昇進や昇給の可能性を探る
- スキルアップや資格取得に挑戦
- 専門性の高い資格取得で収入アップ
副業の検討

- 本業のスキルを活かした副業
- 趣味を活かした小規模ビジネス
- 空き時間を有効活用できるオンライン副業を検討
転職という選択肢
- 専門性や経験を評価される職種を選ぶ
- 経験豊富な50代の需要が高い人材不足業界での勤務を検討
年金の繰下げ受給の検討
- 65歳から受給開始を遅らせると1ヶ月あたり0.7%増額
- 70歳まで繰り下げると42%増の年金を受け取れる
いずれも、健康状態や家族の状況、働ける期間などの考慮が必要です。ご自身に合った収入アップの方法を選びましょう。
支出を抑えるコツ

収入を増やすと同時に、支出を見直すことも重要です。
固定費の見直し
- 住宅ローンの借り換えで金利を下げる
- 保険の見直し(医療保険や生命保険は必要な保障だけに絞る など)
通信費の見直し
- 携帯電話の料金プラン
- 固定回線
- 動画配信サービスなど
変動費の見直し
- 食費の節約(まとめ買いや特売日の活用、食材の使い切り、外食や中食の頻度見直しなど)
- キャッシュレス活用(クレジットカードのポイント還元、各種キャッシュレス決済のキャンペーン活用など)
ただし、必要以上に質素な生活を強いると、生活の質の低下にもつながります。「削れる支出」と「生活の質を維持するために必要な支出」のバランスを考えながら、無理のない範囲で支出の見直しを進めていきましょう。
少額からでもできる!資産形成の基本

50代からでも、少額から始められる資産形成の方法はいくつかあります。特に注目したいのが「iDeCo(個人型確定拠出年金)」と「NISA(少額投資非課税制度)」です。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
- 掛金全額が所得控除になる税制メリット
- 50代の方は毎月最大23,000円(年間276,000円)まで拠出可能
- 60歳までに加入すれば利用可能
- 掛金は投資信託などで運用され、60歳以降受け取り時も税制優遇あり
NISA(少額投資非課税制度)
- 投資で得た利益が非課税になる制度
- 「新NISA」では年間360万円までの非課税投資枠
- 初心者向けの「つみたてNISA」なら少額からのコツコツ投資が可能
どちらの制度も、長期・分散・積立が基本の堅実な投資方法が向いています。投資初心者の場合、まずは投資信託から始めるのがおすすめです。世界中の株式や債券に幅広く投資することで、リスクを分散させながら資産形成を目指せます。
ただし、投資には元本割れのリスクもあるため、生活費などの必要資金は別に確保したうえで行うのが基本です。
焦らなくて大丈夫。今からの一歩が将来を変える
冷静に対策を練って一歩ずつ進んでいくことで、未来は少しずつ変わっていきます。最後に、前向きに行動するためのポイントをご紹介します。
不安な気持ちに寄り添いたい——50代から始める人生設計

「50代になって貯金がほとんどない」という現実に直面すると、強い不安や自己嫌悪に襲われることもあるでしょう。まずは「もっと早くから貯金しておけば」「このままでは老後が心配だ」という自分の感情を否定せず、受け止める姿勢が大切です。
50代は、人生経験も豊富で判断力も高まっている時期といえます。子育てがひと段落し、自分のために使える時間やお金が増えてくる方もいらっしゃるでしょう。これまでの経験を活かして「いまからでも間に合う」という前向きな気持ちで、残りの職業人生をどう過ごすか、退職後の生活をどう設計するかを冷静に考えてみましょう。
「自分には無理」と思わないで。相談できるプロを味方にしよう

老後の資金計画は専門的な知識が必要な部分も多く、一人で考えると「難しすぎる」と感じるものです。そんな場合は、専門家の力を借りることを検討してみてください。
ファイナンシャルプランナー(FP)は、あなたの現状と目標を伺ったうえで、最適な資金計画を提案してくれます。豊富な経験と知識を持っているため、具体的なアドバイスが得られるでしょう。
また、以下のような相談窓口もあります。
- 金融機関の無料相談サービス
- 地域の消費生活センター
- 年金事務所
「プロに相談するのはお金がかかるから…」と躊躇する方もいるかもしれません。しかし、一人では気づかなかった対策や効率的な資産形成の方法などを知ることができるメリットは、相談料をはるかに上回る場合が多いのです。
まずは無料相談から始めてみてはいかがでしょうか。
これから10年、どう生きる?まずは現状を見つめ直すことから
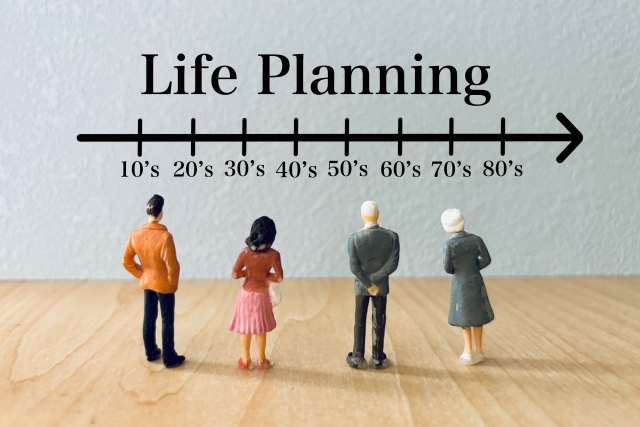
50代から定年までの約10年間は、老後への準備期間として非常に重要です。この期間をどう過ごすかによって、退職後の生活の質が大きく変わります。まずは自分自身の価値観や優先順位を見つめ直してみましょう。
「老後に何をして過ごしたいか」「どんな生活を送りたいか」という理想の未来像を具体的に描くことで、必要な資金計画も明確になります。また、健康管理にも気を配ることが大切です。いくらお金の準備ができていても、健康を損なっては充実した老後は送れません。定期健診の受診や適度な運動、バランスのよい食事など、いまからできる健康投資も重要です。
「老後の備え」は、決して経済面だけの問題ではありません。人間関係や趣味、社会とのつながりなど、お金以外の「資産」も大切です。残りの職業人生を充実させながら準備を進めることが、本当の意味での「老後の安心」につながるのです。
▼ 当サイト「悩ミカタ」ではミドル世代(40代50代)の悩みや不安・ストレスについて各分野の専門家/カウンセラーに相談できるオンラインカウンセリングサービス「悩ミカタ相談室」を展開しています。不安な気持ち、1人で抱え込まずにまずはお気軽に相談してみませんか?

