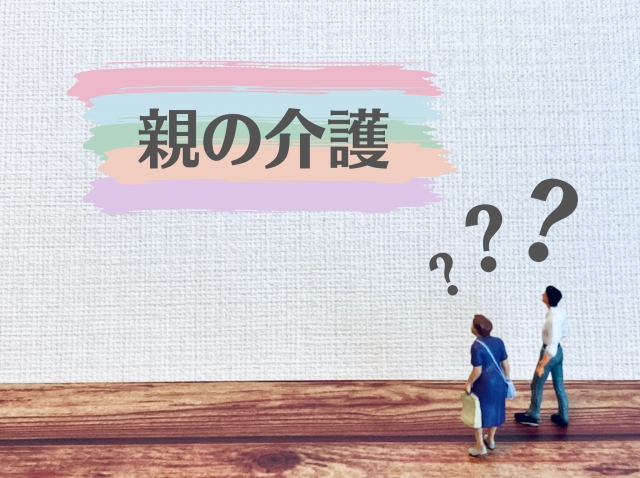「正直、親の介護をしたくない…」そう感じる方は、少なくありません。
特に50代前後の働き盛り世代にとって、仕事、自身の家庭、そして迫りくる老後の不安など、考えるべきことは山積みです。「これ以上、親の介護まで手が回らない」と感じるのは、決して特別なことではありません。また、これまでの親子関係によっては、どうしても介護に前向きになれないという方もいらっしゃるでしょう。
その一方で、「もし、自分が介護しなかったらどうなるんだろう?」「法的に何か問題は?」といった現実的な疑問や不安が頭をよぎるかもしれません。
そこでこの記事では、なぜ「親の介護をしたくない」と感じてしまうのか、その理由を深掘りし、実際に介護をしない場合に起こり得ること、そして、罪悪感や負担を減らしながら親と関わるための具体的な対処法を解説します。
この記事が、あなたとご家族にとって納得のいく道筋を見つける一助となれば幸いです。
関連記事はこちら→親の介護費用はいくら?施設に入れたいけれどお金がないときの対処法や補助制度

介護福祉士・ケアマネジャー・社会福祉士
中谷ミホさん
介護福祉士、社会福祉士、ケアマネジャー、保育士。福祉系短大を卒業後、介護職員・相談員・ケアマネジャーとして介護現場で20年活躍。現在は介護業界での経験を生かし、介護に関わる記事を多く執筆。介護・福祉関連書籍の監修も手掛けている。 X(旧Twitter)
親の介護をしたくないと思うのは自然なこと

親の介護問題が現実味を帯びてくると、「自分の人生が大きく変わってしまうのではないか」「仕事との両立は?」「兄弟や親族との関係が悪化しないか?」といった不安が頭をよぎります。そうした状況で、「本音を言えば介護なんてしたくない」と感じる人も少なくありません。
一見すると親不孝のように思えるかもしれませんが、この感情は決して特別なものではなく、多くの人が抱えるごく自然な感情なのです。
なぜ「したくない」と思ってしまうのか
親を思う気持ちと、自分の生活を守りたい気持ちがぶつかるとき、人は「介護なんてしたくない」と感じることがあります。
この葛藤の背景には、経済的負担や時間の拘束、将来に対する不安など、さまざまな要因が絡んでいます。
介護にかかる費用や医療費、施設入居にかかる出費が家計を圧迫することもあれば、通院の付き添いや日常的な身体介助で自由な時間が減ることへのストレスもあるでしょう。
また、親子関係が良好とは限らず、これまでの確執や距離を置いてきた親と密接な関係になることに抵抗を感じる方も少なくありません。
こうした現実的な問題が、「介護をしたくない」という気持ちを引き出してしまうのです。
「親の介護をしたくない」は悪ではない
「親の介護は子どもがするべき」という価値観は根強くありますが、実際にはすべての人が介護に向いているわけではありません。
身体的なケアに強い抵抗がある人や、精神的に負担を感じやすい人にとって、無理をして介護を担うことは、かえって親子ともにストレスを高めてしまいます。
大切なのは「介護したくない」という感情を否定せず、現実的な選択肢を持つことです。たとえば、在宅介護サービスや施設入所といった外部のサービスを上手に利用することで、無理のない範囲で介護に関わることも可能になります。
理想論ではなく、自分に合った現実的な対応を選ぶことが、結果的にうまくいく近道なのです。
親を介護したくない・できない理由
「介護したくない」という気持ちの裏には、単なる感情だけでなく、人それぞれが抱える切実な事情や、現実的な困難が存在します。主な理由を見ていきましょう。
毒親・親子関係の悪化

親との関係が長年にわたって悪かった場合、「もう関わりたくない」「介護なんて考えられない」という思いが湧くのは当然のことです。
たとえば、精神的・身体的な虐待、過干渉、人格を否定するような言動などにさらされてきた方にとっては、親とのやりとり自体が強いストレスとなります。介護を引き受けることが、過去のトラウマを再び呼び起こし、強い精神的苦痛を伴う可能性があります。
このような場合は、ご自身の心を守ることを最優先に考えてください。無理に直接関わろうとせず、ケアマネジャーや地域包括支援センター、カウンセラーといった第三者に相談し、適切な距離を保ちながら必要な支援につなげる方法を探るのが賢明です。
仕事や家事、育児との両立が難しい

親の介護が必要になる年代の多くは、自身の仕事や家庭生活においても多忙な時期と重なります。特に50代は、職場で重要なポジションを担っていたり、子どもの進学や独立、あるいは自分自身の老後準備も始めたい時期です。
このような状況の中で、日常的な介護を行うのは現実的に非常に難しいことです。もし介護のために仕事を辞めたり、働き方を変えたりすれば(介護離職)、収入減による経済的な困窮だけでなく、キャリアの断絶や社会とのつながりの希薄化など、その後の人生設計に大きな影響を及ぼしかねません。「したくない」というより「物理的にできない」という悲鳴に近い状況も少なくないのです。
自分が介護に向いていないと感じる
介護に対して強い抵抗感を持つ人もいます。たとえば、衛生面に敏感で排せつや入浴の介助にどうしても踏み込めない場合や、人の世話をすること自体に苦手意識がある場合です。
こうした性格や気質は、決して「冷たい」とか「わがまま」ではなく、向き不向きの問題です。また、痰の吸引や経管栄養など医療ケアが必要な場面では、専門的な知識や技術が求められることもあります。
無理をして自分で対応しようとするより、専門職に任せるほうが親にとっても安全で安心できるケースが多いのです。
親の介護は子どもの義務? しないとどうなる?

「介護は子どもの義務なのか」「何もしないと法律的に問題があるのか」といった疑問を持つ方もいるでしょう。この点を正しく理解しておくことが、不安の解消につながります。
法律上の「扶養義務」と介護の違い
日本の民法では、直系血族(親子、祖父母と孫など)および兄弟姉妹は、互いに「扶養義務」を負うと定められています(民法第877条)。
また、特別な事情があれば、三親等内の親族が家庭裁判所の判断で扶養義務を負うこともあります。
重要なのは、この「扶養義務」が、必ずしも「同居して直接介護を行う義務」ではないという点です。主な内容は、扶養が必要な親族が自力で生活できない場合に、経済的な援助を行うことです。
・生活費(仕送りなど)の援助
・医療費の負担
・介護サービス費用や施設費用の援助
などが挙げられます。つまり、「自分が直接介護しなければ法律違反になる」と考える必要はありません。大切なのは、親が必要な支援を受けられるように、自分にできる範囲で経済的・手続き的なサポートを行うことです。
親の介護…しないとどうなる?

親が要介護状態にもかかわらず、まったく支援が行われていない状況が続くと、さまざまな問題が生じます。
まず、親自身の健康が悪化する可能性があり、転倒や事故によるけが、医療や介護の不足による生活破綻といった深刻なリスクがあります。
また、極端な放置が認められた場合、子どもが「保護責任者遺棄罪」(刑法第218条)に問われる可能性もゼロではありません。
さらに、親族や近隣との関係悪化や、社会的な非難を受けることも考えられます。こうした事態を避けるためにも、どんな形であれ介護の手段を確保しておくことが重要です。
このように考えると、「何もしない」という選択は、親を危険にさらし、結果的に自分自身にも法的なリスクや社会的な困難をもたらす可能性が高いのです。どのような形であれ、親が必要な支援を受けられる体制を整えることが重要になります。
親の介護をできるだけしないための方法
ここからは、介護の負担を減らすための3つの方法を紹介します。状況に合わせて、これらの方法を検討してみましょう。
在宅サービスをフル活用する

在宅介護を選択した場合でも、介護保険でさまざまなサービスが利用可能です。
訪問介護(ホームヘルプ)は、食事や入浴、排せつの介助、掃除や洗濯などの生活援助を、訪問看護では、医療的なケアを自宅で受けられます。デイサービスを利用すれば、日中は施設で機能訓練やレクリエーションなどを受けることができ、家族の負担軽減につながります。また、ショートステイは施設に宿泊できるので、緊急時や介護者の休息に役立ちます。
これらを利用するためには、まず要介護認定を受ける必要があります。認定後、ケアマネジャーが親の状況や希望に沿ったケアプランを作成し、必要なサービスを組み合わせてくれます。専門家の力を借りることが負担軽減のポイントです。
施設を利用する
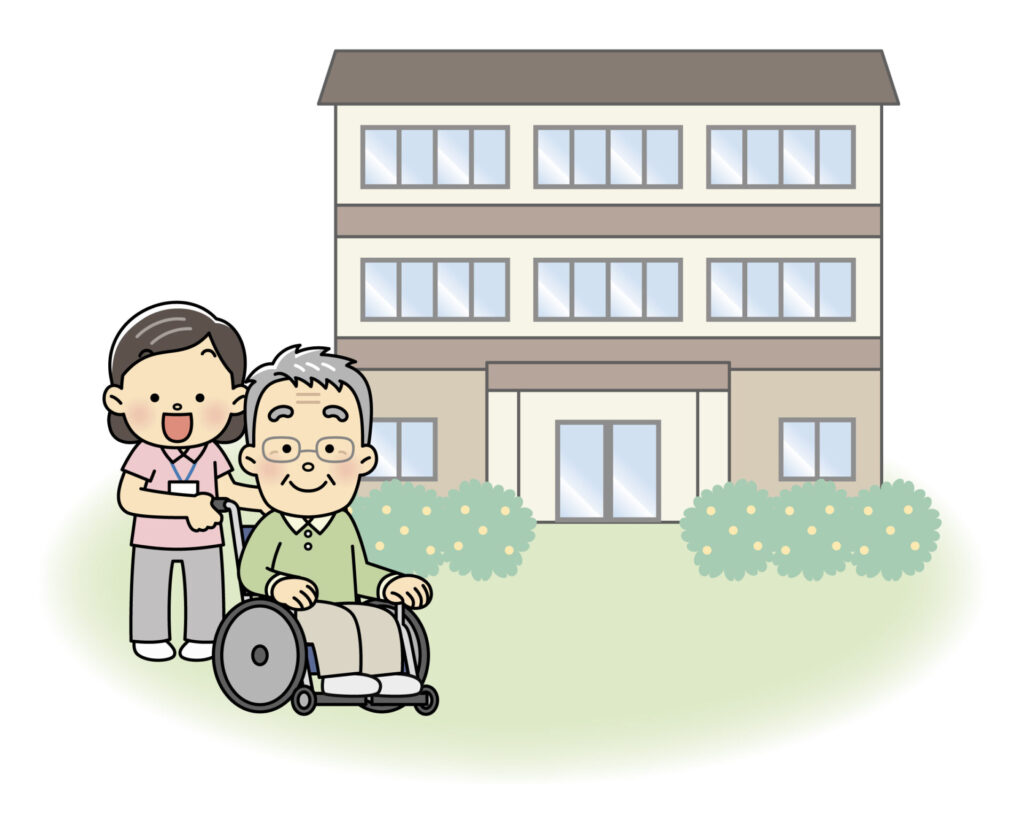
在宅介護に限界を感じた場合や、親との生活を切り離したい場合は、介護施設への入居を検討するのも選択肢の一つです。
たとえば、公的施設の特別養護老人ホーム(特養)は、比較的安価な費用で利用可能です。ただし、要介護度や待機状況によっては入所が難しい場合も。一方で、民間が運営する有料老人ホームは、費用は高めですが、サービス内容や設備が充実し選択肢が豊富です。認知症ケアに特化したグループホームもあります。親の状態や希望、予算に合う施設を選びましょう。
親族や兄弟姉妹で分担する

自分一人で介護を抱え込むと、どうしても限界がきやすくなります。もし兄弟姉妹や親族がいるなら、協力体制を築くことを考えましょう。費用分担や介護の交代など、具体的に話し合うことが大切です。
複数人で分担すれば、一人当たりの負担が減り、介護離職や心身の疲弊を防ぎやすくなります。ただし、価値観の違いや物理的な距離があると、調整が難航することもあるため、冷静な話し合いと第三者の助言を活用するとスムーズに進めやすくなります。
親に介護が必要になる前に準備しておきたいこと
介護が必要になってから慌てないためには、事前の準備が大切です。ここでは、介護が本格化する前に備えておきたいポイントを紹介します。
早めの話し合いと情報収集
親が元気なうちに介護の話をするのは気まずく、後回しにしがちです。しかしいざという時、本人の意思が確認できない、時間がない、という事態も考えられます。そのため、できれば、親の健康状態や持病、介護保険申請のタイミングといった情報を少しずつ共有しておくのが理想です。
また自宅で暮らしたいか、施設を希望するか等の意向確認も大切です。家のバリアフリー化や生活環境(階段、トイレ等)の改修についても確認しておきましょう。
将来への備え(エンディングノート・任意後見)

親がまだ判断能力をしっかり持っているうちに、将来に備える仕組みを整えておくと、いざというときに安心です。
たとえばエンディングノートを活用して、延命治療に関する希望や財産の扱い、葬儀の形などを事前に書き留めてもらうことで、家族が迷わずに対応できます。
さらに、任意後見制度を利用すれば、将来もし親が判断力を失った場合にも、あらかじめ指定された後見人が契約や手続きを代行できるようになります。介護やお金のことを話すのは気が重いかもしれませんが、あらかじめ準備しておくことが、結果的に家族全体の安心につながります。
介護を外部に頼るためのお金が足りないときは?
介護費用が心配で、サービスの利用をためらう方もいるでしょう。しかし、公的な支援制度などを上手に活用すれば、経済的な負担を軽くできる場合があります。
公的制度や補助を確認し、利用する

①介護保険を申請し、要介護認定を受ける
まずはお住まいの市区町村の窓口で介護保険を申請し、「要介護認定」を受ける必要があります。要介護認定を受けた後は、原則として1〜3割の自己負担で介護サービスを利用できます。
②高額介護サービス費制度を利用する
介護サービスの自己負担額が月ごとの上限額を超えた場合、その超過分は後日払い戻しされます。
③高額医療・高額介護合算療養費制度を利用する
医療費と介護費の自己負担額(保険適用分)が1年間で合算して一定の上限額を超えた場合、その超過分が払い戻される制度です。
④医療費控除の対象になることもある
介護サービスの自己負担分のうち、医療費に該当するもの(例:訪問看護や通所リハビリなど)は、確定申告時に「医療費控除」の対象になる場合があります。
きょうだいとの費用分担・リバースモーゲージなど

介護費用が工面できないときは、きょうだいと話し合い、可能な範囲で費用分担を検討しましょう。少しずつの協力でも大きな助けになります。
また実家が持ち家である場合、リバースモーゲージも選択肢です。これは、親の自宅を担保に融資を受け、親の生存中は利息のみを支払い、亡くなった後に自宅を売却して返済する仕組みです。利用には相続人の同意が必要なため、事前に家族で十分に話し合っておきましょう。(詳しくはこちら)
親の介護について悩んだときの考え方と頼れる相談先

親の介護をしたくない」「負担が大きい」と感じても、決して自分を責める必要はありません。 それは特別なことではなく、多くの人が抱える可能性のある自然な感情です。 大切なのは、その気持ちを否定せず、一人で抱え込まないこと。外部の支援や専門家を頼ることで、現実的な解決策が見えてくることもあります。
外部を頼るのは親不孝ではない
介護の話になると、「自分で世話をしないと親不孝だ」という考えにとらわれる方も少なくありません。
特に日本では「家族のことは家族で」という価値観が根強くあります。しかし、介護は体力も気力も必要であり、一人で抱え込むのは非常に負担が大きいものです。無理をした結果、自分の健康が損なわれてしまっては、親の世話すらできなくなるおそれもあります。
一方で、プロの手を借りることで、親が快適で安全な環境で生活できるようになることもあります。「自分でやらないことが親不孝」なのではなく、「最善の形で親を支える」ことが大切なのです。
困った時の主な公的相談窓口

介護に関して困ったときに相談できる公的な相談窓口を知っておくことが大切です。一人で悩まず、専門家のアドバイスを得ながら解決策を見つけていきましょう。
①地域包括支援センター
高齢者の健康や暮らし全般に関する幅広い相談を受け付けている総合的な窓口です。市区町村が設置または委託しています。
介護保険サービスの利用方法、要介護認定の申請、地域のサービス情報、権利擁護など、介護に関する幅広い相談に無料で対応してくれます。
まずどこに相談すれば良いか迷ったら、ここが第一候補です。所在地は市区町村のホームページで確認できます。
②市区町村の介護保険担当課(高齢福祉課など名称はさまざま)

役所内にある介護保険の担当部署です。介護保険料、保険給付、高額介護サービス費などの費用助成制度に関する詳しい説明や手続きについて相談できます。
さらに、自治体独自の高齢者福祉サービスや住宅改修(バリアフリー化)の補助金などについても相談可能です。
まとめ

親の介護を「したくない」と感じるのは、決して珍しいことではありません。仕事や家庭との両立の難しさや、親子関係の複雑さ、さらには精神的・身体的な負担など、そこにはさまざまな事情が関係しています。
大切なのは、自分を責めることではなく、まずはその気持ちを認めることです。そして、どのようなかたちで関われるのか、自分にとって無理のない方法を探すことが、現実的な一歩になります。
介護は一人で抱え込むものではありません。在宅介護サービスや施設の利用、家族との分担、公的制度の活用など、頼れる手段は数多くあります。地域の相談窓口なども積極的に活用しながら、少しずつ状況を整えていきましょう。
▼ 当サイト「悩ミカタ」ではミドル世代(40代50代)の悩みや不安・ストレスについて各分野の専門家/カウンセラーに相談できるオンラインカウンセリングサービス「悩ミカタ相談室」を展開しています。不安な気持ち、1人で抱え込まずにまずはお気軽に相談してみませんか?