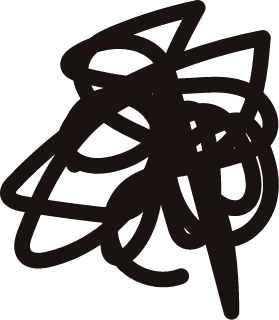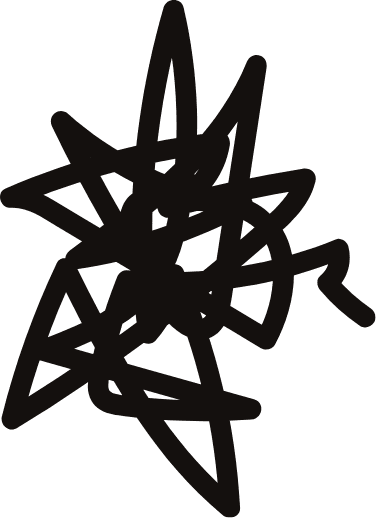「どうしてもこだわるのをやめられない」「あの人はなぜあんな些細なことにこだわるの?」そんな風に悩んでいませんか?その悩みの背景には「アスペルガー症候群」が隠れているかもしれません。今回は、アスペルガー症候群とは何かを解説し、アスペルガー症候群のこだわりの具体例や対処法についてご紹介します。

臨床心理士・公認心理師
佐藤セイさん
公認心理師・臨床心理士。現在、スクールカウンセラー(中学・高校)・非常勤講師(大学)として勤務しつつ、webライターやブックライターとしても活動中。カウンセラー・講師・ライターのどの立場であっても、受け取る人にとって、消化しやすい言葉や表現を選ぶことを心掛けています。
アスペルガー症候群とは?
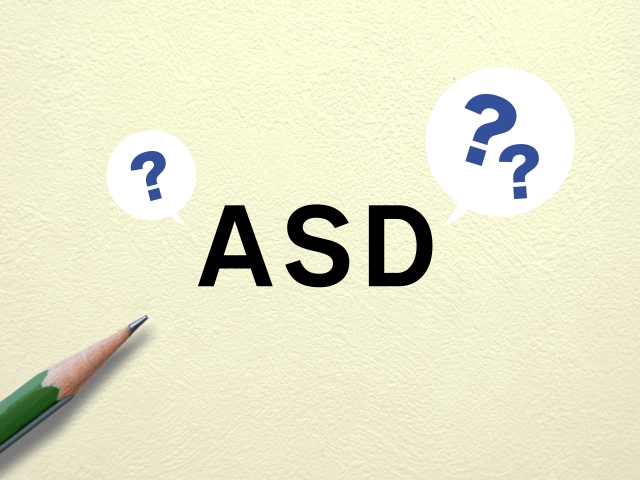
まず、アスペルガー症候群とは、どのような状態を指すのかを解説します。
①アスペルガー症候群の定義
アスペルガー症候群とは発達障害のひとつ。知的な遅れや言語発達の遅れはない一方で、他者とやり取りする能力(対人的相互反応)が生まれつき乏しく、こだわり(常同的な行動)がよく見られるのが特徴です。より詳しい特徴を以下にまとめてみました。
対人的相互反応の障害
□他者とのコミュニケーションに必要な非言語的行動がない(視線を交わす、表情、姿勢、ジェスチャーなど)
□仲間関係をつくることに失敗する
□楽しみや興味、達成感を他者と分かち合うことを自発的にしない(見せたり、持ってきたりしないなど)
常同的な行動
□限定された1つのモノやパターンに熱中する
□機能的でない習慣や儀式にかたくなにこだわる
□いつも同じ不自然な運動を何度も繰り返す(手や指をぱたぱたさせる、曲げるなど)
□物体の一部に持続的に熱中する
知的な遅れや言語の遅れがない分、子どもの頃に気づかれなかったり、大人になっても「変な人」として扱われていたりすることがあります。
なお、現在の診断基準では「アスペルガー症候群」という用語は使われていません。代わりに「自閉スペクトラム症」という診断が下されるようになりました。
②自閉スペクトラム症(ASD)とアスペルガー症候群の関係
以前の診断基準である「DSM-4-TR」や「ICD-10」では、対人的相互反応の障害と常同行動が見られつつ、
・知的な遅れや言語発達の遅れがあるものを「自閉症」
・知的な遅れや言語発達の遅れがないものを「アスペルガー症候群」
として別々に診断していました。
しかし、研究が進むにつれ、アスペルガー症候群と自閉症の境界は曖昧であり、はっきり区別するのは難しいことが分かってきました。
そこで、スペクトラム(連続体)として1つのカテゴリーにまとめようという動きが起こり、DSM-4-TRが「DSM-5」へ、ICD-10が「ICD-11」へ改訂されるに伴って、現在では「自閉症」と「アスペルガー症候群」の2つを合わせた「自閉スペクトラム症(ASD:Autism Spectrum Disorder)」が正式な診断名となりました。
つまり、アスペルガー症候群という言葉は、診断名としては使われなくなったのです。現在では、アスペルガー症候群の人も「自閉スペクトラム症」という診断名で呼ばれます。
③アスペルガー症候群の特性

アスペルガー症候群の5つの特性を整理してみました。
コミュニケーションの障害
・話し言葉の意味をとらえることが難しい
・指示代名詞(「あれ」「それ」など)や程度を示す言葉(「ちょっと」「適度に」など)など曖昧な表現は理解できない
・表情やジェスチャーなどによる非言語的なメッセージが読み取れない
イマジネーションの障害
・先の展開が予想できず、先回りして動けない
・気持ちなどの目に見えないものは想像できない
固執性保持の傾向
・興味が著しく偏っており、同じことをやりつづける
・変化に対して抵抗する
・自分の見た景色でしかものが見えず、相手の立場に立てない
感覚の過敏/鈍麻
・感覚が非常に過敏であったり、鈍かったりする
協調運動の困難さ
・協調運動とは「手と足」や「目と手」など複数の身体部位を調整しながら行う運動のこと。アスペルガー症候群では協調運動が困難で、年齢にそぐわないほど不器用な場合がある
アスペルガー症候群の大人はどんなことにこだわる?
ではアスペルガー症候群の大人はどのようなことにこだわるのでしょうか。3つの例を見てみましょう。
①アスペルガー症候群の大人のこだわり【例1】食事

アスペルガー症候群の人は、食事の食べ方が奇妙だったり、偏食だったりします。
例えば、Aさんは白米とカレーを別々に食べることはできますが、カレーライスの白米とカレーが混ざることがとても苦手です。また、寿司のネタとシャリを一緒に食べることができず、分けて食べます。
客観的に見れば、あまり行儀のよくない食べ方ですし、これまでに何度も注意されてきましたが、Aさんは自分の食べ方にこだわっています。
②アスペルガー症候群の大人のこだわり【例2】服装

アスペルガー症候群の人は、周囲の環境・状況に関わらず、自分のルールを貫く傾向があります。
例えば、Bさんには暑くても寒くても、「10〜6月はジャケットを着用する」という自分ルールがあります。6月でも真夏日が続く今年も、Bさんはジャケットをはおり、汗だくで出勤します。ほかの人たちからは「ジャケットは脱いだ方がいいよ」と言われますが、7月になるまで脱ぐつもりはありません。
③アスペルガー症候群の大人のこだわり【例3】仕事

アスペルガー症候群の人は、仕事でも様々なこだわりを見せます。
慣れ親しんだルールや手順にこだわる
仕事の手順を説明しても独自のやり方を頑として変えないことがあります。
細部にこだわる
上司から「仕上げておいて」と指示された書類についてレイアウトやフォントなど細部までこだわって、いつまで経っても仕上がらない、ということがあります。
突然の変更に耐えられない
取引先の都合で会議時間が変更になりパニック。「どうしてこっちが合わせないといけないんだ」と無理にでも元の時間に会議を始めることがあります。
アスペルガー症候群のこだわりの理由
なぜアスペルガー症候群の人たちは、強いこだわりを持つのでしょうか?その理由にはアスペルガー症候群の特性が関係しています。
①感覚過敏で刺激に耐えられない

アスペルガー症候群(ASD)の人は、感覚が過敏なことが多く、食べ方などにこだわりを持つことがあります。
例えば、口のなかで白米とほかの食べ物が混ざる「触覚」や「味覚」の気持ち悪さに耐えられず、白米だけ食べて、ほかのものはあとで別に食べる……といった行儀の悪い食べ方になってしまうことがあります。
②イマジネーションの障害による見通しの持ちづらさ
私たちは、いつもと違うことが起きても「次はこうなるだろう」と見通しが持てます。例えば、バスが5分遅れても「5分くらいなら間に合うな」とこれからのおおよその見通しを持ち、気持ちを落ち着けることができます。
ところが、アスペルガー症候群(ASD)の人は、イマジネーションの障害があるため、見通しを持つことが苦手です。バスが遅れると「この先どうすればいいんだ」とパニックになってしまいます。
見通しが持てないアスペルガー症候群の人にとって、変化は不安や恐怖をもたらすものです。変化による強い不安や恐怖を回避するため、いつも決まったルールや手順であることにこだわっているのです。
③固執性保持の傾向による自己中心性
アスペルガー症候群の人は、固執性保持の傾向によって「他者の視点から物を見る」ということができません。「もしかして事情があるのかも」と想像することができないのです。
そのため、他者の事情よりも、自分のルールを優先します。例えば、取引先の都合で会議の時間が変更になると「どうして取引先の都合ばかり優先されるんだ!」「時間は守るべきだ!」と怒り、こだわります。「取引先にも何かあったのかも」といった事情はまったく省みられません。
こだわりの強さによる困り感を減らすための対処法

こだわりの強さによって困った事態に陥った経験のある人もいるでしょう。ここでは、こだわりの強さによる困り感を軽減するための対処法をご紹介します。
①こだわりが実現できないときの対処法を考える
アスペルガー症候群の人は、こだわりによって不快や不安から回避しようとします。
しかし、いつでもこだわりが実現できる訳ではありません。こだわりが実現できないとき、パニックにならないための対処法も考えておきましょう。
例えば、以下のような方法です。
・誰かに相談する
・不安を紙に書き出し、1つ1つ対処法を考えてみる
・1人になれる場所でクールダウンする
・自分を落ち着けるグッズを使う(好きな風景画像を見る、触り心地のいいタオルを握る、アロマオイルをつけたハンカチを嗅ぐ)
②こだわりを活かせる環境を見つける

こだわりの強さは、適切な環境では大きな強みにもなります。1つの物事に集中する特性を活かすことで、自己実現や成功につながることもあります。
職人や専門家としての仕事
繰り返し行う作業や、集中を要する仕事に向いています。
マニュアルがある仕事
明確なルールや手順がある環境は、こだわりを活かしやすい傾向があります。
同じパターンで進められる業務
一貫性のある作業は、安定したパフォーマンスを発揮しやすいです。
③こだわりをできる範囲で手放してみる
こだわりを手放すことが難しい場合でも、少しずつ手放してみることで新しい発見や楽しさを得られるかもしれません。手放すことで得られるメリットを意識することがポイントです。
例えば、「6月中はジャケットを羽織る」というこだわりを手放し、涼しいお気に入りのシャツを着ることで、快適さと喜びを得られます。これまで通りの方法を手放し、新しい方法を試すことで、より仕事が効率化する可能性もあります。
手放すためには、小さなこだわりから試してみましょう。
1.「こだわり」を書き出してみる
2.自分にとって手放せそうな順に並べてみる
3.最も手放せそうなこだわりから手放してみる
4.手放した後のポジティブな体験を記録する
家族や職場など周囲の人ができるサポートとは?

アスペルガー症候群の人に対し、家族や職場などで実践できる具体的な支援方法を紹介します。
①感覚の過敏さは苦手とする刺激を避ける配慮を
感覚の過敏さにより「こだわり」が出現するときは、苦手とする刺激を避けるよう配慮すると良いでしょう。例えば、次のような対処です。
・視覚過敏:照明の明るさを落とす、サングラスをかける
・聴覚過敏:音を小さくする、イヤーマフをする
・嗅覚過敏:においの元を除去する、マスクをする
・味覚過敏:本人の食べやすい食器や盛り付けを工夫する、無理に食べさせない
・触覚過敏:本人の心地の良い肌ざわりのものを選ぶ
②変化や変更は事前に伝える
アスペルガー症候群の人は、環境の変化や予測不能な状況に強いストレスを感じ、落ち着くために「こだわり」の行動が出てきます。そのため、変化や変更については事前に伝えることが大切です。
マニュアルを作成する
変化のパターンがいくつかある場合、「パターンAは〇〇すればいい。パターンBは××すればいい」というマニュアルを作成し、変化が予測できるようにしておきます。
事前に変更点を伝える
突発的な変更にならないように、できるだけ早めに変更予定を伝えておきます。
ゴールを明確にする
「適当に」「ちゃんと」などの指示では、どこまでやればいいのかが判断できず、「完璧」までこだわってしまいます。具体的な指示を出しましょう。
③こだわらないメリットを伝える
こだわりを無理にやめさせる必要はありませんが、こだわらなくても良い環境にするサポートはできます。
それは「こだわらないメリットを伝える」という方法。「あなたの方法もいいけれど、こっちの方法だとリスクが少ないよ」「こっちの方法だとメリットがあるよ」と伝えてみます。
本人が納得できれば、こだわりを1つ手放すきっかけになるでしょう。
「アスペルガー症候群かも」と思ったときの相談先
自分や家族が「アスペルガー症候群かもしれない」と感じた場合、早めに相談先を見つけて適切なサポートを受けることが大切です。以下に、具体的な相談先をご紹介します。
①医療機関

最初のステップとして、医療機関の受診を検討しましょう。
精神科や心療内科を受診すると良いでしょう。また、医療機関によっては「成人期発達障害外来」「大人の発達障害外来」などの外来を立ち上げている場合もあります。
日常生活や仕事に支障を感じている場合は早めの受診がおすすめです。
基本的に予約制です。電話(医療機関によってはメールなど)で予約を取りましょう。
アスペルガー症候群に関して受診するときには、
・母子手帳
・通知表
など、子どもの頃の様子がわかる資料が求められます。用意しておきましょう。
②発達障害者支援センター

発達障害者支援センターとは、発達障害者を総合的に支援するための専門機関です。
都道府県や政令指定都市などに設置されており、発達障害者や発達障害の可能性がある人、その家族からの様々な相談に対応しています。
発達障害者支援センターを利用する手順は以下の通りです。
1.発達障害者支援センターを検索
地域の発達障害者支援センターのホームページを探してみましょう。
2.相談予約をする
ホームページを見つけたら、相談予約しましょう。多くの場合は電話ですが、メールやファックスで予約できるところもあります。
まとめ
アスペルガー症候群(現:自閉スペクトラム症)の特徴であるこだわりは、ネガティブに見られがちですが、「1つの物事に集中できる」や「決められたことは徹底してやり遂げる」といったポジティブな側面も持ち合わせています。今回ご紹介した方法を参考にしながら、ぜひこだわりと上手に付き合う工夫をしてみてください。
▼ 当サイト「悩ミカタ」ではミドル世代(40代50代)の悩みや不安・ストレスについて各分野の専門家/カウンセラーに相談できるオンラインカウンセリングサービス「悩ミカタ相談室」を展開しています。不安な気持ち、1人で抱え込まずにまずはお気軽に相談してみませんか?
40代50代のお悩み” は専門家に相談しよう「悩ミカタ相談室」
参考文献
日本心理臨床学会[編](2011)心理臨床学事典 丸善出版.
野島一彦[監修](2022)臨床心理学中事典 遠見書房
市橋秀夫[監修](2018)大人の発達障害 生きづらさへの理解と対処 講談社