上司や同僚との関係がうまくいかず「もしかして自分はモラルハラスメント(モラハラ)を受けているのではないか」と不安を感じていませんか?
本記事では、モラハラに該当すると考えられる職場でのパターンやモラハラの加害者・被害者になりやすい人の特徴、万が一受けてしまった際の適切な対処方法までを詳しく解説します。「毎日職場に行くのが怖い」「繰り返される暴言に心が疲れ果てている」そんな方は、この記事を一歩踏み出すための参考にしてみてください。
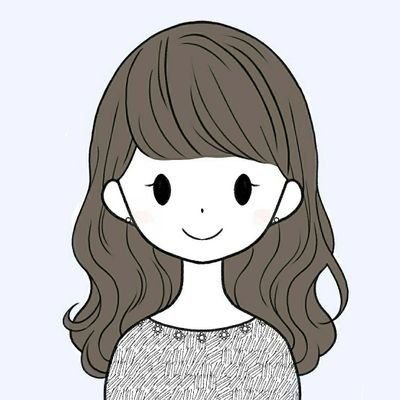
梅田ミズキさん
認定心理士、サービス介助士。大学で臨床心理学・産業組織心理学・発達心理学などを学び、卒業後は公的施設にて精神疾患の方のケアや介助業務、ご家族の相談対応などに従事しながら、ホームページ掲載用のコラムやミニ新聞を執筆。現在はフリーライターとして独立し、くらしにまつわるエッセイの執筆、臨床心理・発達支援・療育関連のコンテンツ制作および書籍編集に携わりながら、心理カウンセラーも務めている。趣味は読書、映画鑑賞、気まぐれで向かうプチ旅行。
職場でのモラハラとは

モラルハラスメント(以下:モラハラ)は、モラル(道徳・倫理)へのハラスメント(嫌がらせ)という言葉の通り、言動で相手の尊厳や人格を傷つけ、精神的な苦痛を与える行為を指します。職場での人間関係において、誰もが経験する可能性のある問題です。
モラハラの定義
「モラハラ」という言葉を提唱したのは、フランスの精神科医マリー=フランス・イルゴイエンヌという女性です。 イルゴイエンヌ氏はモラハラに関する著書を複数出版しており、ハラスメント研究の第一人者として知られています。
イルゴイエンヌ氏が挙げているモラハラの特徴は、以下の5つです。
①精神的な嫌がらせ
②身体的な暴力はない
③他者に見えにくい形で行為が行われる
④加害者は被害者以外への人当たりが良い
⑤被害者は自分が悪いと思い込みやすい
しかし、モラハラは法律で明確に定義されているわけではありません。そのうえ、身体的な暴力を伴わないため周囲から見過ごされやすく、被害者自身も「これはモラハラなのかな?」と判断に迷いやすいのが特徴といえます。
モラハラが与える被害者への影響
前述したとおり、モラハラは法律で定義されているわけでもなければ、身体的な怪我のように目に見えやすいわけでもありません。しかし、モラハラを受け続けると、心身にさまざまな影響が現れます。
例えば、不眠や食欲不振などの身体症状、不安や抑うつなどの精神症状、さらには自己肯定感の低下や社会不安などです。状況によっては、長期的に影響を及ぼす場合もあります。
筆者が実際にお受けした相談例では「休日前になると胃が痛くなる」「月曜日の朝、会社に行くのが怖い」「自分はダメな人間なのかもしれないと思えてくる」といった声が多く聞かれます。これらの症状は、決して個人の弱さが原因ではありません。
職場特有のモラハラの特徴
職場でのモラハラは、立場や権力関係を利用して行われるのが特徴です。退職に追い込むことを目的とした嫌がらせや、昇進・異動に関する不当な扱いなど、職場特有の攻撃があります。
例えば、挙げられるのは「あの部署に異動させられたら、きっと辞めるだろう」との意図での不当な配置転換や「この仕事ができないなら、評価は下げざるを得ない」といった脅しめいた言動などです。
パワハラとの違いとは?

モラハラと似ている代表的な言葉が「パワーハラスメント(以下:パワハラ)」です。パワハラとは、社長や上司など職場内で優位な立場にある人が、その地位や権限(=パワー)を悪用して下の人に行う嫌がらせを指します。
似て非なるこの二つの言葉には、以下のような違いがあります。
攻撃性のわかりやすさ
パワハラが主に業務上の立場や権限を利用した嫌がらせであるのに対し、モラハラは精神的な攻撃や操作が中心です。パワハラは比較的わかりやすい形で現れますが、モラハラは巧妙で見えにくい特徴があります。
例えば、パワハラの場合「この書類を今すぐ作り直せ!」という明確な形での指示や叱責が多いのが特徴です。一方モラハラの場合「こんな書類じゃ使えないわね。まあ、あなたに期待してなかったけど」というように、相手の人格を否定するような言動で現れます。
干渉される範囲
職場内でのパワハラは、主に、業務時間内での過度な叱責や無理な業務命令が中心です。一方で職場内でのモラハラは「休日の過ごし方まで批判される」「プライベートな人間関係に口出しされる」などの状況が発生します。このように、モラハラはパワハラと比べて、被害者の私生活や人間関係全般まで干渉されるのが特徴です。
認定の難しさ
パワハラの場合「深夜まで残業を強要された」「必要以上に大きな声で叱責された」など、具体的な事実を示しやすい傾向にあります。しかし、モラハラの場合「なんとなく無視されている」「さりげない嫌味を言われる」など、微妙な行為が積み重なるケースが少なくありません。そのため、モラハラはパワハラに比べて証拠が残りにくく、客観的な判断が難しいといえます。
あなたも被害者…?モラハラチェックリスト

「もしかして、私がいまされているのってモラハラ…?」
ここまで記事をお読みになり、そう感じている方もいらっしゃるかもしれません。以下に挙げる経験に心当たりがある場合、モラハラの可能性を疑う必要があります。もしも日常的にこれらの行為を受けているとすれば、単なる「人間関係の行き違い」ではないかもしれません。
□上司や同僚から、人格を否定するような言葉を投げかけられることがある
□陰口を言われているのを耳にする
□周囲から孤立させられているような感覚がある
□プライバシーを侵害されることが頻繁にある
□業務に必要な情報や資料が適切に共有されない
□明らかに対応が困難な業務量や、不可能な納期を設定される
業務を意図的に妨げられるようなモラハラ被害は、心理的なダメージが深刻です。最終的に、休職や退職に追い込まれるケースも見られます。
モラハラのよくあるパターンとは?

職場でのモラハラには、いくつかの典型的なパターンが存在します。ご自分の状況をより客観的に評価できるように「もしかして…?」と当てはまるものがないか確認しながらお読みください。
過度な監視と干渉
常に行動を監視され、些細なことまで報告を求められる状況です。休憩時間の使い方や、業務外の活動についても過度に干渉される場合があります。
また、休日の過ごし方や家族のことなど、業務に関係のない私的な事柄を執拗に聞かれたり、本人の同意なく他者に話されるなども珍しくありません。なかには、SNSでの投稿内容をチェックされるなど、プライベートな領域にまで監視の目が及ぶパターンもみられます。
▼具体的な言動の例
- 「トイレが長すぎるんじゃない?」
- 「昼休みにそんなところで誰と話してたの?」
- 「先週末のSNSの投稿、仕事に支障が出そうだからやめたら?」
- 「週末は何をしていたの?誰と会ってたの?」
- 「独身なのにそんなに遅くまで何してるの?」
情報操作による業務妨害
必要な情報を意図的に与えない、あるいは誤った情報を提供するなどして仕事を妨害します。また、他の従業員との情報共有を制限して、孤立化を図る手法もみられるのが特徴です。
主な例としては、会議や打ち合わせの情報が伝えられない、社内メールのCCから外される、昼食に誘われないなどが挙げられます。必要な書類やデータへのアクセスが制限され、業務遂行に支障をきたしてしまう場合もあります。
▼具体的な言動の例
- 「その案件、もう別の人に任せた」
- 「君には難しいと思って、あえて声をかけなかったんだ」
- 「あれ、連絡してなかった?忘れてた」
- 「私たちだけで話を進めたほうが効率的だから」
評価の操作と人格否定
実績や努力を正当に評価せず、些細なミスを過度に非難します。人格を否定する発言を繰り返して言葉で追い詰めたり、継続的に自尊心を傷つけて自信を喪失させようとする状況です。
また、一人で対応できる範囲を大きく超える業務量を抱えさせられたり、達成が物理的に困難な締め切りを課されたりします。そのような無理な要求で生じた遅延や失敗に対して、容赦のない叱責を受ける場合も少なくありません。
▼具体的な言動の例
- 「あなたには向いていない」
- 「他の人なら余裕でできる量だよ」
- 「期待はずれだった」
- 「前回のプロジェクトもそうだったけど、やっぱり期待できないね」
- 「そうやって要領が悪いから、いつまでたっても成長しないんじゃない?」
- 「そのくらいのミスで落ち込むなんて、社会人として未熟」
モラハラの加害者になりやすい人の特徴とは?
モラハラの加害者になりやすいのは、以下のような特徴を持つ人です。
完璧主義な人

自分の価値観や基準を絶対視して合わない相手を否定しがちな人は、モラハラの加害者になりやすい傾向があります。些細な違いや失敗に対しても寛容さを持てず、過度な要求や批判を繰り返すのです。「私ならこうするわ」「なぜこんな簡単なことができないの?」と、自分の基準を押し付けてしまいます。
他者へのコントロール欲求が強い人

他者をコントロールして自己の存在価値を確認しようとする人も、モラハラの加害者になりやすい傾向です。部下や同僚の私生活にまで干渉し、自分の思い通りにならないと攻撃的になります。「私の言うことを聞かないと、あなたのためにならないよ」「あなたのことを考えて言ってるのに」などの言葉で、支配欲求を正当化するケースも珍しくありません。
他者への共感性が低い人
相手の立場や感情を理解する能力が低く、自分の言動が他者に与える影響を認識しにくい傾向のある人です。被害者が苦しんでいることに気づかないか、あるいは気づいても重要視しません。「そんなことで傷つくなんてあなたが気にしすぎよ」「私はあなたのことを思って言ってるのに、なぜ分からないの?」といった発言が特徴的です。
自信過剰または極端に自信がない人

極端な自信過剰で自己愛が強い人は、自分の考えや行動が絶対的に正しいと信じ、他者の意見や感情を軽視しがちです。一方、極端に自信がない人は、自身の不安や劣等感を他者への攻撃的な言動で補おうとする傾向があります。いずれの場合も、相手の立場や気持ちを考慮せず一方的なコミュニケーションになりやすいため、結果としてモラハラの言動につながりやすいのです。
責任転嫁が習慣化している人
自分の失敗や間違いを認めることができず、常に他者に責任を転嫁する傾向のある人です。自己防衛の意識が強く、問題が発生した際に「あの人が適切に対応していれば」「部下の能力が足りないから」と、他者を非難する形で自分を正当化しようとします。このような責任転嫁の習慣が、部下や同僚へのモラハラ的な言動を引き起こす原因となり得るのです。
過去にハラスメント被害を受けていた人
過去にハラスメント被害を経験した人のなかには、その苦しい経験が癒えないまま、無意識のうちに同じような加害行為を繰り返してしまう場合があります。「自分もつらい思いをしてきたのだから」という意識や、過去の被害経験による心の傷が、他者への不適切な言動になって現れるのです。特に、部下や後輩に対して、自身が経験した理不尽な扱いを同様に行ってしまう傾向がみられます。
モラハラの被害者になりやすい人の特徴とは?
一方、モラハラの被害者になりやすい人にも特徴があります。ただし、これは被害者に責任があるという意味ではありません。自己防衛の手段を考えるための第一歩として、ぜひ参考にしてみてください。
人へ配慮をしすぎてしまう人
周囲への気遣いが強く、自分の感情や意見を主張するのを躊躇する傾向がある人です。相手の要求を断れず、過度な負担を抱え込みやすい性格といえます。「相手の気持ちを考えるとNOと言えない」「周りに迷惑をかけたくない」との思いから、不当な要求も受け入れてしまいがちです。
自己主張が苦手な人
自分の権利や立場を主張するのが苦手で、不当な扱いを受けても声を上げられない人も、モラハラの被害者になりやすい傾向があります。「自分が我慢すれば状況は良くなる」「言い返したら、もっと状況が悪くなるかもしれない」「私が我慢すれば、きっと分かってくれるはず」との考えに縛られているのが特徴です。
責任感が強くて真面目な人
与えられた仕事に対して強い責任感を持ち、期待に応えようと努力する真面目さが、加害者からの過度な要求を受け入れてしまう原因になる場合もあります。「自分がもっと頑張れば解決するはず」「期待に応えなければ」という思いから、無理な要求も断れない状況に陥りやすいのです。
周囲の期待に過剰に応えようとする人
仕事への責任感が強く、周囲からの要望や期待に「NO」と言えない傾向にある人も、モラハラの被害者になりやすい特徴があります。「迷惑をかけたくない」という思いから、無理な要求でも引き受けてしまいます。一度引き受けた仕事は「何としても成し遂げなければ」と考えるため、自身の限界を超えた負担を抱え込んでしまいやすいのです。
完璧主義で自分に厳しい人
常に高い目標を掲げ、些細なミスも許せない完璧主義の傾向がある人も、モラハラの被害に遭いやすい傾向があります。失敗や間違いが起きた際に「全て自分の責任だ」と考え、周囲からの不当な批判も「自分が至らないからだ」と受け入れてしまうのです。
この自己否定的な考え方は、加害者からの心理的な攻撃に対する抵抗力を弱め、精神的なダメージをより深刻なものにしてしまう可能性があります。また、自分を責める習慣が強いため、助けを求めることも躊躇しがちです。
「モラハラを受けている」と感じたときにできる対処法
ここまでお読みになり「やっぱり自分が受けているのはモラハラのようだ」と落ち込んでいる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、具体的な対処方法を知れば、状況の改善に向けて行動を起こしやすくなります。これからご紹介する対処法を無理のないペースで実践しながら、できることから始めていきましょう。
モラハラを受けた際の記録を取る

職場でモラハラを受けた日時、場所、状況、証人の有無など、できるだけ詳細な記録を残します。メールやメッセージは保存し、できれば音声録音なども行いましょう。あなたが残した記録は、後の相談や対応の際の重要な証拠になります。具体的には、以下のような記録を残すのがおすすめです。
・いつ、どこで、誰から、どのような言動を受けたか
・その場に居合わせた人は誰か
・その結果、どのような影響があったか
・相談記録(相談日時、相談先、対応内容など)
スマートフォンのメモ機能やノートなどを活用し、できるだけ客観的な事実を記録していきましょう。
モラハラ行為への明確な境界線を設定する
過度な要求や不適切な行為に対して、明確な境界線を設定します。「それは私の業務範囲を超えています」「プライベートな質問にはお答えできません」など、適切な言葉での拒否もときには必要です。
具体的には、以下のような対応例が挙げられます。
・「申し訳ありませんが、それは業務とは関係のない内容かと思います」
・「その件については、上司の方に直接ご確認いただけますでしょうか」
・「休憩時間は、個人の時間として使わせていただきたいと思います」
上記のような返答を、落ち着いて冷静に伝える姿勢が重要です。
一人で抱え込まず信頼できる人に相談をする

職場でモラハラを受けているつらい気持ちは、一人で抱え込まず、信頼できる人に相談しましょう。第三者への相談で、新たな視点や解決策が見つかる場合も多くあります。
相談する際は、記録した具体的な事実を基に説明しましょう。より適切なアドバイスを得やすくなります。また、気持ちを外に吐き出すことで、精神的な負担の軽減も期待できるでしょう。
なお職場のモラハラの相談先については、後述いたします。
退職を視野に入れる

上記の方法でも期待通りの結果が得られず、職場に居心地の悪さを感じるような場合には、退職を検討するのも一つの手段です。日々の業務を行ううえで、職場の雰囲気や人間関係は非常に重要な要素となります。「どうしても自分にとって快適に働ける環境ではない」と感じる際に別の職場に移る選択肢を考えるのは、悪いことではありません。
モラハラの相談先について
「自分一人では解決できそうになくて心配」「専門的な人に間へ入ってもらいたい」そんな気持ちをお持ちの方に向けて、モラハラの被害を受けた際に活用できる相談窓口や支援機関をご紹介します。一人で悩まず、専門家のサポートを積極的に検討しましょう。
職場の相談窓口

多くの企業には、ハラスメント相談窓口が設置されています。人事部門や産業医への相談も可能です。社内の状況を熟知している担当者から、具体的なアドバイスを得られる可能性があります。
労働局の総合労働相談コーナー
各都道府県労働局に設置されている無料の相談窓口です。専門家が相談に乗り、必要に応じて調停なども支援します。法的な観点からのアドバイスも受けられ、企業との調整も可能です。
民間の相談機関

カウンセリング機関や弁護士事務所など、専門家による相談サービスを提供する機関を活用するのも一つでしょう。より専門的な見地からのアドバイスや、心理的なサポートを受けるられます。
また過度なモラハラ被害に遭っているのであれば、侮辱や名誉毀損として損害賠償請求を検討できます。加害者本人だけではなく、会社に対しての請求も可能です。
▼当サイト「悩ミカタ」では、ミドル世代(40代50代)の悩みや不安・ストレスについて各分野の専門家/カウンセラーに相談できるオンラインカウンセリングサービス「悩ミカタ相談室」を展開しています。つらくて不安な気持ち、1人で抱え込まずにまずはお気軽に相談してみませんか?
40代50代のお悩み” は専門家に相談しよう「悩ミカタ相談室」
モラハラをすみやかに対処してあなたらしい一歩を

職場でのモラハラは、個人の問題ではありません。組織全体で取り組むべき課題です。あなたは、健康で安全な職場環境で働く権利を持っています。
モラハラ自体があまり一般的ではないうえ、職場でのモラハラはさらに一般的ではありません。しかし「おかしい」と感じる感覚を一人で抱え込んでしまわないようにしましょう。
職場で境遇がつらい場合、この記事でご紹介した対処法を参考に行動を始めてみてください。周囲のサポートも積極的に受けながら、新しい視点や具体的な解決策を見つけていきましょう。

