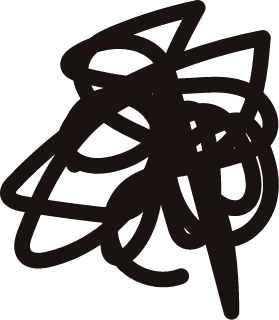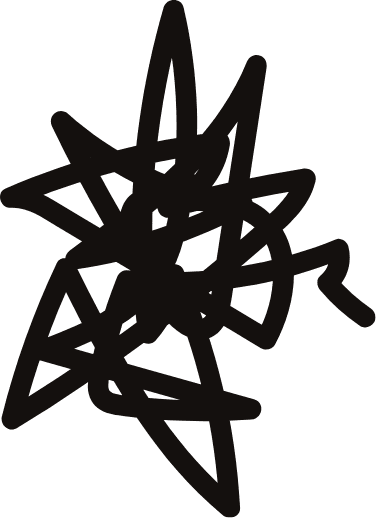朝昼構わず一日中眠くて仕方がない。夜しっかり寝ても、日中眠たくて困っている。とにかくいつも眠くて日常生活が大変。そんなお悩みを日常的に感じている方は少なくありません。
今回は、眠くて何時間も寝てしまう原因や、強すぎる眠気への対処法・解決策について解説します。

まりこさん
教育×産業の2つの領域で経験を積んだハイブリッドなカウンセラー。
教育領域では保育園・幼稚園・小学校・中学校などあらゆる現場を経験。
現在は私立小学校の教育相談スーパーバイザーを務める。
産業領域では、セルフケア・ラインケア・ハラスメントなど、メンタルヘルス系の研修講師を務める。
カウンセリングオフィスkahunaを運営。
一日中寝てしまう原因は生活習慣のストレス?
丸一日寝続けることができてしまう、寝ても寝ても寝足りない、そのような状態になる原因は一体何なのでしょうか?考えられる要因をまとめました。
過剰なストレスが影響を与えている場合
そもそも【ストレス】とは何でしょうか?
仕事上のストレス、人間関係のストレス、経済的なストレス、社会的なストレスなど、さまざまな場面で人はストレスを感じています。どのストレスにも共通するのは、何かしらの【変化】や【困難】に晒されている状態にある、ということです。
例えば、仕事上のストレスについて考えてみましょう。就職、転職、異動、昇進、リストラなど、大きな変化はストレスになります。他にも、業務量が増えた、残業が続いている、パワハラを受けているなどの困難も、分かりやすいストレスですね。
こうしたストレスがかかると、心と体が疲弊し、生活習慣が乱れて睡眠にさまざまな問題が発生します。よく聞くのは「眠れない」「寝つきが悪い」という症状ですが、逆に「寝すぎてしまう」「ずっと眠たい」といった状態になる人もいます。
いずれも、大きな変化や困難な状況によって心身にストレスがかかり、睡眠に乱れが発生した状態だといえるでしょう。
不規則な生活が影響する場合
一日中寝てしまうけれど、「特にストレスは感じていない」「思い当たるストレスはない」という方もいるかもしれません。このような方は、もしかしたら不規則な生活によって【睡眠リズム】が大きく乱れたせいで、常に眠気が消えなくなっているのかもしれませんよ。
人には体内時計が備わっており、朝の日の出と共に目が覚めて、日が落ちて夜になると自然と眠くなるようにプログラムされています。しかし、夜勤や昼夜逆転生活など、不規則な生活を続けていると、体内時計が狂ってしまいます。この狂った体内時計によって、朝晩構わず眠気が引き起こされている可能性もありますね。
単なる睡眠不足が影響する場合
ストレスはない、昼夜逆転生活もない、それなのに一日中眠い…。そんな方はシンプルに睡眠時間が足りていない可能性があります。平均的にいえば、少なくとも6時間は毎晩睡眠をとらないと、日中に強い眠気が生じやすくなります。
6時間未満の睡眠が長期間に渡って続いていると、体が【睡眠負債】を抱えた状態に陥ります。体は眠ることで睡眠負債を解消しようとしますので、常に眠気を感じるような状態が続いてしまうのです。
睡眠環境の悪さが影響する場合
ストレスはない、昼夜逆転もない、睡眠時間も毎日6時間以上しっかり寝ているのに「それでも一日中眠い」という方は、もしかしたら睡眠環境が悪く、夜間に熟睡できていないのかもしれません。
夏場なら、気温や湿度が最適ではなく、寝苦しくて何度も目が覚めてしまうことがありますよね。冬場なら、寒すぎてトイレに行きたくて何度も起きてしまうなど、寝室の環境に何かしらの問題はありませんか?
他にも、明々とした光をつけたまま寝ているとか、騒音の中で眠っているなど、睡眠の質を悪化させ熟眠を妨げる環境要因はさまざまあります。ぐっすり眠れる環境かどうか、寝具や寝室の状態にも気を配ってみましょう。
一日中寝てしまうのは病気が原因かも…?

ストレス・不規則な生活・睡眠不足・睡眠環境の悪さ、これら全てをチェックしてもあまり当てはまらないというケースもあるでしょう。その場合は、もしかしたら背景に病気が原因として隠れている場合もあるので、要注意です。
具体的にどんな病気の可能性があるのか、強い日中の眠気との関連が深い4つの病気について解説していきましょう。
うつ病
うつ病症状の一つとして過眠症状が出る場合があります。これは、うつ病の方は慢性的にストレスを抱えていることが多く、体がより睡眠を欲する状態になるからです。
また、うつ病の治療薬の副作用として、強い眠気が起こっている可能性もあります。薬を服用中の方は、一度主治医に相談してみるとよいでしょう。
ナルコレプシー
ナルコレプシーは過眠症の一種で、主な症状は、日中に突然眠り込む【睡眠発作】と、感情が高ぶると、突然全身の筋力が抜けてしまう【情動脱力発作】です。
夜はしっかりと睡眠をとっているにもかかわらず、会議中・運転中・食事中など、通常眠気が起こるとは思えない状況でも眠ってしまい、日常生活に支障が出ます。ただ、眠る時間は短く、目覚めるとスッキリした気分になるとのこと。
ナルコレプシーの原因は、脳の視床下部と呼ばれている部分が関わっているといわれています。視床下部には睡眠と覚醒を調整する役割がありますが、ナルコレプシーでは、そのバランスが崩れ、過眠症状や居眠りが起こると考えられているそうです。
特発性過眠症
特発性過眠症は日中に強い眠気が襲ってくる睡眠障害の一つで、慢性的な睡眠不足などでは説明がつかない、原因不明の日中の眠気です。ナルコレプシーと同様に、自分の意志で眠気をコントロールできず、居眠りするとは考えにくい状況で眠ってしまい、日常生活に支障が出ます。
ナルコレプシーと異なる点は、日中に突然眠り込む【睡眠発作】が1時間以上、ときには3~4時間と長く続くこと。また寝起きがよくないという人も多いようですよ。ナルコレプシーでは見られる、感情と連動する【情動脱力発作】は起こりません。
反応性過眠症
反応性過眠症は、別名「クライネ・レビン症候群」や「反復性過眠症」と呼ばれる睡眠障害です。比較的珍しい病気で、10代に発症する傾向があります。
特徴は、過剰な眠気が続く【傾眠期】が数日から数週間続くことで、その期間は食事やトイレ以外はほぼ眠り続けてしまい、抑うつ的になることもあるようです。
その他の病気
その他にも、日中の強い眠気との関連が指摘されている病気はあります。例えば「睡眠時無呼吸症候群」など、睡眠中の無呼吸が原因でうまく眠れていないことから、日中に眠気が起きているケース。他にも、「低血糖症」といって、血糖値が急激に下がることで、脳がエネルギー不足に陥り、強い眠気が引き起こされるケースも。
病気が関係していそうな場合、大切なことは、睡眠専門医にしっかり診てもらうことです。ここで解説した病気や症状は、それぞれ治療法が異なります。自分だけで判断せず、まずは睡眠外来で専門的な検査を受けてみましょう!
一日中寝てしまうのを防ぐには

ここからは日中の眠気を予防し、日々を快適に過ごすための方法を紹介しますよ。まずは以下の1〜3の方法で、睡眠リズムが整っていくか試してみてくださいね。それでも改善しない場合は、医療機関で相談する段階だと判断しましょう。
1:起床・就寝リズムを整える
朝日の光と共に起きて、夜は寝るという、基本的な睡眠リズムを大切にしましょう。体内時計が乱れにくくなり、日中の強い眠気を予防することに繋がります。
気を付けたいのは、平日と休日で寝る時間と起きる時間が大きくずれることです。休みの日はつい寝溜めをしたくて、起床時間が遅くなりがちですが、このずれが体内時計を狂わせ、結果的に平日の日中の眠気を生み出している場合がありますからね。
体内時計を整えるためには、休日であっても平日と同じように午前中のうちに目を覚まし、日中にしっかり体を動かすことが大事です。
2 : 睡眠環境を整える
自分にとって快適に過ごせる睡眠環境になっているかどうか、寝室の状態を見直してみましょう。
見直すポイントは下記のとおりです。
- 温度や湿度
快適に眠れる温度・湿度になるよう、エアコンやサーキュレーターをうまく使う。
- 光の調整
朝、カーテンを閉め切った暗い部屋で過ごしていると、目が覚めにくくなります。昼間はなるべく日の光を浴びる。逆に、夜になったら蛍光灯の光は避け、徐々に部屋を薄暗くしていき、眠気が起こりやすい環境を作る。
- ベッド、枕、布団など寝具の快適さ
ベッドや敷布団の硬さ、枕の高さ、布団の重みなど、寝具に問題があって自分の体に負担がかかっていないか確認する。人によって快適な寝具は異なるので、自分にとって快適な寝具を見つける。
- 寝る時の服装の快適さ
寝る時に身に付ける服の素材、体の締め付け感などに問題がないか確認し、できるだけリラックスできる服を着るようこだわる。
3:食生活を改善する
食生活で気を付けるのは、【食事のリズム】と【食べる量】です。まず、朝・昼・晩と、なるべく決まった時間に食べるよう意識してみましょう。体内時計が整いやすくなりますよ。
また、食べる量は、暴飲暴食を防ぐことも意識しましょう。
お昼に血糖値が上がりやすい食べ物を一気に早食いすると、その後の急激な血糖値の下降により、抗えない強い眠気が起きてしまいます。そのため、血糖値の乱高下が起きにくい食事のメニュー、食事の量を心がけてください。
リズムよく適量を食べることが、体内時計を整え、日中の眠気を遠ざけてくれるでしょう。
4:医師に相談する
生活習慣の改善を試みても日中の強い眠気が解消されない場合は、病気の可能性を考慮して早めに医療機関を受診しましょう。その際には、睡眠の専門医がいる病院を選ぶことが重要です。正確に診断してもらい、適切な治療を受けるようにしましょう。
何科を受診したらよいか分からない、という場合は、まず睡眠外来と表記のあるクリニックや病院を受診するとよいでしょう。大学病院など大きな病院には「睡眠科」や「睡眠医療センター」などの診療科が設けられている場合もあります。
まとめ
今回は一日中眠くて寝てしまう症状の原因や、原因に応じた解決策について紹介してきました。日中の活動に支障が出るほどの眠気が続いている場合は、何か心や体に負担がかかっているサインだといえます。
生活習慣や睡眠リズムをしっかり整えてみて、それでも改善されない場合は、早めに睡眠専門医に診てもらい、適切なケアを受けてくださいね。
参考文献
・「過眠症の診断と治療 : ナルコレプシーを中心に(セミナー,<特集>眠りの科学)」ファルマシア/46 巻 (2010) 11 号
・「日中の過眠を訴える患者の睡眠呼吸障害以外の原因に関する後ろ向き調査研究」日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 2020年 第28巻 第 3 号