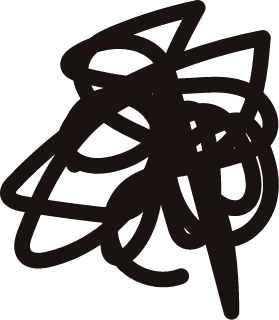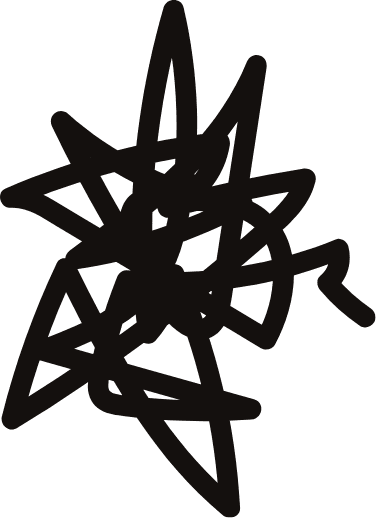親の介護について考えたとき、「一人っ子の自分がすべてを背負うことになるのでは」と不安を感じる方は少なくありません。精神的な負担や経済的な心配、周囲に頼れる人がいない孤独感など、悩みはさまざまです。
そこでこの記事では、一人っ子ならではの課題に向き合いながら、事前にできる準備、公的支援の使い方、実際の介護事例などを紹介します。無理なく介護と向き合うための現実的な考え方を、一緒に整理していきましょう。
関連記事はこちら→親の介護費用はいくら?施設に入れたいけれどお金がないときの対処法や補助制度

介護福祉士・ケアマネジャー・社会福祉士
中谷ミホさん
介護福祉士、社会福祉士、ケアマネジャー、保育士。福祉系短大を卒業後、介護職員・相談員・ケアマネジャーとして介護現場で20年活躍。現在は介護業界での経験を生かし、介護に関わる記事を多く執筆。介護・福祉関連書籍の監修も手掛けている。 X(旧Twitter)
一人っ子が「親の介護」で直面しやすい5つの課題

親の介護が現実味を帯びてくると、「自分ひとりで全部背負わなければいけないのでは?」という不安に直面する一人っ子の方は少なくありません。とくに大きな課題は、以下の5つです。
1・精神的な負担の増大
介護では「在宅か施設か」「延命治療をどうするか」など、大きな決断を迫られる場面が多くあります。これをすべて一人で判断しなければならない状況は、想像以上に精神的なエネルギーを使います。
誰にも相談できずに「この選択でよかったのか」と自問し続けることも、一人っ子特有の悩みと言えるでしょう。選択のすべてに責任を負うプレッシャーが積み重なり、心の余裕がなくなっていくこともあります。
2・時間的・体力的な負担
介護には、通院の付き添い、食事や排せつの介助、掃除や洗濯といった家事支援など、日常的なサポートが伴います。仕事や家庭との両立を求められる中で、限られた時間と体力をやりくりするのは大きな負担となります。慢性的な睡眠不足や疲労感が蓄積し、自分の健康を後回しにしてしまう人も少なくありません。
3・経済的負担の集中
介護サービスの費用だけでなく、食費・交通費・おむつなどの消耗品といった実費も少なくありません。兄弟姉妹と費用を分担できない一人っ子の場合、すべてを自分で負担しなければならず、経済的なプレッシャーも重くのしかかります。貯金がみるみる減っていくことへの不安や、将来の生活資金への影響を心配する声も多く聞かれます。
4・緊急時の頼り先が見えにくい
「親が急に倒れたらどうしよう」「夜中に異変があったら?」といった緊急時の不安も、一人っ子の大きな悩みです。いざという時に頼れる人が身近にいないと、不安が大きくなります。
5・支援制度や相談先の情報不足
介護には公的な支援制度や地域の相談窓口など、活用できるサービスが数多く存在します。しかし、情報を知らなければ利用することができません。一人っ子の場合、「誰かが教えてくれる」ということが少ないため、自ら積極的に調べておく必要があります。
一人っ子が知っておきたい「介護が始まる前」の基礎知識と準備

親の介護は、思いがけず突然始まることがよくあります。例えば、転倒や入院をきっかけに「明日から介護が必要です」と言われることも珍しくありません。
こうした事態に慌てず対応するためにも、事前の準備と情報収集がとても大切です。特に一人っ子の場合は、相談できる相手が限られているため、早めに準備しておくことで安心感が得られます。では具体的にどんなことを準備しておけばいいのかについて、以下にご紹介します。
1・家族での話し合いを早めに
介護の備えで最も大切なのは、親本人の意思を確認しておくことです。
- どのような暮らし方を希望しているか
- 介護が必要になったとき、在宅と施設のどちらを希望するか
- 誰に何を頼みたいか
元気なうちにこうした話をしておくと、後々の判断に迷いが少なくなります。話を切り出しにくい場合は、「いざというときに困らないように話しておきたい」と率直に伝えることが大切です。
2・介護保険制度の基本を押さえる
介護保険制度は、介護を必要とする人を行政がサポートする公的な社会保険です。主に自立が難しくなった高齢者を対象に、介護サービスを経済的に支援する仕組みとなっています。概要は以下の通りです。
- 介護保険サービスは、原則65歳から利用できる
- 介護保険サービスを利用するには、事前に市区町村に申請し「要介護認定」を受ける必要がある
- 認定までには申請・調査・審査を経るため、早めの申請が重要
「まだ早い」と思っていても、いざというときに慌てないよう、制度の仕組みを前もって理解しておくことが大きな備えとなります。
3・地域包括支援センターを活用する
「どこに相談すればいいか分からない」というときは、親の住所を管轄する地域包括支援センターに相談しましょう。高齢者に関する地域の総合相談・支援を行う機関であり、本格的な介護が始まる前から関わっておくと心強い味方になります。
地域包括支援センターの運営主体は市区町村で、中学校校区に1つの割合で全国に設置されています。
4・介護情報を記録に残しておく
将来の混乱を避けるためにも、以下のような情報は日頃から書き留めておくと役立ちます。
- 親の持病・服薬内容
- 通院先・主治医
- 介護の希望(例:在宅か施設か、避けたいこと、希望するサポート内容)
スマホのメモ機能やノートに、気づいたときに少しずつ記録するだけでも大きな安心につながります。
一人で抱え込まない!親の介護を支える支援の選び方と実践法
親の介護を一人で担うのは、体力的にも精神的にも大きな負担です。「限界を感じる前に支援を頼る」ことが、無理なく続けるための大切なポイントです。
ここでは、一人っ子でも安心して介護を続けるための方法と支援の選び方をご紹介します。
1・在宅介護と施設介護、どう選ぶ?
介護の方法は、大きく分けて次の2つがあります。
在宅介護

自宅で生活を続けながら、必要に応じて介護保険サービスを利用する方法です。自宅で暮らし続けるために、親の状態や生活環境に合わせてサービスを上手に組み合わせることが大切です。(例:訪問介護、デイサービス、ショートステイなど)
施設介護

生活の場そのものを施設に移す方法です。元気なうちから入居できる高齢者向け住宅や自立型の有料老人ホームから、常に介護が必要な人が入居する介護施設までさまざまな種類があります。施設介護を検討するときは、親の希望を尊重しつつ、費用や家族の面会のしやすさなどを踏まえて話し合いましょう。
2・ケアマネジャーは「介護のナビゲーター」

介護保険サービスを利用するには、ケアマネジャー(介護支援専門員)の存在が欠かせません。ケアマネジャーは以下のような役割を担います。
- 介護プラン(ケアプラン)の作成
- サービスの選定と手配
- 各事業者との連絡・調整
親の介護について不安なことや困ったことなどもケアマネジャーが一緒に考えてくれます。
3・民間サービスを活用する

一人っ子の場合、「頼れる人がいない」ことを前提に考える必要があります。そこで、民間のサービスをうまく取り入れて負担を軽減することも有効な手段です。経済的にすべてを任せるのは難しくても、「一部だけ」「必要なときだけ」活用することで、心身のゆとりを確保できます。
なお、民間で活用できる支援には以下のようなものがあります。
① 家事代行・見守りサービス
掃除や洗濯、ゴミ出しといった家事を代行してくれるサービスです。1回数千円程度から利用できるものもあり、定期的な訪問で親の様子をさりげなく見守ってもらえる点でも安心です。遠方に住んでいる場合の安否確認にも役立ちます
② 買い物・通院の付き添い
食材や日用品の買い物代行、病院への同行など、外出をサポートしてくれるサービスです。親の体力や足腰に不安があるとき、自分が毎回付き添うのが難しいときに重宝します。必要な時だけ依頼できるスポット利用も可能です。
③ 食事宅配・配食サービス
栄養バランスの取れた食事を自宅に届けてくれるサービスです。やわらか食、制限食(減塩・糖質制限など)にも対応している事業者もあり、健康状態に応じた食事管理ができます。調理の手間を省くことで、介護者自身の負担軽減にもつながります。
4・一人で悩まないための「つながり」を持つ
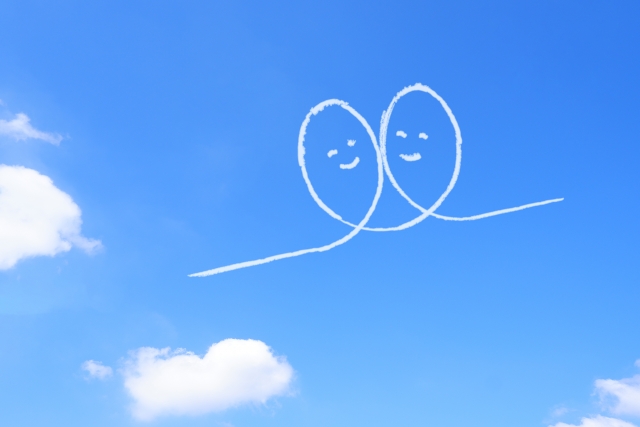
介護は孤独になりやすいからこそ、同じ立場の人と情報交換ができる場が心の支えになります。自分だけが悩んでいるわけではないと感じられるだけでも、気持ちがずいぶんと楽になります。
なお「つながり」の場には、以下のようなものがあります。ぜひ活用してみてください。
①地域の介護者向け交流会
市区町村や地域包括支援センターなどが開催している、介護者同士の交流を目的とした集まりです。直接会って話すことで、「わかってもらえた」という安心感が得られます。実際の体験談を聞いたり、サービスの使い方のヒントが得られたりと、情報交換の場としても有効です。
②自治体が主催する介護講座
介護の基礎知識や制度の使い方、認知症への対応方法など、実践的な内容が学べる講座です。プロの講師やケアマネジャーが解説してくれることも多く、「知らなかった」情報を得られる貴重な機会になります。講座をきっかけに相談窓口とのつながりが生まれることもあります。
③ SNSやオンラインコミュニティ(例:X(旧Twitter)やFacebookの介護グループなど)
ネット上のつながりでも、「悩んでいるのは自分だけじゃない」と感じられることがあります。匿名で相談しやすく、リアルでは話しづらい本音を共有できる点もメリットです。特に遠方に住んでいて地域のサポートを受けにくい一人っ子にとっては、貴重な情報源にもなります。
これらには孤立感を和らげるだけでなく、他の人の工夫や知識から学べるメリットもあります。
5・「全部自分でやらなくていい」と思えることが大切

介護は「頑張ればなんとかなる」ではなく、「どう支えてもらうか」を考えることが重要です。ひとりで抱え込まず、適切な手を借りながら進めることで、心身の余裕が生まれます。
たとえば以下のような方法で、周囲のサポートを得ることも検討してみてください。
① 公的支援を頼る
介護保険や高額介護サービス費制度など、国や自治体が提供する支援は充実しています。手続きさえすれば使えるものが多く、経済的・身体的負担の軽減に大きく役立ちます。
②ケアマネジャーに相談する
ケアマネジャーは介護のプロであり、困ったときの頼れる伴走者です。自分だけでは思いつかないサービスや制度を提案してくれる心強い存在です。
③ 民間サービスを活用する
「時間がない」「疲れている」ときに、お金をかけて誰かに任せることは悪いことではありません。必要なときに必要な分だけ取り入れる柔軟な選択が、自分を守ることにもつながります。
④ 周囲とつながりを持つ
地域の支援者やオンラインの介護者仲間とつながることで、情報や気持ちをシェアでき、孤独感が和らぎます。
これらをバランスよく取り入れることで、「一人じゃない」と感じられる環境がつくれます。
「お金がない」一人っ子が親の介護を乗り切るには?必要な知識と支援制度
親の介護には、体力や時間だけでなく、お金の負担も避けて通れません。特に一人っ子の場合、費用を分担できる兄弟姉妹がいないため、「本当に自分一人でやっていけるのか」と不安を感じる方が多いでしょう。
しかし、正しい知識と制度を活用することで、経済的な負担を軽減することは可能です。ここからは、一人っ子でも無理なく介護を続けるために役立つ費用の目安や支援制度について、お伝えします。
1・介護にかかる費用の目安を知る

介護費用は、介護の形によって大きく異なります。在宅介護なら月に4.8万円、施設介護では12.2万円と推計されています。
まずは「どのくらいかかりそうか」を大まかに把握するだけでも、気持ちの整理につながります。
2・公的制度を最大限に活用する

介護費用の自己負担を軽くするために、以下の制度をぜひ知っておきましょう。
①介護保険制度
・利用料の7~9割を公費が負担…介護サービスを利用する際、自己負担は一部で済むため、家計への大きな負担を避けやすくなります。
・自己負担は原則1~3割…所得に応じて負担割合が決まるため、低所得者にも配慮された仕組みになっています。
②高額介護サービス費制度
・一定額を超えた自己負担分は、あとで払い戻しが受けられる…月をまたいで高額になった場合でも、限度額を超えた分は戻ってくるため安心です。
・上限額は所得に応じて決まる…家計状況に見合った支援が受けられます。
③その他の制度(一例)
・介護休業給付金(会社員が介護のために休む場合の支援)…一時的に仕事を離れる必要があるとき、収入の一部が補償される制度です。
・医療費控除・障害者控除(確定申告で還付金が受けられる場合も)…年間の医療費や介護費が一定額を超える場合は、確定申告で税金の一部が戻る可能性があります。
これらを知っているだけで、受けられる支援の幅が大きく広がります。
3・市区町村の独自サービスにも注目

お住まいの地域によっては、介護保険以外に独自の高齢者福祉サービスが提供されています。以下はその一例です。
① 紙おむつの支給
要介護の高齢者に対して、紙おむつやリハビリパンツを無料または助成価格で支給する自治体があります。毎月の出費を抑えることができ、経済的な負担軽減に役立ちます。
②配食サービス
一人暮らしや高齢者世帯に、栄養バランスの取れた食事を届けてくれるサービスです。見守りも兼ねていることが多く、離れて暮らす家族にも安心です。
③ごみの訪問収集
高齢や障害によりごみ出しが難しい人のために、職員が自宅まで回収に来てくれるサービスです。自立支援と衛生環境の維持に役立ちます。
④ 介護タクシー費用の助成
通院や外出に介助が必要な人が利用する介護タクシーの費用を、一部助成している自治体があります。移動のハードルを下げ、外出機会を支える支援です。
⑤ 緊急通報装置の設置支援
急病や転倒などの緊急時にボタンひとつで通報できる装置の貸与や設置費の助成です。高齢者の在宅生活を安全に続けるうえで心強い備えになります。
親が住む市区町村にはどのようなサービスがあるか、市区町村のホームページでチェックしてみてください。
4・民間サービスも「部分的に」使えば負担は抑えられる

すべての介護を自分で抱え込む必要はありません。民間サービスを上手に取り入れることで、経済的な負担を抑えつつ、自分自身の心と体にも余裕が生まれます。
例えば、以下のようなサービスが利用できます。
① 買い物・外出の代行
食料品や日用品の買い出し、薬の受け取りなどを代行してくれるサービスです。体調や移動に不安がある親のサポートとして、手間を減らす効果があります。
② 家事代行や見守りサービス(定期利用も可能
掃除や洗濯、調理などの日常的な家事を手伝ってくれるほか、定期的に訪問して安否確認をしてくれるプランもあります。親と離れて暮らす一人っ子にとって、安心材料となるサービスです。
これらは必要なときに、必要な分だけ取り入れるのがポイントです。
5・「お金がない」と感じたら、まずは相談を
経済的な不安があるときこそ、ひとりで抱え込まずに相談することが大切です。主な相談窓口は次の通りです。
- 地域包括支援センター
- 社会福祉協議会
- 介護保険担当課(市区町村)
介護にお金がかかるのは事実ですが、制度と情報力で乗り越える道はあります。「全部自分でなんとかしなければ」と思い詰めず、まずは使える制度から一つずつ確認してみましょう。
遠方に住む一人っ子が「親の介護」でできる5つのこと
親と離れていても「できること」はたくさんあります。今の時代ならではの方法やツールを活用し、遠距離介護でも安心して関わる仕組みを整えていきましょう。
1・見守り機器を導入する

まず検討したいのが、自宅での見守り体制の整備です。
①室内カメラや人感センサー、転倒検知機能つき機器などを活用
高齢者の動きや異変をリアルタイムで把握できるため、万が一の事故や体調の変化にいち早く対応できます。設置も簡単な機器が多く、導入のハードルは年々下がっています。
②スマホで状況確認ができるサービスも多く、日常の安心材料に
アプリ連携で外出先からでも手軽に確認できるため、忙しい一人っ子でも継続的な見守りが可能です。通知機能付きで、異常があれば即座にアラートが届く仕様のものもあります。
最近は、導入コストも下がってきており、手軽に始められるものもあります。
2・定期的な帰省スケジュールを作る

常にそばにいることは難しくても、定期的に会いに行く計画を立てることは可能です。
①「月に1回」「長期休暇ごと」など、自分なりのルールを設定
無理のない頻度で訪問の予定を立てておくことで、自分自身の生活リズムを崩さずに介護に関われます。親にとっても「次に会える日」が見えることが心の支えになります。
②体調や家の様子を確認し、顔を見て話すことで安心感を得やすい
声だけでは分からない細かな変化にも気づきやすくなり、健康状態や生活の質を定期的にチェックできます。短時間でも対面の時間があることで、信頼関係の維持にもつながります。
あらかじめ予定を伝えておくことで、親にも安心してもらえます。
3・ 地域の支援機関とつながっておく

離れているからこそ、現地で親を支えてくれる人たちとの連携が重要です。
①地域包括支援センターや担当ケアマネジャーに、定期的に連絡を取る
日頃から親の様子を共有し、些細な変化にも気づいてもらえる関係を築いておくことが大切です。メールや電話で定期的にやり取りしておくと、距離があっても状況を把握しやすくなります。
②「遠距離から見守っている一人っ子」であることを事前に伝えておく
現地でのサポート体制が必要であることを明確にしておくことで、支援者側も配慮や工夫をしやすくなります。「何かあればすぐ連絡してほしい」と伝えるだけでも安心感が得られます。
「現地のパートナー」として頼れる関係を築いておくと安心です。
4・近所の協力者を確保する

身近に親戚や親の知人がいれば、緊急時の連絡先として一声かけておくことも大切です。
①近隣の親しい人に「何かあったら連絡を」とお願いする
体調不良や異変などの早期発見につながる場合もあります。信頼できる方に、簡単な連絡ルールを伝えておくと安心です。
②メールや電話番号をあらかじめ交換しておくと、いざという時にスムーズ
緊急時の連絡が遅れると対応に支障が出るため、普段から連絡手段を共有し、連絡しやすい関係性を築いておくことが重要です。
一人っ子にとって、地域に協力者がいることは精神的な支えにもなります。
5・ オンラインツールでこまめに会話する

距離がある分、コミュニケーションの回数と質がとても大切です。
①LINEやZoomなどを利用して顔を見て会話する
音声だけでなく表情や仕草も確認できるため、対面に近い安心感を得られます。定期的な「顔合わせ」を日課にするのも効果的です。
②「今日はどうだった?」の一言が、体調や気分の変化に気づくきっかけになる
小さな会話の積み重ねが、異変の早期発見につながることもあります。特に高齢の親にとっては、声を聞くだけでも励みになります。
小さな会話の積み重ねが、異変の早期発見につながることもあります。特に高齢の親にとっては、声を聞くだけでも励みになります。
一人っ子の介護体験談:無理なく続けるための現実的な工夫と支え

介護は家庭の事情や親の状態によって千差万別です。しかし、同じ「一人っ子」という立場の人がどう向き合っているかを知ることで、自分自身のヒントになることもあるでしょう。
ここでは、実際に親の介護をしている2人の一人っ子の事例をご紹介します。どちらも、完璧を目指すのではなく「できることを続ける」という視点で現実的に対応している点が共通しています。
事例①:遠距離介護をする40代会社員(関東在住/親は関西)
この方は、関東でフルタイム勤務をしながら、関西に住む親の介護に関わっています。親の転倒・入院をきっかけに介護保険を申請し、ケアマネジャーと契約しました。
- 介護保険サービス(訪問介護・デイサービス)で日常生活をサポート
- 月1~2回の帰省と、電話・ビデオ通話でこまめにフォロー
- 地元の民生委員やご近所の協力も確保
「遠くにいるからこそ、手伝ってもらう勇気が持てた」 と語ります。「頼れる体制」を作ることが、精神的なゆとりにもつながっているようです。
事例②:同居で在宅介護を続ける50代・フリーランス
こちらの方は、要介護2の母親と同居しながら、在宅介護と仕事の両立に取り組んでいます。
- 週2回のデイサービスと月4日のショートステイを利用
- 毎月ケアマネジャーとこまめにケアプランを調整
「一人でやっているという感覚は確かにある」としつつも、「関わってくれる人がいるから、ここまでやってこれた」 と話します。
完璧を目指さなくてもいい。つながりが支えになる
どちらのケースにも共通しているのは、「すべてを一人で抱え込まない工夫」をしていることです。
一人っ子という立場は、必ずしも不利なものではありません。「誰と、どう連携するか」を意識することで、状況に合った介護の形を見つけることができます。
できることから取り入れていくことで、親の介護と向き合う気持ちにも、自然と落ち着きが生まれてくるでしょう。
まとめ

親の介護は、特に一人っ子にとって不安やプレッシャーが大きくなりがちです。しかし実際には、すべてを一人で背負う必要はありません。
介護保険などの公的制度、地域の支援窓口、専門職のサポート、民間サービスなど、さまざまな支援の選択肢があります。また、見守り機器やオンラインツールなど、現代ならではの便利な手段も増えています。
大切なのは「困ったら誰かに頼っていい」という意識です。誰かに相談し、周囲の力を借りましょう。一人っ子という立場でも、適切な支援を活用すれば、無理なく親の介護を続けていく道が見つかるはずです。この記事が、これから親の介護に向き合う方の参考になれば幸いです。
▼ 当サイト「悩ミカタ」ではミドル世代(40代50代)の悩みや不安・ストレスについて各分野の専門家/カウンセラーに相談できるオンラインカウンセリングサービス「悩ミカタ相談室」を展開しています。不安な気持ち、1人で抱え込まずにまずはお気軽に相談してみませんか?