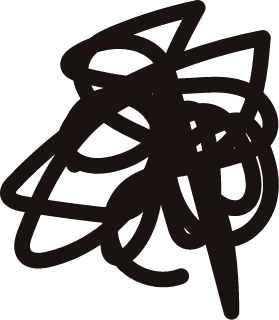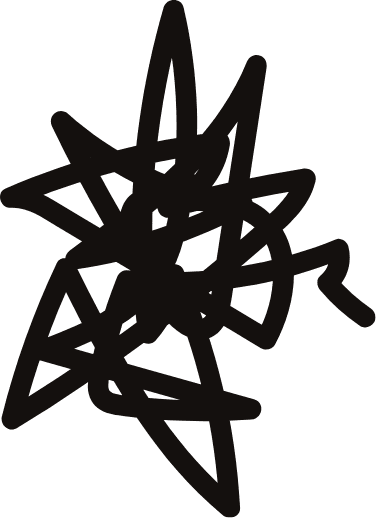介護うつは、家族の介護による身体的・精神的な疲労が重なることで発症するうつ病の一種です。眠れない、食欲がない、何をしても楽しめないといった症状が2週間以上続く状態を指します。介護うつは早期発見・早期治療が重要で、適切なケアを受ければ回復が可能であることをご存じでしょうか。
そこでこの記事では、介護うつの具体的な症状やセルフチェック、予防や治療をわかりやすく解説しています。「もしかして介護うつかも」と思っている人はこの記事を読んで、不安を少しでも解消してくださいね。

佐々木ゆりさん
公認心理師、臨床発達心理士。保育士歴は20年。現在は療育スタッフとして発達障害を持つお子さんやその家族と関わっています。発達と保育を軸に、直接支援はもちろん、webライター、保育士になりたい人の支援、保育士さん支援など幅広いキャリアを展開中です。
介護うつとはどういう状態か

介護うつでネット検索してみると「眠れない食べれない」「介護による精神的疲労」と、見るだけで辛い文面が並んでいますよね。ここでは介護うつの症状はもちろん、一般的なうつ病との違いも一緒に解説していきます。
介護うつの定義と一般的なうつ病との違い
介護うつとは正式な病名はうつ病ですが、世間的にうつ病の原因が主に介護によるものとわかっているときに使用されています。一般的なうつ病は原因がいくつかあってはっきりしない場合もありますので、原因や影響として介護があるとわかっていることが違いといえるのではないでしょうか。
介護うつの主な症状と特徴
介護うつはうつ病ですから、うつ病の患者と同じ状態であることが多い様子です。うつ病の症状としては主に
・楽しみや喜びを感じない
・何か良いことが起きても気分が晴れない
といった状態が2週間以上続き、生活する上で困っている状態をいいます。ただし、うつ病は個人差が大きく、また原因も介護だけではない場合もあります。下にチェックリストも掲載していますので、ぜひセルフチェックしてみてはいかがでしょうか。
なぜ介護者がうつ病になりやすいのか

なぜ介護者がうつ病になりやすいのでしょうか。うつ病は主な原因として「環境」「性格」「病気や障害」があげられているのですが、介護者はその3つの原因を抱えやすいと考えます。
・介護をしなければならない立場や、不安定な生活リズム、そして経済的な不安を抱えやすい状態から心身ともに負担が大きくなりやすい(環境)
・もともと責任感が強いタイプであったり、人に頼りにくい、他人の目を気にするタイプである(性格)
・介護者自身が更年期障害や糖尿病があること(病気や障害)
あてはまるものはありましたか? 次はうつ状態かどうかのチェックリストを取り上げていきますね。
あなたは当てはまる?介護うつの症状をセルフチェック

「自分は介護うつなのか気になる」「これはうつ病とは違うのだろうか」と自分の状態がうつに当てはまるかどうか気になるのではないでしょうか。
介護うつは正式な病名ではないので、ここでは一般的なこころの病気におけるチェックリストを取り上げてみました。ご自身が日頃介護について悩んでいる場合にはいわゆる「介護うつ」の可能性があります。ただし、病名は医師が総合的に判断するものです。セルフチェックをした後でもよいので、介護うつかどうかお近くの医療機関を受診するようにしてくださいね。
身体的な症状におけるチェックリスト
・眠れない、もしくは夜中に何度も起きてしまう
・食欲がない、もしくは急に食欲が増えた
・体重が減った、もしくは体重が増えた
・疲れがとれない、朝から疲れている
・頭が重い、下痢や便秘が続いている など
精神的な症状におけるチェックリスト
・気分が落ち込んでいる、常にネガティブな考えになってしまう
・何もしたくない気持ちが続いている
・不安が強い
・イライラして落ち着かない など
日常生活での変化におけるチェックリスト
・今までなかったのに、遅刻が増えている
・会話で自分からしゃべらなくなった
・人と関わりたくなくなった
・他人の目を以前よりも強く意識するようになった
・今まで楽しめていた趣味などに興味が持てなくなった など
繰り返しになりますが、うつ病は個人差がありますし、また他の病気が隠れている可能性もあります。セルフチェックがたくさん当てはまるからといってうつ病とは限りませんし、また少なくてもうつ病の可能性があります。うつ病は内科でも相談に乗ってもらえる病気です。ぜひかかりつけの医師に相談してみましょう。
介護うつの原因や介護うつになりやすい人の特徴とは?

介護うつとは主に介護が原因で、何事にもやる気がもてなかったり、睡眠不足といった状態が10日から2週間以上続き生活をする上で困っている状態のことでしたね。一口に介護が原因といっても、介護の何が原因なのでしょうか? ここでは介護うつの原因や介護うつになりやすい人の特徴を取り上げてみました。
介護うつを引き起こす主な原因や背景
介護うつは、介護による身体的・精神的疲労、経済的負担によって、脳のエネルギーが欠乏した状態といえます。また、うつ病は性格や遺伝、そして持っている病気や障害によってなりやすいこともわかっています。*1
具体的には
・トイレの手伝いやおむつ交換などで頻繁に身体を動かす必要がある
・夜間対応のため、睡眠不足になりやすい
・いつ呼び出されるかわからないので、体をゆっくり休める時間がない
・認知症があるため、暴言や暴行ががあり目が離せない
・家族や親戚から「家でみるのが一番よ」「もっと面倒をみてあげて」と言われた
・将来いつまでこの状態が続くのかわからないため、予定なども入れにくい
・介護サービスを受けたくても、経済的に余裕がないためサービスを控えてしまう
・介護のため、仕事を減らしたりやめてしまって、収入が減ってしまった
こういった周りの状況から身体的・精神的疲労が起こり、介護うつを引き起こしやすいと考えられています。
介護うつになりやすい人の特徴
介護者メンタル協会によると、介護をひとりで抱え込み、頑張りすぎている人には以下のような特徴がみられているとされています。
・義務感や責任感で介護をやろうとしている
・相談するタイミングがわからない
・自分に限界があることを認められない
・理想の介護ができない自分を責めている
※参照:介護者メンタル協会
介護における疲労などに加えて、上記の特徴をもっていると、疲労や精神的苦痛がより強くなってしまい、ゆくゆくは介護うつにつながることが考えられます。
介護うつを予防するためにできること
介護うつには身体的な原因や性格的な特徴が影響していることから、介護うつにならないためにはどうしたらよいか気になっているのではないでしょうか。ここでは今日からできる介護うつを予防するためにできることを4つ取り上げてみました。
自分の性格や見方について知っておく
介護うつになりやすいのは責任感が強く、真面目で、誰かに頼ることが苦手な性格の人でしたね。自分はそういった介護うつになりやすい性格なのかどうか、改めて知っておくと、介護サービスを使うことや、誰かと介護をする上で参考になる部分ではないでしょうか。
介護うつを予防するということは、介護する人はもちろん、介護される人に大切なことです。自分の中にある責任感や頼ることの苦手さに気づき、その上でどうしたらよいか物事を考えるようにしてみてはいかがでしょうか。
介護サービスを使う

介護うつの主な原因は介護による身体的精神的そして経済的負担が大きいことでしたね。介護サービスを使うことで、これらの負担をそれぞれ軽減できる場合があります。介護サービスは複雑で、また制度も年々変わってきています。また住んでいる場所によって受けられるサービスなども異なります。そういった介護に関する情報を提供してくれるのがケアマネジャー(介護支援専門員)です。市区町村の窓口や地域包括センター、病院などでもケアマネージャーのいる施設や事業所を紹介してもらえますので、一度問い合わせてみるとよいでしょう。
自分以外の人が介護をする機会をつくる

「自分以外の人が介護といっても誰もいない」「そもそも家族は介護を嫌がっていると思う」と考える人は多いのではないかと思います。いつも介護をしていない家族では自分と同じようにはできないかもしれませんが、少しずつ一緒に介護をやってみることからみてはどうでしょうか?
ヘルパーや看護師といったプロに頼めれば一番安心できますが、一緒にやることで疲れや不安を共有できるかもしれません。最初から介護がうまくできる人はあまりいませんので、一緒にやっていくことで家族が介護をする機会が持てるとよいですね。
ストレス解消やセルフケアを意識する

うつ病になると今まで興味があったものでも関心がなくなってしまうことが特徴です。介護うつになってしまうと、好きなことでストレス解消をしようという考えになりにくくなっているかもしれません。だからこそ、自分が好きなことを定期的にする、1日の中で介護から離れられる時間を持つと、介護うつの予防につながります。
ぜひこれを機会に昔好きだったものや音楽、運動やエンターテイメントに積極的に触れてみる、触れる時間を持つように意識してみてはいかがでしょうか。
介護うつは治るの?治し方は?
介護うつかどうか気になった場合、介護うつが治るのかどうかも当然知りたい人が多いのではないでしょうか。介護うつは、介護によるうつ病と考えた時に、病院で治療を受けることが可能です。ここでは介護うつが治るのかどうか、直し方などを、本来の病名であるうつ病を元にみていきます。
介護うつからの回復と期間

介護うつはうつ病の種類に当てはまります。うつ病は個人差こそありますが、回復する病気です。回復する期間も人によってさまざまなのが特徴です。うつ病の治療期間は一般的に、「急性期」、「回復期」、「再発予防期」と大きく3つの期間に分かれます。それぞれ個人差もありますが、「急性期」は1〜3か月、「回復期」は4〜6か月、「再発予防期」が1年からとなることが多いです。
多くの病気と同じで、うつ病になってしまったからといってまったく回復しないのではなく、かといって、再発をしない病気ではないことは知っておくとよいかもしれません。
専門家による治療とケアの方法

うつ病の場合、主に以下の3つの治療が行われます。
・休養
・薬物療法
・精神療法
などがあります。薬物療法は、その人に合わせたお薬を服用します。抑うつ薬とよばれる治療薬の他に、睡眠に問題がある場合には睡眠薬が処方されることもあります。なにより、介護うつは介護による身体的な疲労や精神的負担が原因と考えられていますので、介護者の負担を休養といった介護による負担を減らすのが治療と考えてよいかもしれませんね、
セルフケアを取り入れる

脳のエネルギー不足がうつ病、と考えると脳のエネルギーを回復するためにできることがセルフケアといえるかもしれません。
以下はこころが疲れてしまった時によく行われるセルフケアの具体例です。みなさんができそうなことはありますでしょうか?
・体の疲れをいやす
・生活の中で腹式呼吸を試してみる
・自分がイライラしているのか、不安なのかといった状態を確認してみる
・自分をほめる
・今の気持ちを書いてみる
・見方を変える(だれもわかってくれない→少しでもわかってくれる人がいればいい)
家族の介護うつに疲れたときに頼れる相談先とは?
介護は先の見えないケアです。不安になったり疲れてしまうのは当然ではないでしょうか。「どこかに頼りたい」と思った時、一体どこに相談すればよいのかわからない人もいるかもしれません。ここでは介護に関わる相談を受けてくれる場所はもちろん、自分のメンタルについて相談できる場所も取り上げてみました。
市区町村の窓口
介護におけるさまざまなサービスを無料、もしくは低価格で受けるためには市区町村の窓口にいく必要があります。市区町村によって担当する課の呼び方はさまざまですが、総合窓口で要件を話すと担当する窓口まで案内してくれます。
その際はどんなことが知りたいのか(夜、預かってくれる介護サービスに申し込みたい、補助金など経済的な支援が知りたいなど)具体的に伝えるとよいでしょう。また地域包括センターも介護の相談先です。全ての市町村にありますので、一度お住まいのセンターに問い合わせてみるのもよいでしょう。
※参照:全国の地域包括支援センターの一覧(厚生労働省のHPより)
医療機関

「眠れない」「疲れが取れない」「病気ではないか」といった心配事がいつも気になってしまう人は医療機関を受診しましょう。内科でもうつに関する相談を受け付けていることが多いですし、専門的に診てもらいたい人は心療内科や精神科などを受診するとよいでしょう。
うつ病は1度の受診ですぐよくなることはあまりありません。定期的な受診が必要になってきますので、通いやすい場所や受診をしてみて自分にあっているかどうか、といった点を踏まえるとよいかもしれませんね。
電話相談・オンライン相談

こころの健康状態はもちろん、医療機関を受診するべきかどうか悩んでいる人は相談窓口を利用してみませんか? 国が行っているこころの病気の相談窓口としては、こころの健康統一相談ダイヤルがあります。
「自分の介護うつになりやすい性格的な要素をなんとかしたい」「他にも悩み事があるから聞いてもらいたい」という人はオンライン相談室「悩ミカタ」を利用してはいかがでしょうか。オンライン相談はちょっと不安という人はまずは無料のコンシェルジュに聞いてみると、自分にあった方法やカウンセラーを紹介してもらえます。
40代50代のお悩み” は専門家に相談しよう「悩ミカタ相談室」
まとめ

介護うつは介護による負担やストレスが原因で起こるうつ病です。うつ症状からの回復には時間がかかることもあるため、予防と早期発見が大切です。市区町村の窓口や地域包括支援センターでは、介護の負担を軽減するためのサービスや支援制度について相談できますので、ぜひ一度足を運んでみましょう。
介護うつは決して珍しい症状ではなく、誰にでも起こりうるものです。一人で抱え込まず、周りと一緒に、あなたの心身の健康を大切にすることが、介護を続けるための第一歩となります。ぜひ頼ることを恐れずに、完璧にこだわらないお互いここちよい介護を探していきましょう。
*1 参考文献: 厚生労働省 こころの耳 「ご存じですか?うつ病」