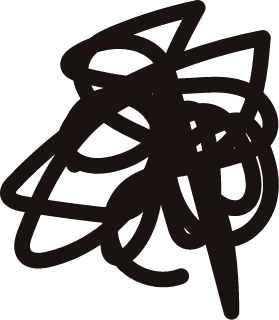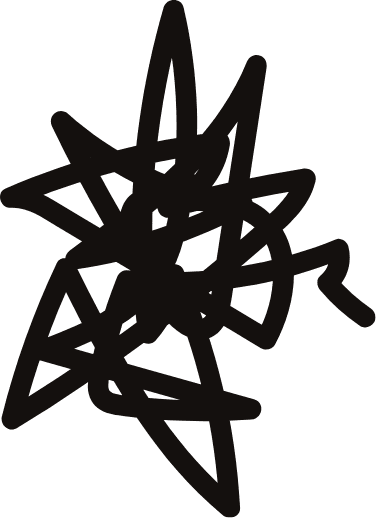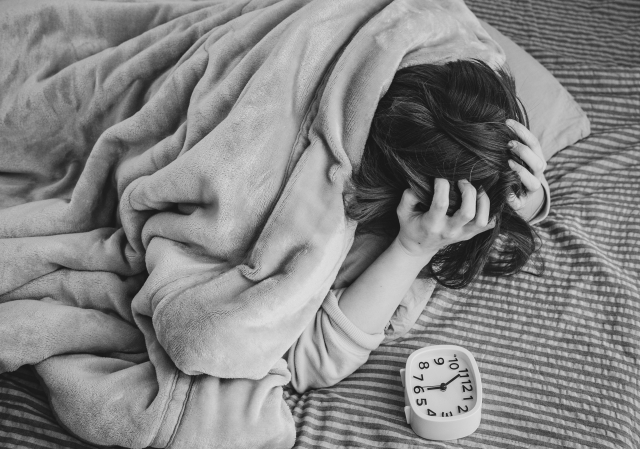最近、定時で帰れない日が増え、新しい仕事を任される機会も多くなってきた。しかし、プレッシャーや疲労が重なり、ケアレスミスが増えて上司に叱責されることも多くなっている。
そんな状況の中、朝通勤の車から職場の駐車場へ降りる際に、「仕事に行くのが怖い」と感じ、動けなくなってしまうことがある。なんとか自分を奮い立たせて出勤しているが、このままでは心身が限界を迎えてしまいそう…。こうした悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?
本記事では、「仕事に行くのが怖い」と感じる原因や心理状態、気持ちを軽くする考え方や行動のヒント、不調が続く場合の相談先 について詳しく解説します。今まさに悩んでいる方の参考になる内容をまとめていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

あーちゃんさん
公認心理師、臨床心理士。指定大学院を卒業後、街のクリニックで非常勤心理士としてカウンセリングや心理検査の業務に従事する。その後、小学校や高校のスクールカウンセラー、公的機関の電話相談員、Webライターとしても活動中。
仕事に行くのが怖いと感じる要因や心理とは?
仕事に行くのが怖いと感じる要因や心理としては、業務量や仕事内容の負荷が大きいこと、精神的にプレッシャーを感じていること、パワハラやいじめを受けていることなどが上げられます。
業務量や仕事内容、パワハラやいじめは外的要因の要素が強いですが、精神的なプレッシャーは本人の完璧主義や心配性などの内的要因が関係していることが多いです。
業務量や仕事の内容の負荷が大きい

業務量や仕事内容の負荷が大きい場合に、仕事に行くのが怖いと感じることがあります。
例えば、明らかに残業が常態化していたり、疲労やストレスが溜まり仕事の質が落ちていたりする場合などは、業務量や仕事内容が適切でない可能性が高いです。また業務量や仕事内容の負荷が大きくなる背景には、会社のコスト削減による人員不足、業務配分の不適切さ、個人のタスク管理不足などの要因があることが多いようです。
精神的にプレッシャーを感じている

仕事に対し精神的にプレッシャーを感じている場合も、仕事に行くのが怖いと感じやすいでしょう。
例えば、これまで経験したことのない仕事や、現在のスキル以上を求められるチャレンジングな仕事、動くお金が大きく人に影響を与える範囲が大きい仕事を任されるケースではプレッシャーを感じる傾向が高まります。
元々の性格傾向が完璧主義で心配性な場合は、よりプレッシャーを感じやすくなります。
パワハラやいじめを受けている
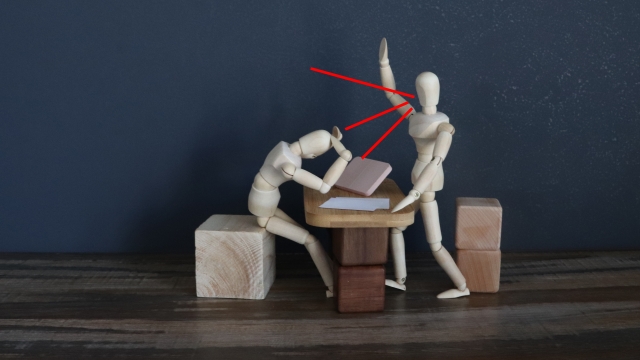
職場内でパワハラやいじめを受けている場合も、仕事に行くのが怖いと感じやすいようです。
例えば、職場の人たちに挨拶をしても無視をされる、他に人がいる前で強く叱責をされる、達成不可能なノルマを与えられる、業務のない部署に移動させるなどの行為は全てパワハラやいじめに該当します。
このような行為を受けていると心身に苦痛を感じますから、仕事に行くのが怖いと感じるのはむしろ自然なことです。
仕事への恐怖心を抱えたまま働き続けるリスクや影響
仕事への恐怖心を抱えたまま働き続けるリスクや影響としては、心身ともにエネルギーを消耗してしまうこと、仕事に集中できなくなり悪循環に陥ること、適応障害やうつ病を発症してしまうことなどが上げられます。
「これぐらいできて当然」「休むことは甘え」と言われることは多いですが、こうした言葉をうのみにすると、後々精神疾患を発症するなど長期的な悪影響を受けるリスクが高まります。
心身ともにエネルギーを消耗してしまう
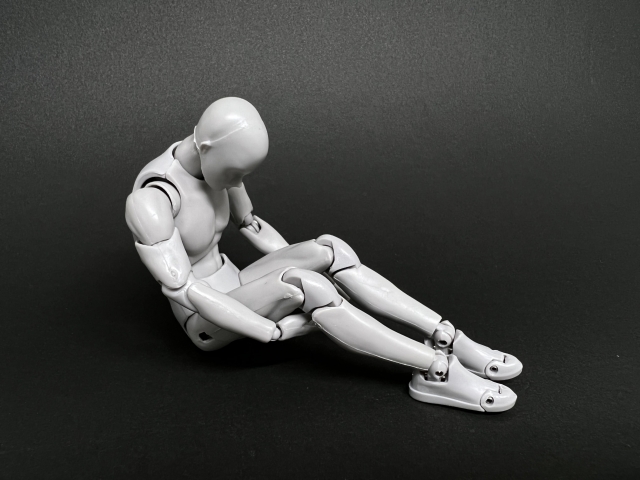
人の体は仕事への恐怖心を感じてすぐに調子が悪くなるわけではありません。
一時的なストレスであれば、休養を多めに取り気分転換を行うことで回復できます。しかし慢性的に長期的なストレスを感じ続けると、心身にさまざまな不調をきたします。
カナダの生理学者セリエは、ストレスによって心身に生じる反応を「汎適応症候群」として段階的に説明しました。
この理論によると、ストレスを受けた際の反応は 風邪をひくときの経過に似ているのだそうです。最初は心身が抵抗を示しますが、長期間ストレスが続くと次第に疲弊し、抑うつ、不安、不眠 などの症状が現れることがわかっています。
【参照元】「セルフメンタルヘルス」(厚生労働省)
仕事に集中できなくなり悪循環に陥る

仕事への恐怖心を感じ続けながら働くと、やがて仕事に集中できなくなり悪循環に陥る可能性が高まります。
例えば、「上司や先輩に叱られるのが怖い」と感じながら仕事をしていると、プレゼンの際にも「どう説明するか」よりも「上司や先輩の顔色」ばかりが気になり、集中できなくなります。
その結果、不注意によるミスが増えやすくなり、そのミスによってさらに叱責を受ける…という 悪循環に陥りがちです。
適応障害やうつ病を発症してしまう

仕事に対する恐怖を感じながらも、無理をして頑張り続けると、最終的に適応障害やうつ病を発症し、朝起きたときに動悸がして出社できない、といった状況に陥る可能性があります。
仕事の負荷や上司の叱責など、明確な要因が発生してすぐに症状が現れる場合は適応障害、一方で特に明確な原因がないのに気分の落ち込みや無気力が続く場合は、うつ病の可能性が高いとされています。
一度適応障害やうつ病を発症すると回復には服薬治療やカウンセリングが必要になり、治るまでに長い時間がかかることも多いため、早めの対策が重要です。
仕事に行くのが怖い気持ちを軽くする考え方
仕事に行くのが怖い気持ちを軽くする考え方として、ぐるぐる思考をやめること、仕事の意義を考え直すこと、人から見られる自分を意識しすぎないことなどが上げられます。
どれも自分の思考のクセを知り、より適応的な考え方や行動に修正するための方法ですので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
ぐるぐる思考をやめる

ぐるぐる思考 とは、反芻(はんすう)思考とも呼ばれ、ネガティブな出来事や気分の原因について、延々と考え続けてしまう状態を指します。
例えば、何かミスをしたときに、「なぜあんな失敗をしてしまったのだろう?」と何度も自問自答し、頭の中で繰り返し考えてしまうことがあります。「もう考えたくない」と思っても、なかなか止められないのが特徴 です。
ぐるぐる思考を防ぐには、次のような方法が効果的です。
- ぐるぐる思考に陥りやすい状況を把握する(どんな時に考えすぎてしまうのか知る)
- 運動やおしゃべりなど、意識を別のことに向ける(体を動かしたり、人と話したりする)
- 「次回はどうすればうまくいくか?」と解決策を考える(失敗の原因を責めるのではなく、前向きに対処法を考える)
このような工夫を取り入れることで、ぐるぐる思考から抜け出しやすくなります。
仕事の意義を考え直す
仕事を始めたばかりの頃は、「人の役に立ちたい」など、明確な目標を持っていた人が多いでしょう。しかし、働き続けるうちに理想通りにいかないことが増え、やがて 「自分は何のためにこんなに苦しんでいるのか?」 と疑問を抱き、仕事に行くのが怖くなることもあります。
仕事の意義を見失うと、苦しさが増してしまう ものです。そんなときは一度立ち止まって、 「私はなぜこの仕事を続けているのか?」と、自分に問いかけてみましょう。
改めて考えてみることで、思いがけないモチベーションを見つけるきっかけになるかもしれません。
人から見られる自分を意識しすぎない
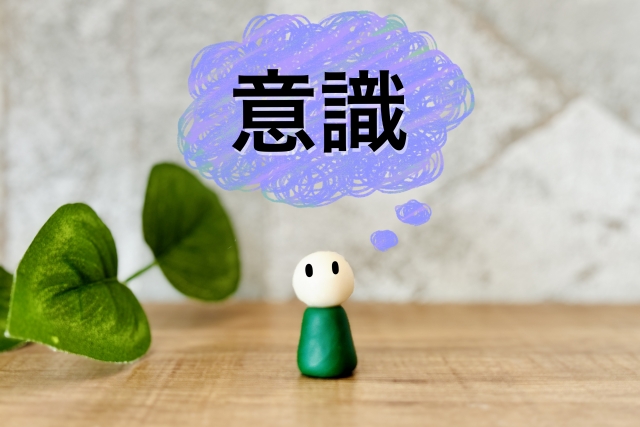
「人からどう見られているだろう」と見られる自分を意識しすぎることを「自己注意」が強い状態といいます。この自己注意が強すぎると、人前で話をすることを苦痛に感じる機会が増え、社交不安症などの原因になることもあります。
自己注意を弱めるためには、外に注意を向ける機会を増やすことがポイントです。例えば、人前でプレゼンをする機会がある際は、参加者のメガネやネクタイなどの身体的特徴に注目するといった方法でも自己注意を弱める助けになります。
慣れてきたら、自己注意と外に注意を向けることを交互にできるようになると、さらにパフォーマンスを上げることができるでしょう。
【参照元】「社交不安症の認知行動療法マニュアル」(厚生労働省)
仕事に行くのが怖いときの対処法

仕事に行くのが怖いと感じたときの対処法として、次の方法が有効です。
- 仕事に行くのが怖い理由を紙に書き出す(不安の正体を明確にする)
- 具体的にできそうな対策をピックアップする(小さな解決策を見つける)
- 課題を解消するための行動を少しずつ実践する(無理のない範囲で行動に移す)
ポイントは、最初から「怖くなくなる」ことを目指さないこと。
少しでも気持ちが楽になる方法を探し、スモールステップで前進する ことを意識すると、不安を和らげやすくなります。
仕事に行くのが怖い理由を紙に書き出す
仕事に行くのが漠然と怖く感じる理由を知りたい場合は、思いつく理由を紙に書き出してみる方法が有効です。
このように紙に書き出したり、人に話をしたりする中で自分の心の中で起きていることを第三者視点から内省するプロセスのことを「外在化」といいます。
外在化を取り入れると、問題から少し距離をとって冷静に向き合うことができるようになるため、冷静に対処策を検討しやすくなります。
【参照元】内在化と外在化のための質問(日本保険医療行動科学会)
具体的に対処できそうなことをピックアップする
仕事に行くのが怖い理由が分かってきたら、次に「具体的な対処法」を考えてみましょう。
例えば、仕事の量が多すぎてキャパオーバーになっている場合、その問題を解決するために小さなステップで対策を考えることが大切です。
具体的には、次のような方法があります。
- タスクをToDoリストで管理し、一目で把握できるようにする
- 優先順位をつけ、必要なものから順番に片付ける
- リマインダーを設定し、期限を忘れないようにする
このように、対処法を具体的な行動に落とし込むこと が、気持ちを軽くするポイントです。
課題の解消に向けて行動を起こす

仕事に行くのが怖い理由と、実践できる対処法が分かったら、次はいよいよ行動に移しましょう。
まずは、いくつかの対処法を試してみて、自分に合うものを探ることが大切です。最初から完璧に解決しようとせず、試行錯誤しながら自分に合う方法を見つけるつもりで取り組みましょう。
もし上手くいく方法が見つかったら、それを続けてみてください。小さな一歩でも、それが積み重なれば、確実に課題の解決に近づいているはず です。
仕事に行くのが怖いのは適応障害の可能性がある?

適応障害とは、特定のストレス要因により気分の落ち込みや無気力、不眠、動悸や息切れなどの症状が生じている状態を指します。
うつ病との違いは、異動や転勤などのストレス要因がはっきりとしていることです。短期的な不適応反応のため、ストレス要因が解決すれば、症状が改善し、適応の状態に戻るのが特徴です。
DSM-5(精神障害の診断と統計マニュアル 5)では、ストレス要因が生じてから3ヶ月以内に症状が出現し、ストレス要因の消失後6ヶ月以内に改善するものとされています。
「上司や先輩の叱責が怖くて仕事に行くのが怖い」と感じて、動悸や息切れがして通勤の電車に乗れないなどの症状が生じている場合は、要因がはっきりとしているため、適応障害である可能性が高まります。
【参照元】「適応障害と私」(働く人のポータルサイト こころの耳 厚生労働省)
仕事に行くのが怖い気持ちが消えないときはどうする?
仕事に行くのが怖い気持ちが消えないときは、社内の上司や人事に相談をしてみる、職場の産業医に相談をしてみるこ、医療機関の主治医や心理士を頼る、といったことなどが役立ちます。
大切なのは悩みを1人で抱え込まずに、深刻な状態になる前に、早めに職場の上司や産業医、外部機関に相談をしてつながることです。
社内の上司や人事に相談をしてみる

仕事に行くのが怖い気持ちが自分の努力だけでは解消できない場合は、社内の上司や人事に相談をしてみることも1つの手です。
傍目からはあなたが問題なく働けているように見えてしまっていて、だからこそキャパオーバーなタスクを振ってしまっている可能性もあります。そのため、ここは勇気を出して「しんどいです」と打ち明けてみることで、タスク量を調整したり、解決方法を一緒に考えたりするチャンスが作れるかもしれません。
職場の産業医に相談をしてみる

仕事に行くのが怖いと悩みを抱えているが、直属の上司には相談をしにくい内容であるといった場合は、職場の産業医に相談をしてみてもいいでしょう。
業務量の調整やハラスメントの相談をしたいが、直属の上司に相談しにくい場合は、こういった第三者的立場の専門家を頼ることで、話し合いがスムーズに進められるようになることがあります。
また、自分が適応障害かもしれないが、医療機関を受診しようか迷っているといった場合も、受診の目安について助言をもらうことができます。
医療機関の主治医や心理士を頼る

仕事に行くのが怖いと感じており、出勤時に動悸や息切れがする、夜眠れないなどの症状が出ている場合は、医療機関の主治医や心理士に相談をしてみてください。
産業医よりも外部性が高いため、職場内で話しにくいことが相談しやすいですし、生活習慣上気をつけるべきことや服薬治療、心理療法など専門的な観点から悩みの解消をサポートしてくれます。万が一、一定期間休職をしたい場合も、医療機関は休みが必要な状態かどうかを判断してくれます。
オンラインカウンセリングを活用する

「病院に行くほどではないけれど、専門家に話を聞いてもらいたい」という人には、オンライン相談もおすすめです。
▼ 当サイト「悩ミカタ」ではミドル世代(40代50代)の悩みや不安・ストレスについて各分野の専門家/カウンセラーに相談できるオンラインカウンセリングサービス「悩ミカタ相談室」を展開しています。不安な気持ち、1人で抱え込まずにまずはお気軽に相談してみませんか?
40代50代のお悩み” は専門家に相談しよう「悩ミカタ相談室」
まとめ

いかがでしたか?
仕事に行くのが怖いと感じたときは、その気持ちが大きくなってしまう前に、早めに対処することが大切です。
- 少し気になる程度なら、「ぐるぐる思考」をやめる工夫をする
- 理由が明確なら、タスク管理など具体的な対策で改善を試みる
- すでに悩みが大きくなり、一人で対処できない場合は、周囲に相談する
また、何よりも一人で抱え込まないことが重要です。職場の上司や先輩、人事、産業医、医療機関の主治医、心理士など、信頼できる人や専門家に相談し、適切なサポートを受けることも選択肢に入れましょう。
本記事が、少しでも皆さんの不安を軽くし、安心して仕事に向かえる助けになれば幸いです。